★ここのところモンスターペアレントの話題がマスメディアで取り上げられている。今日の日経新聞(朝刊070625)でも、「『クレーム親』猛威―学校に理不尽な文句・『プロ化に』現場自衛」という記事が載っていた。
★理不尽なクレームの例として
<運動会の組み体操のピラミッドで自分の子どもが一番上でないのはおかしい。母親が起きられないので学校で子供を起こして欲しい。部活動のユニホームは学校で洗って欲しい。校内で子供の携帯電話を取り上げたら『料金を日割りで負担して』と迫られた。子供にかすり傷一つつけないよう誓約書を書いて欲しい。本当は同級生に割りばしでいたずらされた程度なのに『大木で殴られた』と慰謝料を請求してきた。>などが挙げられていた。
★がしかし、理不尽は理不尽であるけれど、すべてどこかがおかしい。運動会の例は、昔からあるクレームだな。運動会だけではなく、文化祭の演劇のときの主役を誰がやるかでは、いつも意気消沈してきた親子が多いのではないか。だからといって平等な演劇というのも変ではある。これは全員が組み体操をやるべきかどうか選択判断を子供同士でやったかどうかが重要。演劇もそうだ。もし選択判断をさせずに強制的にやったとしたら、このこと自体モンスター的行為。学校行事だからしかたがないと考えているとしたら、対立軸としてモンスターペアレントは出現する。
★部活のユニホームは学校でも家庭でも、子供が自分で洗うという選択肢があってもよい。むしろそれはコモンセンスではないだろうか。そのような習慣を身につけることが重要か重要でないか子供たちに議論もさせずに、家庭で洗って来いでは、モンスター的行為だろう。対立軸のモンスターペアレントが出現するのは必然。
★校内で携帯電話を取り上げる・・・。前もってルールが共有されていれば問題ない。子供たちと保護者たちに。議論のチャンスやアンケート調査のコミュニケーションの場を設けていないのではないか。
★まるでベニスの商人のような誓約書だし、中身は検討の余地があるが、アグリメントは欧米では当然。日本社会が欧米化されているのだから、そのようなシステムは必要ではないだろうか。
★「割りばしでいたずらされた程度なのに」という感性が貧困。鉛筆でも武器になる。大げさな訴えを事実錯誤として訴える前に、小さないたずらもその根っこに何があったのか、話し合うチャンスを設けることが必要だ。
★モンスターペアレントはモンスタースクールの鏡である。クレームは、発する側にももちろん目先の問題がある。しかし、多くは発せられる側にきっかけがあるものだ。しかし、互いにそれはある。寛容な文化としてのコミュニケーション・システムが急務。
★もっともこれは臨済宗の十段階の悟りのレベル(十牛図という比喩がある)で言えば、最終レベルなのだ。だからこそ許し合う・受け入れる・相手に仕えるという構えがポイントになるのだろうが。
★理不尽なクレームの例として
<運動会の組み体操のピラミッドで自分の子どもが一番上でないのはおかしい。母親が起きられないので学校で子供を起こして欲しい。部活動のユニホームは学校で洗って欲しい。校内で子供の携帯電話を取り上げたら『料金を日割りで負担して』と迫られた。子供にかすり傷一つつけないよう誓約書を書いて欲しい。本当は同級生に割りばしでいたずらされた程度なのに『大木で殴られた』と慰謝料を請求してきた。>などが挙げられていた。
★がしかし、理不尽は理不尽であるけれど、すべてどこかがおかしい。運動会の例は、昔からあるクレームだな。運動会だけではなく、文化祭の演劇のときの主役を誰がやるかでは、いつも意気消沈してきた親子が多いのではないか。だからといって平等な演劇というのも変ではある。これは全員が組み体操をやるべきかどうか選択判断を子供同士でやったかどうかが重要。演劇もそうだ。もし選択判断をさせずに強制的にやったとしたら、このこと自体モンスター的行為。学校行事だからしかたがないと考えているとしたら、対立軸としてモンスターペアレントは出現する。
★部活のユニホームは学校でも家庭でも、子供が自分で洗うという選択肢があってもよい。むしろそれはコモンセンスではないだろうか。そのような習慣を身につけることが重要か重要でないか子供たちに議論もさせずに、家庭で洗って来いでは、モンスター的行為だろう。対立軸のモンスターペアレントが出現するのは必然。
★校内で携帯電話を取り上げる・・・。前もってルールが共有されていれば問題ない。子供たちと保護者たちに。議論のチャンスやアンケート調査のコミュニケーションの場を設けていないのではないか。
★まるでベニスの商人のような誓約書だし、中身は検討の余地があるが、アグリメントは欧米では当然。日本社会が欧米化されているのだから、そのようなシステムは必要ではないだろうか。
★「割りばしでいたずらされた程度なのに」という感性が貧困。鉛筆でも武器になる。大げさな訴えを事実錯誤として訴える前に、小さないたずらもその根っこに何があったのか、話し合うチャンスを設けることが必要だ。
★モンスターペアレントはモンスタースクールの鏡である。クレームは、発する側にももちろん目先の問題がある。しかし、多くは発せられる側にきっかけがあるものだ。しかし、互いにそれはある。寛容な文化としてのコミュニケーション・システムが急務。
★もっともこれは臨済宗の十段階の悟りのレベル(十牛図という比喩がある)で言えば、最終レベルなのだ。だからこそ許し合う・受け入れる・相手に仕えるという構えがポイントになるのだろうが。











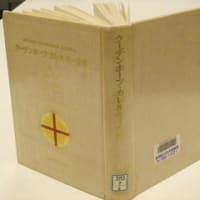


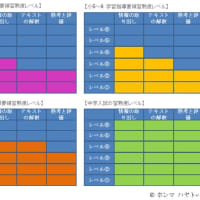
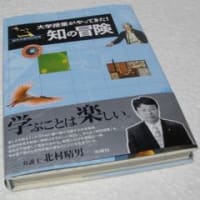
![府知事選の行方[了]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/e9/3d13aadc415722befc574b161350f584.jpg)
![府知事選の行方[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/80/2c2c23ed16365dd67e6b840f66b72c44.jpg)

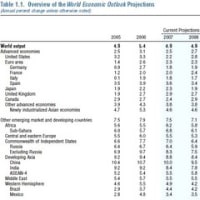
とは言え、その判断能力には、大人と同レベルを期待すべきではなく、結局ある程度の介入は必要ですが。
子供は、大人が思うより遥かに賢いが、同時に遥かに愚かですから。
子供の自主性を強調しすぎるのは、――逆説的ですが、大人の勝手であり、責務放棄です。子供には十分な判断力があると、ハナから決め付けているから。子供が自分で判断出来る部分と出来ない部分を見極める事が最も重要でしょう。
自分の携帯電話の料金を他人に負担させようというとてつもない理不尽はスルーですか?
ユニフォームのクレームは、子供に洗わせろ…ではなく、職員が洗え、という事でしょう?
幼稚園の制服は園の職員が洗えと言って来た親もいる。
…誓約書って…しまいには、スキンシップ一つでも、事前の契約書が必要になり、体育教育は不可能になりますね。『絶対未来の誓約』とはどれほど恐ろしい意味なのか、分かっているのでしょうか…
論点がどんどんずれてない?
被害妄想はキリないよ。