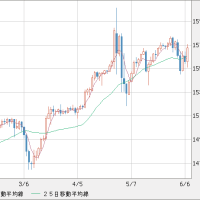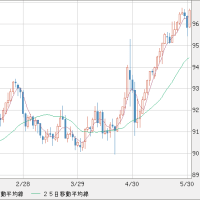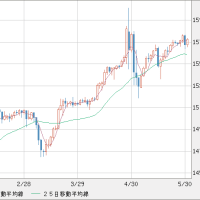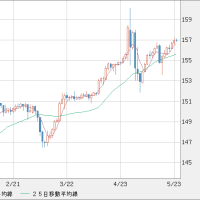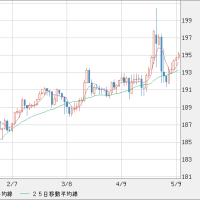文科省の大失策であるポスドク問題がただでさえ悲惨な状況に陥っているのに、
我が国の雇用市場の問題をまるっきり分かっていない厚労省が追い打ちをかけた。
彼らは官庁としてどんな大失態をしても殆ど責任を問われないから気楽なものである。
(個人の小さな不祥事は責任を問われるが組織の失態の責任はうやむやにされるのが日常茶飯事)
朝日新聞の報道によると、国内有力大学が非正規雇用の講師の雇い止め強化に動いている。
これは多くの経済学者が事前に警告していた通りの事態であり、
日本の労働者の正規・非正規の非合理的な格差を直視せず
省庁が愚劣な法改正を行った正義の味方気取りの当然の帰結である。
官庁にはアナクロニズムのマルクス経済学の事実上の信奉者が大勢おり、
「正社員として雇うのが当然」とほざいて
まるで共産主義国のような雇用政策を実現するために策動している。
お前達が安く商品やサービスを購入できるのは
サービス業で安く使われている非正規雇用のおかげだとなぜ理解できないのか。
全員正社員にするのが当然と本気で思うのなら
お前達の食費も旅行代も支出を2倍以上支払ってみせるがいい。
お前達と同じ職場で働いている非正規労働者にせめて同じ水準の時給を払うがいい。
あさましい自己欺瞞もいい加減にすべきである。
自分達は正規雇用であるのを当然視しながら、
自分達の利用する企業が非正規雇用に支えられ低価格を実現しているのを問題視しないのは
彼ら自身が特権を握りしめて放さない「赤い貴族」であることの何よりの証左である。
当ウェブログは以前より以下のような「現実」を指摘している。
「硬直した旧態依然の大学の教育システムを反省せず、
安易に教員へテニュアをバラまいて教育の質を上げる努力を怠り
少子化が分かっていたにも関わらず大学を増やした愚かな大人に
大学生を批判する資格などない」
「本格的に課題解決型の授業を導入したら日本の教授の半分はクビだろう。
彼らにはそれだけの能力がないからだ」
「日本社会や大人たちに課題解決能力が本当にあるなら
失われた20年など生じなかっただろうし
年金問題も原発問題も最初から起きなかった筈だ」
この教育分野の問題は、公共部門全体にも完全に当てはまる。
↓ 参考
小学校レベルの算数ができない大人の方が、分数のできない学生より深刻 - 教授と職員の雇用が問題の根源
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/36d01d0a1821489cb81687115c191e4e
国際教養大学の「神話」にも翳りが? -「使いにくい」との声や、日本企業の古い体質に合わず退職する例も
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d8902538260985bbc1017e10d43d3a99
▽ 文科省の施策及び日本の大学組織は、硬直性という根本的な問題を抱えている
▽ 大学改革の最大の「抵抗勢力」は教授会、グローバル化対応においても全く同じ構図
大学、5年でクビ? 非常勤講師、雇い止めの動き(朝日新聞)
http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201306140015.html
朝日新聞は労働契約法の問題として捉えているが
それだけでは充分ではない。そもそも正規雇用と非正規雇用で
身分差別的な待遇格差があるからこのような問題が起きるのだ。
(非正規雇用が正規雇用維持のためのバッファー、つまり使い捨てにされている)
世界的に見て余りにも優遇され過ぎている長期雇用の教員の社会保険料を大きく引き上げて基金を積み立て、
不安定な非正規雇用教員に所得移転するのが理の当然である。
また、より根本的には少子化の放置が大学経営を絶対的な窮地へと追い込んでいる。
合計特殊出生率を引き上げるとともに社会人が資格を得てキャリアアップする
北欧型の実学教育の拠点として大学を再編するべきである。
非常勤講師という被差別民(池田信夫)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130625-00010014-agora-soci
池田信夫教授が久々に正論を吐いてる。
原発停止で日本経済が大混乱に陥るかのような大ハズレの予言を
口走ってしまったのはご愛嬌だが、エネルギー政策等の不得意分野に言及しさえしなければ
(「小さな政府」原理主義バイアスがあるものの)傾聴すべき見解も少なくない。
この主張も完璧に正しい。
我が国の大学には長期雇用にしがみつく老人ばかりが増えて年齢構成がどんどん老化し、
彼らに研究者への道を阻まれた若者は絶望と貧困に突き落とされている。
尚、池田信夫氏はアメリカの大学にしか言及していないが、
異なる意味で競争的な北欧の大学のシステムも大いに参考になる。
北欧の大学は実学重視で、風力発電や省エネ等の新しい成長分野に合わせて
柔軟にカリキュラムを設定・新設して新しい専門家を育成する。
▽ 大学など公共部門でもリストラ・再編が日常茶飯事である
ただ絶対的な給与水準が低いので英米圏に研究者が流出する傾向があるようだ。
しかし平等性・公平性・柔軟性において日本より遥かに優っているのは間違いない。
我が国の雇用市場の問題をまるっきり分かっていない厚労省が追い打ちをかけた。
彼らは官庁としてどんな大失態をしても殆ど責任を問われないから気楽なものである。
(個人の小さな不祥事は責任を問われるが組織の失態の責任はうやむやにされるのが日常茶飯事)
朝日新聞の報道によると、国内有力大学が非正規雇用の講師の雇い止め強化に動いている。
これは多くの経済学者が事前に警告していた通りの事態であり、
日本の労働者の正規・非正規の非合理的な格差を直視せず
省庁が愚劣な法改正を行った正義の味方気取りの当然の帰結である。
官庁にはアナクロニズムのマルクス経済学の事実上の信奉者が大勢おり、
「正社員として雇うのが当然」とほざいて
まるで共産主義国のような雇用政策を実現するために策動している。
お前達が安く商品やサービスを購入できるのは
サービス業で安く使われている非正規雇用のおかげだとなぜ理解できないのか。
全員正社員にするのが当然と本気で思うのなら
お前達の食費も旅行代も支出を2倍以上支払ってみせるがいい。
お前達と同じ職場で働いている非正規労働者にせめて同じ水準の時給を払うがいい。
あさましい自己欺瞞もいい加減にすべきである。
自分達は正規雇用であるのを当然視しながら、
自分達の利用する企業が非正規雇用に支えられ低価格を実現しているのを問題視しないのは
彼ら自身が特権を握りしめて放さない「赤い貴族」であることの何よりの証左である。
当ウェブログは以前より以下のような「現実」を指摘している。
「硬直した旧態依然の大学の教育システムを反省せず、
安易に教員へテニュアをバラまいて教育の質を上げる努力を怠り
少子化が分かっていたにも関わらず大学を増やした愚かな大人に
大学生を批判する資格などない」
「本格的に課題解決型の授業を導入したら日本の教授の半分はクビだろう。
彼らにはそれだけの能力がないからだ」
「日本社会や大人たちに課題解決能力が本当にあるなら
失われた20年など生じなかっただろうし
年金問題も原発問題も最初から起きなかった筈だ」
この教育分野の問題は、公共部門全体にも完全に当てはまる。
↓ 参考
小学校レベルの算数ができない大人の方が、分数のできない学生より深刻 - 教授と職員の雇用が問題の根源
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/36d01d0a1821489cb81687115c191e4e
国際教養大学の「神話」にも翳りが? -「使いにくい」との声や、日本企業の古い体質に合わず退職する例も
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d8902538260985bbc1017e10d43d3a99
▽ 文科省の施策及び日本の大学組織は、硬直性という根本的な問題を抱えている
 | 『大学破綻 合併、身売り、倒産の内幕』(諸星裕,角川書店) |
▽ 大学改革の最大の「抵抗勢力」は教授会、グローバル化対応においても全く同じ構図
 | 『なぜ、国際教養大学で人材は育つのか』(中嶋嶺雄,祥伝社) |
大学、5年でクビ? 非常勤講師、雇い止めの動き(朝日新聞)
http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201306140015.html
”【吉田拓史、牧内昇平】有力大学の間で、1年契約などを更新しながら働いてきた非常勤講師を、原則5年で雇い止めにする動きがあることがわかった。4月に労働契約法(労契法)が改正され、5年を超えて雇うと無期契約にする必要が出てきたからだ。
■無期契約 避ける狙い
法改正は、有期契約から無期契約への切り替えを進め、雇用を安定させるためだ。だが講師たちは生活の危機にある。朝日新聞の取材で、国立の大阪大や神戸大、私立の早稲田大が規則を改めるなどして非常勤講師が働ける期間を最長で5年にしている。
大阪大と神戸大は、その理由を「法改正への対応」と明言。無期への転換を避ける狙いだ。有期の雇用契約の更新を繰り返し、通算5年を超えた場合、働き手が希望すれば無期契約に切り替えなければならなくなったからだ。
早大は、3千人以上の非常勤講師を徐々に減らす方針で、「長期雇用の期待をもたせられない」(清水敏副総長)。もともと非常勤講師以外の有期職員は上限が5年。これに合わせることも考えていたという。
一方、国立の徳島大などは、労働組合や指導現場と協議して上限を設けなかった。「地方大学は、5年で一律に辞めさせたら講師が確保できない」(徳島大)という事情もある。首都圏大学非常勤講師組合(松村比奈子委員長)によると、多くの大学が当初、契約期間の上限設定を検討したが、講師らとの協議で、撤回する例が相次いだ。
松村委員長は「解雇しにくいという理由で大学は無期転換をいやがる。だが、非常勤講師は特定の授業をするために雇われ、その授業がなくなれば解雇される。無期転換を拒む理由はない」と主張する。一方、大学側は「担当の授業がなくなっても雇用継続を主張する人も出てくる」(大阪大)と警戒する。
こうした問題を受け、政府は成長戦略で、研究者などへの労契法適用に関する課題を検討することを決めた。労契法に特例を設けるのか、別の制度で対応するのか、文部科学省と厚生労働省で検討していく。〔以下略〕”
朝日新聞は労働契約法の問題として捉えているが
それだけでは充分ではない。そもそも正規雇用と非正規雇用で
身分差別的な待遇格差があるからこのような問題が起きるのだ。
(非正規雇用が正規雇用維持のためのバッファー、つまり使い捨てにされている)
世界的に見て余りにも優遇され過ぎている長期雇用の教員の社会保険料を大きく引き上げて基金を積み立て、
不安定な非正規雇用教員に所得移転するのが理の当然である。
また、より根本的には少子化の放置が大学経営を絶対的な窮地へと追い込んでいる。
合計特殊出生率を引き上げるとともに社会人が資格を得てキャリアアップする
北欧型の実学教育の拠点として大学を再編するべきである。
非常勤講師という被差別民(池田信夫)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130625-00010014-agora-soci
”早稲田大学が、今年度から非常勤講師の契約の上限を5年と決めたことに対して、非常勤講師15人が大学を刑事告訴した。これは直接には新しい就業規則が労基法違反だという訴えだが、根本的な問題は「契約社員は5年雇ったら正社員にしなければならない」という労働契約法の規定である。
常識で考えれば、非常勤講師を5年雇ったら終身雇用にしろと規制したら、4年11ヶ月で契約を解除するのは大学経営としては当然だ。この労働契約法改正については、私を含めて多くの経済学者が反対したが、厚労省の官僚と労働政策審議会の圧倒的多数を占める労働法学者には、この程度の論理的な推論もできないのだろうか。
私も非常勤講師をしているが、同じような仕事をしながら大学ほどひどい差別をしている職場はないだろう。授業が90分で、1コマ7000円だ。往復2時間の通勤や準備や試験監督なども考えると、時給はコンビニのアルバイトと大して変わらない。他方、准教授になれば無条件にテニュア(終身在職権)が与えられ、年収は1000万円以上になる。年間200コマとしても、1コマ5万円だ。
日本のサラリーマンは非競争的にみえるが、仕事のできない社員はクビにできなくても左遷され、定年まで窓際ポストで恥をかくので、長期雇用は「恥の文化」では強いインセンティブになっている。
〔中略〕
これに対して大学教師は「専門バカ」なので、配置転換という競争が機能しない。しかも准教授になったら全員がテニュアを得るので、授業のノルマさえこなしていれば研究する義務もなく、職階がないので出世競争もない。要するに競争原理がまったく働かないので、日本の大学が先進国で最低レベルになるのは当然だ。
文科省のデータによれば、アメリカの大学教員のうちテニュアをもつのは62%で、助教授では12%しかいない。一流大学ほど要件はきびしく、ハーバード大学では2300人の教員のうちテニュアは870人しかいない。東大が世界と競争するなら、秋入学などより、非常勤も含めてすべての教員をテニュア審査してはどうだろうか。”
池田信夫教授が久々に正論を吐いてる。
原発停止で日本経済が大混乱に陥るかのような大ハズレの予言を
口走ってしまったのはご愛嬌だが、エネルギー政策等の不得意分野に言及しさえしなければ
(「小さな政府」原理主義バイアスがあるものの)傾聴すべき見解も少なくない。
この主張も完璧に正しい。
我が国の大学には長期雇用にしがみつく老人ばかりが増えて年齢構成がどんどん老化し、
彼らに研究者への道を阻まれた若者は絶望と貧困に突き落とされている。
尚、池田信夫氏はアメリカの大学にしか言及していないが、
異なる意味で競争的な北欧の大学のシステムも大いに参考になる。
北欧の大学は実学重視で、風力発電や省エネ等の新しい成長分野に合わせて
柔軟にカリキュラムを設定・新設して新しい専門家を育成する。
▽ 大学など公共部門でもリストラ・再編が日常茶飯事である
 | 『スウェーデン・パラドックス』(湯元健治/佐藤吉宗,日本経済新聞出版社) |
ただ絶対的な給与水準が低いので英米圏に研究者が流出する傾向があるようだ。
しかし平等性・公平性・柔軟性において日本より遥かに優っているのは間違いない。