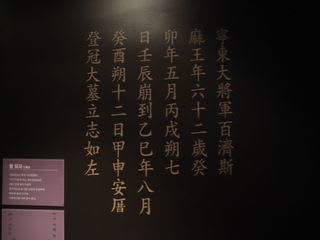コース順路:コース満足度★★★★★ 5月28日~6月04日
世界遺産チェスキークリムロフ歴史地区 → 世界遺産プラハ歴史地区 → 世界遺産ブラスチラヴァ歴史地区 → ブタペスト・ゲッレールトの丘 → ドナウ川クルーズ → 世界遺産ブタペスト歴史地区 → 王宮礼拝堂のミサ → 美術史博物館 → 世界遺産ウィーン歴史地区 → コンサート<モーツアルト&ヨハン・シュトラウス>
一度は行きたいと思っていた中央4カ国(チェコ、スロヴァキア、ハンガリー、オーストリア)の旅がやっとい実現、ショパンの母国ポーランドが加われば最高だったのだがそれは贅沢というもの、素晴らしかった旅の思い出をやっと載せることができた。
ゴシック、ルネッサンス、そしてバロック時代の建築様式を今に残す美しい町並みが並ぶチェスキークリムロフ歴史地区(世界遺産)を訪れる。
アーチ状となった入口から旧市街地区に入り、旧い建物が続く街の角を眺めるとお城の塔が見える。
大きく屈折するヴルタヴァ川(スメタナの交響詩で有名なモルダウ川)に抱かれた旧市街が美しい。



13世紀にヴィートコフ家の居城として建てられ、その後何度も増改築が繰り返されたというチェスキークリムロフ城を見渡す。
逆に城の中からの旧市街の眺めも風情がある。


世界で一番美しい街と言われるプラハ歴史地区(世界遺産)を訪れる。
まずは、14世紀のカレル4世の時代にほぼ現在の形になったと言われるプラハ城を目指す。
プラハ城の入口には、兵士が門の前に立っていて訪れる観光客を迎えてくれているのが面白い。


城の中で圧倒的な存在感を持っているのが聖ヴィート大聖堂で、どこから眺めても目立つ塔の高さは96.6mもある。
ホールの中は素晴らしく、特にミーシャがデザインしたステンドグラスの美しさは際立っている。



プラハ城からの帰りの道から旧市街を望む。
いつも賑やかというカレル橋には30体の聖像が並んでおり、そこには聖フランシスコ・ザビエルの像もある。
橋を渡った先の広場には、プラハの街の繁栄を築いた神聖ローマ帝国の皇帝カレル4世の大きな像が立っている。
12時に時を知らせるプラハ旧市庁舎の仕掛け時計、時間になって像みたいなものが動き出しさあこれからと思ったら、それだけのことですぐに終了。



竹久夢二にも通じる独特の絵で有名なミーシャの美術展を見たあと、カレル橋のすぐ脇にあるスメタナ博物館を訪れる。
スメタナの像に挨拶して中に入ると、一番の代表作である交響詩「モルダウ」の美しいメロディーが流れている。


スロヴァキアの首都ブラスチラヴァ歴史地区(世界遺産)を訪れる。
ドナウ川と旧市街を見下ろす小高い丘の上に建つブラスチラヴァ城は、テーブルを逆さにしたようなどっしりとした四角い建物で4本の塔が延びている街のシンボル的な存在。
街角から通りを覗くと、あの特徴的なお城の塔がよく見える。
かつては旧市街を取り囲んでいたという城門の一つミハエル門からは、旧市街が一望できるらしい。



街を歩くと、リストが訪れて公開演奏を行ったという家、そして立派なスロヴァキア国立歌劇場もあって、ここも音楽の都の一つという印象を訪れる人に与えている。


次に訪れたドナウの宝石ブタペストと呼ばれるハンガリーの首都の眺めの美しさ、それこそ、口には表せきれないほどのものだった。
最初に訪れたゲッレールトの丘から眺めると、その美しさの訳がよく分かる。
ドナウ川が街の中央を南北に流れ、西岸のブダは王宮を中心に歴史的建造物が並び、東岸のペストは近代的な美しい街並みが広がっている。
夜になってドナウ川クルーズに参加したが、船から見るナイト・イルミネーションされた建物の美しさは感激そのものと言って良い。


イルミネーションされた国会議事堂の眺めも素晴らしい。
896年に建国されたハンガリー、英雄広場には、初代の王イシュトバーンから19世紀の独立戦争を指揮したコッシュートなど14人の英雄像が並んでいる。


1884年に完成したヨーロッパ屈指のブタペスト国立歌劇場、その入口にはハンガリーの代表的作曲家フランツ・リストの像が立っている。



ブタペスト歴史地区(世界遺産)を歩くと、私にとってまず目に入るのはベートーヴェンが公開演奏をしたという家。
ドナウ川を見下ろすブダ側の王宮の丘から見るくさり橋、ブタとペスト地区を結ぶ鉄の鎖の吊り橋でドナウに架かる最初の橋にして最も美しい橋と言われる。


マーチャーシュ教会で一番素晴らしいと言われるのは、屋根を飾るモザイクの美しさで、本当に何度眺めても魅力的。
教会の傍には、二重の十字架を持っている聖イシュトヴァーンの騎馬像が立っている。
これは、イシュトヴァーンがこの地にキリスト教を導入したこと、ハンガリー国内の大司教を決める決定権を法王から与えられたことのふたつを意味しているという。


聖イシュトヴァーン大聖堂はブダペスト最大のルネサンス様式聖堂で、ドームの高さは96m、収容人数8000人という。
内部はモザイク画や壁画、彫刻などの装飾がすばらしく、時間をかけてゆっくりと見ていたい誘惑に駆られる。


シシィの愛称で知られるハプスブルグ家の美貌の皇妃エリザベート妃の像、美しいハンガリーの国土とブタペストの街を最も愛した故に、市民にとても愛される存在となっている。
この教会ではエリザベート皇妃の載冠式が行われ、リストはこの日のために「ハンガリー載冠ミサ曲」を作曲している。


ウィーンはなんといっても音楽の都、まずは象徴的なウィーン国立歌劇場を眺める。
ウィーンは有名な作曲家の像が多い街、早速写真を撮ろうと地図を頼りに像巡りに出発する。
道を迷いながらも偶然に遭遇したのはブラームスの像、地図にも載っていなかったので嬉しい気持ちになる。


ベート-ヴェンの像にやっとたどり着く、すぐ近くには有名なヨハン・シュトラウスの像があって、こちらには観光客も多い。


ちょうど日曜日ということで王宮礼拝堂で行われたミサに行き、シューベルトのミサ曲第6番変ホ長調を聴くことができた。。
シューベルトの代表的なミサ曲を実際のミサという形で、ウィーン国立オペラ劇場の奏者とウィーン少年合唱団の演奏で聴くという貴重な体験であった。


ウィーン歴史地区(世界遺産)を巡る旅は、マリア・テレジア像がある広場からスタート。
マリー・アントワネットの母、マリア・テレジアの偉大さを語るのは難しい。
王室に男子が生まれなかったことにより事実上の「女帝」として23歳でハプスブルグ家を継ぎ、ハンガリー王、ボへミア王、オーストリア大公という称号を持つ。
16人も子供を産み、有能な君主として40年ものあいだ君臨し続けたというから凄いの一言に尽きる。
ウィーンは音楽だけでなく、有名な美術館もあり、中でも代表的とされる美術史美術館を訪れる。
ブリューゲルの「バベルの塔」、フェルメールの「絵画芸術」、ベラスケスの「青いドレスのマルガリータ王女」、そしてラファエロの「草原の聖母」などを鑑賞する。
シェーンブルン宮殿は、ハプスブルグ家の夏の宮殿として17世紀末から建設が始まりマリア・テレジア時代に完成している。


ウィーの街並みを一望するためにシュテファン寺院を訪れたが、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトとコンスタンツェ・ウェーバーの結婚式が行われ、後には彼の葬儀もここで行われたということの方が私には印象が強い。
ベルヴェデーレ宮殿は、オスマン朝によるウィーン包囲から街を守ったオイゲン公の夏の離宮として建てられた所。
今は主にムスタフ・クリムトの代表作、「接吻」、「ユーディット」などを展示する美術館となっている。


世界遺産チェスキークリムロフ歴史地区 → 世界遺産プラハ歴史地区 → 世界遺産ブラスチラヴァ歴史地区 → ブタペスト・ゲッレールトの丘 → ドナウ川クルーズ → 世界遺産ブタペスト歴史地区 → 王宮礼拝堂のミサ → 美術史博物館 → 世界遺産ウィーン歴史地区 → コンサート<モーツアルト&ヨハン・シュトラウス>
一度は行きたいと思っていた中央4カ国(チェコ、スロヴァキア、ハンガリー、オーストリア)の旅がやっとい実現、ショパンの母国ポーランドが加われば最高だったのだがそれは贅沢というもの、素晴らしかった旅の思い出をやっと載せることができた。
ゴシック、ルネッサンス、そしてバロック時代の建築様式を今に残す美しい町並みが並ぶチェスキークリムロフ歴史地区(世界遺産)を訪れる。
アーチ状となった入口から旧市街地区に入り、旧い建物が続く街の角を眺めるとお城の塔が見える。
大きく屈折するヴルタヴァ川(スメタナの交響詩で有名なモルダウ川)に抱かれた旧市街が美しい。



13世紀にヴィートコフ家の居城として建てられ、その後何度も増改築が繰り返されたというチェスキークリムロフ城を見渡す。
逆に城の中からの旧市街の眺めも風情がある。


世界で一番美しい街と言われるプラハ歴史地区(世界遺産)を訪れる。
まずは、14世紀のカレル4世の時代にほぼ現在の形になったと言われるプラハ城を目指す。
プラハ城の入口には、兵士が門の前に立っていて訪れる観光客を迎えてくれているのが面白い。


城の中で圧倒的な存在感を持っているのが聖ヴィート大聖堂で、どこから眺めても目立つ塔の高さは96.6mもある。
ホールの中は素晴らしく、特にミーシャがデザインしたステンドグラスの美しさは際立っている。



プラハ城からの帰りの道から旧市街を望む。
いつも賑やかというカレル橋には30体の聖像が並んでおり、そこには聖フランシスコ・ザビエルの像もある。
橋を渡った先の広場には、プラハの街の繁栄を築いた神聖ローマ帝国の皇帝カレル4世の大きな像が立っている。
12時に時を知らせるプラハ旧市庁舎の仕掛け時計、時間になって像みたいなものが動き出しさあこれからと思ったら、それだけのことですぐに終了。



竹久夢二にも通じる独特の絵で有名なミーシャの美術展を見たあと、カレル橋のすぐ脇にあるスメタナ博物館を訪れる。
スメタナの像に挨拶して中に入ると、一番の代表作である交響詩「モルダウ」の美しいメロディーが流れている。


スロヴァキアの首都ブラスチラヴァ歴史地区(世界遺産)を訪れる。
ドナウ川と旧市街を見下ろす小高い丘の上に建つブラスチラヴァ城は、テーブルを逆さにしたようなどっしりとした四角い建物で4本の塔が延びている街のシンボル的な存在。
街角から通りを覗くと、あの特徴的なお城の塔がよく見える。
かつては旧市街を取り囲んでいたという城門の一つミハエル門からは、旧市街が一望できるらしい。



街を歩くと、リストが訪れて公開演奏を行ったという家、そして立派なスロヴァキア国立歌劇場もあって、ここも音楽の都の一つという印象を訪れる人に与えている。


次に訪れたドナウの宝石ブタペストと呼ばれるハンガリーの首都の眺めの美しさ、それこそ、口には表せきれないほどのものだった。
最初に訪れたゲッレールトの丘から眺めると、その美しさの訳がよく分かる。
ドナウ川が街の中央を南北に流れ、西岸のブダは王宮を中心に歴史的建造物が並び、東岸のペストは近代的な美しい街並みが広がっている。
夜になってドナウ川クルーズに参加したが、船から見るナイト・イルミネーションされた建物の美しさは感激そのものと言って良い。


イルミネーションされた国会議事堂の眺めも素晴らしい。
896年に建国されたハンガリー、英雄広場には、初代の王イシュトバーンから19世紀の独立戦争を指揮したコッシュートなど14人の英雄像が並んでいる。


1884年に完成したヨーロッパ屈指のブタペスト国立歌劇場、その入口にはハンガリーの代表的作曲家フランツ・リストの像が立っている。



ブタペスト歴史地区(世界遺産)を歩くと、私にとってまず目に入るのはベートーヴェンが公開演奏をしたという家。
ドナウ川を見下ろすブダ側の王宮の丘から見るくさり橋、ブタとペスト地区を結ぶ鉄の鎖の吊り橋でドナウに架かる最初の橋にして最も美しい橋と言われる。


マーチャーシュ教会で一番素晴らしいと言われるのは、屋根を飾るモザイクの美しさで、本当に何度眺めても魅力的。
教会の傍には、二重の十字架を持っている聖イシュトヴァーンの騎馬像が立っている。
これは、イシュトヴァーンがこの地にキリスト教を導入したこと、ハンガリー国内の大司教を決める決定権を法王から与えられたことのふたつを意味しているという。


聖イシュトヴァーン大聖堂はブダペスト最大のルネサンス様式聖堂で、ドームの高さは96m、収容人数8000人という。
内部はモザイク画や壁画、彫刻などの装飾がすばらしく、時間をかけてゆっくりと見ていたい誘惑に駆られる。


シシィの愛称で知られるハプスブルグ家の美貌の皇妃エリザベート妃の像、美しいハンガリーの国土とブタペストの街を最も愛した故に、市民にとても愛される存在となっている。
この教会ではエリザベート皇妃の載冠式が行われ、リストはこの日のために「ハンガリー載冠ミサ曲」を作曲している。


ウィーンはなんといっても音楽の都、まずは象徴的なウィーン国立歌劇場を眺める。
ウィーンは有名な作曲家の像が多い街、早速写真を撮ろうと地図を頼りに像巡りに出発する。
道を迷いながらも偶然に遭遇したのはブラームスの像、地図にも載っていなかったので嬉しい気持ちになる。


ベート-ヴェンの像にやっとたどり着く、すぐ近くには有名なヨハン・シュトラウスの像があって、こちらには観光客も多い。


ちょうど日曜日ということで王宮礼拝堂で行われたミサに行き、シューベルトのミサ曲第6番変ホ長調を聴くことができた。。
シューベルトの代表的なミサ曲を実際のミサという形で、ウィーン国立オペラ劇場の奏者とウィーン少年合唱団の演奏で聴くという貴重な体験であった。


ウィーン歴史地区(世界遺産)を巡る旅は、マリア・テレジア像がある広場からスタート。
マリー・アントワネットの母、マリア・テレジアの偉大さを語るのは難しい。
王室に男子が生まれなかったことにより事実上の「女帝」として23歳でハプスブルグ家を継ぎ、ハンガリー王、ボへミア王、オーストリア大公という称号を持つ。
16人も子供を産み、有能な君主として40年ものあいだ君臨し続けたというから凄いの一言に尽きる。
ウィーンは音楽だけでなく、有名な美術館もあり、中でも代表的とされる美術史美術館を訪れる。
ブリューゲルの「バベルの塔」、フェルメールの「絵画芸術」、ベラスケスの「青いドレスのマルガリータ王女」、そしてラファエロの「草原の聖母」などを鑑賞する。
シェーンブルン宮殿は、ハプスブルグ家の夏の宮殿として17世紀末から建設が始まりマリア・テレジア時代に完成している。


ウィーの街並みを一望するためにシュテファン寺院を訪れたが、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトとコンスタンツェ・ウェーバーの結婚式が行われ、後には彼の葬儀もここで行われたということの方が私には印象が強い。
ベルヴェデーレ宮殿は、オスマン朝によるウィーン包囲から街を守ったオイゲン公の夏の離宮として建てられた所。
今は主にムスタフ・クリムトの代表作、「接吻」、「ユーディット」などを展示する美術館となっている。