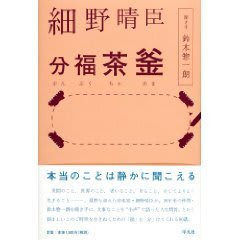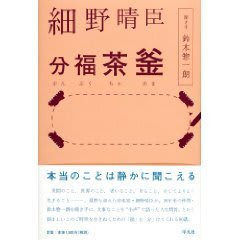
細野晴臣/鈴木惣一朗「分福茶釜」 平凡社
ああ、これはまさに「ぼくのおじさん」なんだと思った。
おじさんというのは、たとえばこんな人のことを言う。
「人類学や民俗学は、「おじさん」を特殊な存在であると見なしている。ここで言う「おじさん」とは、両親の兄弟の中で、結婚もせず、定職にもつかず、遊びほうけている連中のことを言う。
そういう「おじさん」は、共同体にとって、不要な存在であった。父親や母親は胡散臭がるが、甥や姪からは絶大な人気があった。なぜかと言うと、共同体の外にまで遊びに出かけるおじさんは、外の世界のことをよく知っていて、両親たちが絶対教えてくれないようなことを、なによりも「自由」を、教えてくれるからである。
かつては、そんな「おじさん」たちがたくさんいた」(高橋源一郎「おじさんは白馬にまたがって」)
その具体的なものとして、ジャック・タチの名作「ぼくのおじさん」があり、かつて伊丹十三が編集長を勤めた「モノンクル」という雑誌があった。この本を読む者は、細野晴臣にそんな「おじさん」的姿を見ることができるだろう(先ほど引用した高橋源一郎本人もそういう意味では「おじさん」的である。もっとも彼の場合、結婚してないどころか、5回もしてるけど。いや、その過剰性こそが「おじさん」的なんだ)。
飄々として、自由で、他の大人の感性とは違う視点からものを言う。
「今の世の中は泣かせるビジネスが溢れてて、そういうのが気持ちが悪い」と最近の風潮を嫌がってみたりしたのちに、「泣けないような悲しみっていうのがこの世にはあるんだ。人間の一番深くにある孤独感っていうのはそういうものであって、泣いたり笑ったりするのは、お酒を飲んでるのと大して変わらないものだよ」
ノンシャランとしていながら、なかなかに深い言葉だと思う。
こないだ「神楽感覚」を読んだり、ここんとこなんだか細野晴臣と縁がある。あ、そういえば、この本を読んで知ったのだが、武満徹はコシミハルを天才と呼んで高く評価してた、と。

別冊歴史読本「歴史の中のサンカ・被差別民」 新人物往来社
差別について考えている。縄文がぼくのキーワードだったのだけれど、いろいろ調べていくうちに差別に行き当たった。こういう雑誌の特集の面白いところは、1冊の中に相反する意見があったり、同じ意見を何人かがくり返していたりするところだ。
たとえば東北に被差別が少ない、また差別そのものがあまりないという点について(実は縄文的世界観の残っているところには差別が少ない)、宮台真司と網野善彦の発言は正反対だったりする。
「東北は、江戸時代後期に至るまで非常に貧しく、それゆえに社会的分業もさして進んでいなかったので「職業に貴賤なく」、それゆえに「貴賤」への「聖穢」の重ね焼きもなかった。皆が貧しくてカツカツの状況では、実は、人に「聖穢」を貼り付ける差別は起こらないのです。人に「聖穢」を貼り付ける差別は、豊かになり、階層化が進み、分業秩序を維持したり頂点を正当化する必要が出てきて、初めて登場するのです。その結果として、聖でも穢でもない―――階層の頂点で末端でもない―――膨大な人々が、方向感覚や美意識や勇気を与えられるわけです」(宮台)
しかし、網野善彦(そしてその発言はこの本にはないが赤坂憲雄なども)はそれを古く一方的な見方でしかないと退けている。
またその一方で宮台のこの発言は正鵠を得ていると思う。長くなるけど引用しちゃう。
「これまたどんな社会にもあることですが、同型的な部族社会が社会の各所に散在するような環節的=セグメンタルな段階から、これらが中心的部族によって集権的に掌握される段階になると、中心的部族の巫王だけが偉くて、後は偉くないんだという話になります。日本で言えば、飛鳥時代の朝廷成立に関わることですが、階層的な社会構成に変わっていくわけです。そのときに、どの社会でも同じなんですが、聖なるものは、ピラミッド型をした階層の頂点に存在する人に配当されます。そのときに問題になるのが、各部族で聖なるシャーマンとして機能してきた人たちがどうなるのかということです。
日本でもそれが問題になって、彼は典型的には陰陽寮に隔離的に配置され、ミカドの聖性に抵触しない範囲内で、人々の土俗的な習俗に見合った統治の装置としての機能を、過渡的には果たすわけです。やがて中央集権化が深まってくると、これも多くの社会で起こったことですが、頂点に存在する聖性にとって、下々の土俗的聖性を支えてきたシャーマン、すなわち陰陽寮に属する者たちが、邪魔になってくるんです。
つまり、権力的支配が貫徹可能な段階になると、従来の部族的段階の聖性を担ってきた者たちは、集権的支配を補完する道具として利用できる範囲で存在を許されていたものが、用済みになって、階層性の最も下に叩き落とされるわけです。かくしてピラミッド型階層の頂点に聖なるミカドが存在し、底辺に穢なる被差別民が存在し、他の階層は全てケ(俗なるもの)として両者にサンドイッチされる形になります。すなわち、非階層的な環節的社会における「聖穢」観念が、階層的社会における「貴賤」の身分観念と重ねられ、単なる時間・空間観念というよりも、人に貼り付けられるものとなります。どこでも同じことが起こっています」
そこに問題がある。古くからのとして有名なのが京都の清水坂と奈良坂だが、そのどちらも皇室が起源であるという出自をもつ。差別の問題は王権と強く絡み合っているのだ。であるならば、宮台本人の言う「経済的要因」だけでなく、西の方に差別が強くあるのは、東北に比べて王権が確立していた側面もその要因になっているのではないだろうか。
ところで、「野中(野中広務のこと)のような出身者を日本の総理にはできないわなあ」などと言い放った麻生太郎こそ日本の総理にふさわしくないと思うのだが。

藤野千夜「おしゃべり怪談」 講談社
女流作家かと思った。4編の短編小説集なんだけれど主人公はみな女性。すごいなあ。ぼくにとって女性は謎なのに。長島有なんかもそうだよなあ、すごいよなあ。もっとも謎は謎なりに、生のまま提出してる部分が味なのかもしれない。たとえば病気の金魚に対するぐずぐずした態度とか。
いずれにしても、ああ、そういう女性っているかもね、という日常の面白さと不思議なずれが満載。表題作はその点、ほかの3作と違って背景が非日常的で異色。店長が刺された雀荘で、包丁で脅され延々麻雀をさせられる4人の女性たち。この作品はそうした背景だけじゃなく怖かった。

早乙女貢「会津士魂」第4巻 新人物往来社
ちょっと辛くなってきた、第4巻。慶喜の大阪脱出。もうこれから会津にとっていいことなんかありゃしねえ(C忌野清志郎)。歴史ものの困るところはここなんだよなあ。おお、会津ここから奇跡のJ1残留かよ、みたいなドラマは訪れない。会津やアイヌといったぼくがシンパシーを感じる人々の歴史のなんとツライことか。