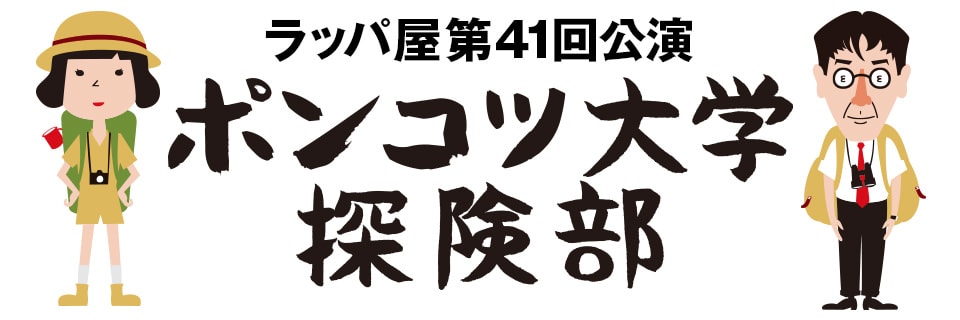川の汚染や自動車社会からの要請などさまざまな要因で、多くの川が蓋をされ見えない地下を流れている。川は死んでいないけれど、見えない。そんな見えない川を暗渠という。暗渠が好きだと言うと「そもそも暗渠とはなんだ」に始まって、「なにが面白いのかわからない」「今までそういう視点で眺めたことがなかった」などのほか、一部好事家は「わかるわかる」と反応してくれる。暗渠は一部の人間にとって胸揺すぶる存在なのだ。この感覚を著者の一人吉村生さんは「恋」と表現する。
「私はひょんなことから、その商店街のつなぎ目に昔、川が流れていたことを知る。「暗渠」との出逢いだった。この現象を他者に論理的に伝えることは難しい。おそらく、恋に落ちる感じと似ている」
暗渠に惹かれること、それはもう論理を越えた恋なのだ、と。なんといったって、吉村さんは暗渠と「出会い」ではなく「出逢い」を経験してしまったのだから。
しかし吉村さんは恋のドキドキだけで暗渠との関係を済まさない。
「どんな「ドブ」にもものがたりがあり、地形が記憶を紡ぎ出す。過去と現在、街の裏と表、昭和と自分、生と死などが交差する場所が暗渠だった」
ここに至って暗渠は単なる興味の対象ではなく、彼女の世界認識の根源の一つとなっている。さらに暗渠ガイドなどをしながら拡がっていったネットワークを通じて暗渠沿いの地元の人々との交流、聞き書きに及び、こうなるともう過去を整理し記述し後世に残す役割すら著者にお願いしたくなる。
共著者である高山英男さんはちょっとスタンスが異なる。吉村さんが「恋」と表現した感情を高山さんはなぜそういう恋心を抱くのだろうか、とメタ視点から分析する。この絶妙な二人の掛け合い。
「暗渠歩きを重ねるごとに、暗渠の魅力は「ネットワーク」「歴史」「景色」の三つに大別することが見えてきた」
われわれが普段思い浮かべる道路や鉄道網でのネットワークに加え、見えなくなってはいるが川が結んでいたネットワークもあるのではないか、と。かつて大きな街は水運が発達していたので、歴史的に見ればそのネットワークが大きな役割を果たしたことは想像に難くない。
そして歴史。川辺の歴史は日本史で学ぶような大きな歴史とは異なる生活の手触りのする歴史を私たちに伝えてくれる。東京には「暗渠に込められた東京のものがたり」があるが、同じように世界中の暗渠に、その街の人々の小さいけれども、大切な歴史が込められている。
そして「景色」に至ってその表現はより標準化、モデル化を指向し始める。暗渠に見られる景色、たとえば銭湯やクリーニング屋などを暗渠サインとして定義したり、暗渠に見られる加工度をレベル分けしたりしているが、しかし、白眉は景色を語る最後の「見立て」である。ここに至ってまったく違うアプローチをしていた共著者である吉村さんと同じく、言ってみればエラン・ヴィタールの瞬間。「恋」という言葉で暗渠に飛びついた感情を吐露した吉村さん、「見立て」という言葉で暗渠に飛び込んだ高山さん。
枯山水は水を抜くことによって水を意識させる日本独特の表現形式で、これは要するに最高の有は無によってしか表現できない、という逆説的な表現なのだけれど、まさに暗渠こそ現代の枯山水なのかもしれない。
図版豊富、写真豊富、過去の映画作品に現れた暗渠や日本だけでなく台湾の暗渠まで味わう二人のこの生き方を賭したような暗渠との付き合いが強く表れた本、地形や歴史、暗渠好きな人はもちろん、そうしたマニアックな人の情熱に触れたい人にもおすすめの好著。
「私はひょんなことから、その商店街のつなぎ目に昔、川が流れていたことを知る。「暗渠」との出逢いだった。この現象を他者に論理的に伝えることは難しい。おそらく、恋に落ちる感じと似ている」
暗渠に惹かれること、それはもう論理を越えた恋なのだ、と。なんといったって、吉村さんは暗渠と「出会い」ではなく「出逢い」を経験してしまったのだから。
しかし吉村さんは恋のドキドキだけで暗渠との関係を済まさない。
「どんな「ドブ」にもものがたりがあり、地形が記憶を紡ぎ出す。過去と現在、街の裏と表、昭和と自分、生と死などが交差する場所が暗渠だった」
ここに至って暗渠は単なる興味の対象ではなく、彼女の世界認識の根源の一つとなっている。さらに暗渠ガイドなどをしながら拡がっていったネットワークを通じて暗渠沿いの地元の人々との交流、聞き書きに及び、こうなるともう過去を整理し記述し後世に残す役割すら著者にお願いしたくなる。
共著者である高山英男さんはちょっとスタンスが異なる。吉村さんが「恋」と表現した感情を高山さんはなぜそういう恋心を抱くのだろうか、とメタ視点から分析する。この絶妙な二人の掛け合い。
「暗渠歩きを重ねるごとに、暗渠の魅力は「ネットワーク」「歴史」「景色」の三つに大別することが見えてきた」
われわれが普段思い浮かべる道路や鉄道網でのネットワークに加え、見えなくなってはいるが川が結んでいたネットワークもあるのではないか、と。かつて大きな街は水運が発達していたので、歴史的に見ればそのネットワークが大きな役割を果たしたことは想像に難くない。
そして歴史。川辺の歴史は日本史で学ぶような大きな歴史とは異なる生活の手触りのする歴史を私たちに伝えてくれる。東京には「暗渠に込められた東京のものがたり」があるが、同じように世界中の暗渠に、その街の人々の小さいけれども、大切な歴史が込められている。
そして「景色」に至ってその表現はより標準化、モデル化を指向し始める。暗渠に見られる景色、たとえば銭湯やクリーニング屋などを暗渠サインとして定義したり、暗渠に見られる加工度をレベル分けしたりしているが、しかし、白眉は景色を語る最後の「見立て」である。ここに至ってまったく違うアプローチをしていた共著者である吉村さんと同じく、言ってみればエラン・ヴィタールの瞬間。「恋」という言葉で暗渠に飛びついた感情を吐露した吉村さん、「見立て」という言葉で暗渠に飛び込んだ高山さん。
枯山水は水を抜くことによって水を意識させる日本独特の表現形式で、これは要するに最高の有は無によってしか表現できない、という逆説的な表現なのだけれど、まさに暗渠こそ現代の枯山水なのかもしれない。
図版豊富、写真豊富、過去の映画作品に現れた暗渠や日本だけでなく台湾の暗渠まで味わう二人のこの生き方を賭したような暗渠との付き合いが強く表れた本、地形や歴史、暗渠好きな人はもちろん、そうしたマニアックな人の情熱に触れたい人にもおすすめの好著。