円周率の3.14が日本では350年も前から使われてきたのだそうです。これは全く知りませんでした。てっきり明治あたりに西洋から教わったのだと思ってました。
そんな素晴らしい伝統を知っていれば、ゆとり教育で3とするなんてバカな発想も起きなかったのじゃないでしょうか。
やはり、正しい国家観も歴史観も無い東大卒の優等生の考えることなのでしょう。
世界に抜きん出ていた日本の和算をねずさんが詳しく教えてくれています。微分積分で脱落した私としては何とも恥ずかしい。
ねずさんのひとりごとより 2020/5/27
円周率と 日本人
・・・略
円周率の計算は、古代バビロニアの粘度板から、当時の人々(紀元前17~19世紀)が、3.125などを使っていたことが 明らかになっています。
いまやコンピューターを駆使して、なんと小数点以下10兆桁まで計算されるようになった円周率ですが、世界では円周率の計算 式を求めて、18世紀から19世紀にかけて大激論が交されていました。
ところが日本では、江戸初期となる17世紀、寛文3(1663)年には村松茂清が小数点以下7桁までの正しい値を求め、日常 的に使用する円周率を3.14と決めています。
つまり私たちが学校で習う3.14は、日本国内で350年もの長きにわたって使われてきたものです。・・・以下略
それにしても、我が先人は素晴らしい人達が多いですね。そんな優秀な人達も、今の文科省の薦める教育を受ければとんでもないことになりそうです。
やはり、国の基礎は教育から。政府・自民党は何時まで文科省を放置しておくのですか。










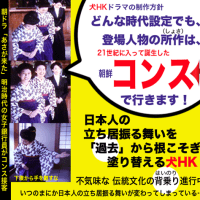
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます