さて、いよいよ、椴法華の地名の由来でございます。

古くは日本書紀のなかに、本州から蝦夷ゲ島に渡るのを「渡島(わたりしま)」と書いてあります。これも「ととう」と呼べます。
現在、北海道南部を、渡島半島と呼びますが「渡島(おしま)」も、「ととう」と読めるわけでございます。
さらに、鎌倉時代の吾妻鏡という史書には、幕府が罪人を、蝦夷ゲ島に島流しにしたとあります。
それらの人ばかりではなく、商人、漂流者、戦いに敗れた者など、大勢の人が渡って来たそうです。それらの一団も「渡り党」です。
「党」とは、武士又は集団を意味する言葉で、これもまた「渡党(ととう)」と読めます。
日持上人と、一緒に海峡を渡った、蛎崎一族も「渡党」と、いわれるものです。
この一族も、法華宗の渡り党なので「渡党法華」と呼ばれ、もしかして、磯伝いに、日持上人と一緒に、椴法華に、住みついたのかもしれません。
さらに、いまで言う、米国に渡ることを、渡米といいます。
唐の国に渡ったので「渡唐」です。
このように、あれやこれやと推測いたしますと、「渡島(わたりしま)」
「渡党(わたりとう)」そして、法華の上人が唐の国に渡った事などから「渡唐法華」と、なったのでございます。
後に、村には椴(とど)の木が多くあったので、その字を当てはめ「椴法華」と、なったものと思われます。
日本で初の海外布教をめざし、北海道開教の始祖といわれる、法華の高僧、日持上人。我が村から唐に渡ったというお話し、いかがだったでございましょうか。
村は桜の満開を迎えております。桜が散ると、恵山つつじが、村中に咲き始めます。
そんな今日この頃、遠い鎌倉時代に思いをはせれば、どこかしら椴法華という名前、ロマンチックで、愛すべき地名として、より身近に、感じられるのではないでしょうか。
椴法華村、その地名の由来、いかがだったでございましょうか。
村にある、先輩のお寺です。

※ これは昭和60年の村民文化祭で、講談調で、私が口演したものです。
笛の上手な友人が、横で盛り上げてくれました。
資料は、日蓮宗本山のものや、様々な文献を参考に、私がまとめたものです。
もう一つ別バージョンがあります。僧侶の旅装束を着て、法華の太鼓を持ち、「東西ナ、東西ナ、東西ナという人は、日蓮和尚のその弟子で、日持上人と申す者」で始まる、コミカルなものです。
これは、以前、北海道日蓮宗の大会が、函館で開催された時、高校の先輩で日蓮宗の僧侶に、ぜひ披露してくれと頼まれたので、数百人の僧侶の前でやったことがあります。
日持上人が日蓮大聖人の六高弟なので、会場にいたたくさんの僧侶が、私を拝んでいました。
本山の大僧正もいらしていましたが、その方から、お布施をいただきました。
嘘のような、本当の話です。
その時、私の先輩の僧侶は、司会役を仰せつかっていたのですが、緊張のあまり、楽屋でウイスキーをラッパ飲みしていました。
荒行に耐えて、物怖じしない先輩ですが、大僧正に前では、相当緊張したようです。
今考えれば、なんてことをしでかしたのかと思います。
若いというのは、狂気にも似た行動ができるということです。
お付き合いいただき、ありがとうございました。

古くは日本書紀のなかに、本州から蝦夷ゲ島に渡るのを「渡島(わたりしま)」と書いてあります。これも「ととう」と呼べます。
現在、北海道南部を、渡島半島と呼びますが「渡島(おしま)」も、「ととう」と読めるわけでございます。
さらに、鎌倉時代の吾妻鏡という史書には、幕府が罪人を、蝦夷ゲ島に島流しにしたとあります。
それらの人ばかりではなく、商人、漂流者、戦いに敗れた者など、大勢の人が渡って来たそうです。それらの一団も「渡り党」です。
「党」とは、武士又は集団を意味する言葉で、これもまた「渡党(ととう)」と読めます。
日持上人と、一緒に海峡を渡った、蛎崎一族も「渡党」と、いわれるものです。
この一族も、法華宗の渡り党なので「渡党法華」と呼ばれ、もしかして、磯伝いに、日持上人と一緒に、椴法華に、住みついたのかもしれません。
さらに、いまで言う、米国に渡ることを、渡米といいます。
唐の国に渡ったので「渡唐」です。
このように、あれやこれやと推測いたしますと、「渡島(わたりしま)」
「渡党(わたりとう)」そして、法華の上人が唐の国に渡った事などから「渡唐法華」と、なったのでございます。
後に、村には椴(とど)の木が多くあったので、その字を当てはめ「椴法華」と、なったものと思われます。
日本で初の海外布教をめざし、北海道開教の始祖といわれる、法華の高僧、日持上人。我が村から唐に渡ったというお話し、いかがだったでございましょうか。
村は桜の満開を迎えております。桜が散ると、恵山つつじが、村中に咲き始めます。
そんな今日この頃、遠い鎌倉時代に思いをはせれば、どこかしら椴法華という名前、ロマンチックで、愛すべき地名として、より身近に、感じられるのではないでしょうか。
椴法華村、その地名の由来、いかがだったでございましょうか。
村にある、先輩のお寺です。

※ これは昭和60年の村民文化祭で、講談調で、私が口演したものです。
笛の上手な友人が、横で盛り上げてくれました。
資料は、日蓮宗本山のものや、様々な文献を参考に、私がまとめたものです。
もう一つ別バージョンがあります。僧侶の旅装束を着て、法華の太鼓を持ち、「東西ナ、東西ナ、東西ナという人は、日蓮和尚のその弟子で、日持上人と申す者」で始まる、コミカルなものです。
これは、以前、北海道日蓮宗の大会が、函館で開催された時、高校の先輩で日蓮宗の僧侶に、ぜひ披露してくれと頼まれたので、数百人の僧侶の前でやったことがあります。
日持上人が日蓮大聖人の六高弟なので、会場にいたたくさんの僧侶が、私を拝んでいました。
本山の大僧正もいらしていましたが、その方から、お布施をいただきました。
嘘のような、本当の話です。
その時、私の先輩の僧侶は、司会役を仰せつかっていたのですが、緊張のあまり、楽屋でウイスキーをラッパ飲みしていました。
荒行に耐えて、物怖じしない先輩ですが、大僧正に前では、相当緊張したようです。
今考えれば、なんてことをしでかしたのかと思います。
若いというのは、狂気にも似た行動ができるということです。
お付き合いいただき、ありがとうございました。















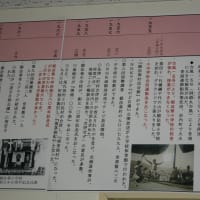




それにしても玄人はだしのご活躍、漁師にしておくのが・・・いや、止めておきます。御活躍の程を。合掌
渡島地方の宣伝の歌ですが、♪おしまなら来てよね 私さびしいの・・・なんて宴会で歌ったこともあります!