方言とは地域・風土に適応した言葉である。
その場の雰囲気を的確に言い表す時、標準語では充分ではなく、方言が最適だというものがある。
北海道の場合は、本州からの移住者が多いので、他所の土地の言葉がそのまま定着している。
方言を調べると、先祖がどこの土地から移住してきたかがわかる。
今朝の北海道新聞に、前松前副町長のMさんが、松前町の言葉の出自を調べたという記事が目に付いた。
「松前稼ぎ」という言葉がある。
昔、青森県下北半島からの出稼ぎが多かったので、下北地方の方言が松前には、圧倒的に多いという統計が出ていた。
松前はその昔、ニシン漁が盛んだったので出稼ぎ者が多かったのだろう。
それにしても、松前町の対岸の津軽半島からでなく下北半島からというのも不思議である。
下北は戊辰戦争後、会津藩が移住した。会津藩と松前藩の関係がその根底にあるのかなと思ったりもする。歴史を調べていると、一寸したつながりから思わぬ発見をすることがあり面白い。
※ズンブ デッケイ イガダナ(ずいぶん大きなイカですね)という意味。

それはさておき、私の目にとまったのは「だけだけに」という方言である。
私の村でも以前は頻繁に使われていたが、近年Kさんが亡くなってから、その言葉を聞くことがなくなったからだ。
Kさんは大正生まれの方で、村の多くの役職についていたので、特に印象深い方言であった。
「だけだけ」とは(相応に)という意味だ。松前の調査によると石川県だけで使われている言葉であるという。
石川県と松前といえば、北前船のつながりで、近江商人が活躍した歴史だ。
能登半島は門徒宗が多い。そのKさんも門徒宗だ。Kさんの先祖は石川県の出身ではないかと思う。今度ご家族から聞いてみようと思う。
ちなみに、Kさんの得意な台詞「だけだけに・そのかたちの中で」は、会合の場で、問題が起き始めた時によく使用していた。
「まあそのぐらいで、こんなかたちで収めたほうがいいのではないか」という意味である。
それで事態は収拾したものである。
Kさんは落としどころを心得ている人でもあった。今はその言葉を踏襲する人もいないし、その言葉が似合う人物もいなくなってしまった。
方言とは風土から生まれた言葉だ。
インフラ整備で地方が地方らしさを失い、それにつれ方言も徐々に少なくなってきた。
地方の時代とか地域主権とか叫ばれるが、そんなことも考えてみることも必要なことなのかなと思った、今日の記事である。
その場の雰囲気を的確に言い表す時、標準語では充分ではなく、方言が最適だというものがある。
北海道の場合は、本州からの移住者が多いので、他所の土地の言葉がそのまま定着している。
方言を調べると、先祖がどこの土地から移住してきたかがわかる。
今朝の北海道新聞に、前松前副町長のMさんが、松前町の言葉の出自を調べたという記事が目に付いた。
「松前稼ぎ」という言葉がある。
昔、青森県下北半島からの出稼ぎが多かったので、下北地方の方言が松前には、圧倒的に多いという統計が出ていた。
松前はその昔、ニシン漁が盛んだったので出稼ぎ者が多かったのだろう。
それにしても、松前町の対岸の津軽半島からでなく下北半島からというのも不思議である。
下北は戊辰戦争後、会津藩が移住した。会津藩と松前藩の関係がその根底にあるのかなと思ったりもする。歴史を調べていると、一寸したつながりから思わぬ発見をすることがあり面白い。
※ズンブ デッケイ イガダナ(ずいぶん大きなイカですね)という意味。

それはさておき、私の目にとまったのは「だけだけに」という方言である。
私の村でも以前は頻繁に使われていたが、近年Kさんが亡くなってから、その言葉を聞くことがなくなったからだ。
Kさんは大正生まれの方で、村の多くの役職についていたので、特に印象深い方言であった。
「だけだけ」とは(相応に)という意味だ。松前の調査によると石川県だけで使われている言葉であるという。
石川県と松前といえば、北前船のつながりで、近江商人が活躍した歴史だ。
能登半島は門徒宗が多い。そのKさんも門徒宗だ。Kさんの先祖は石川県の出身ではないかと思う。今度ご家族から聞いてみようと思う。
ちなみに、Kさんの得意な台詞「だけだけに・そのかたちの中で」は、会合の場で、問題が起き始めた時によく使用していた。
「まあそのぐらいで、こんなかたちで収めたほうがいいのではないか」という意味である。
それで事態は収拾したものである。
Kさんは落としどころを心得ている人でもあった。今はその言葉を踏襲する人もいないし、その言葉が似合う人物もいなくなってしまった。
方言とは風土から生まれた言葉だ。
インフラ整備で地方が地方らしさを失い、それにつれ方言も徐々に少なくなってきた。
地方の時代とか地域主権とか叫ばれるが、そんなことも考えてみることも必要なことなのかなと思った、今日の記事である。















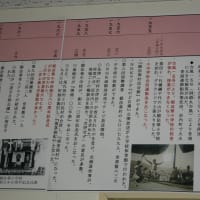




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます