▼今日のテーマは、今朝(30日)の道新、川柳欄に掲載された句だ。居酒屋ばかりではなく、家飲みまで制限されたら♪酒は涙だかため息か 心のうさの捨てどころ♪という歌を思い出した。
▼「コロナ禍でうさの捨て場もない日本」と、私も一句で嘆きたくもなる。コロナばかりではなく核のゴミの捨て場もない我が国は、閉塞感漂い「息詰まる日本」になっているようだ。
▼「国家安全法」が猛威をふるっている香港は、ため息もできないという現状のようだ。「香港」というかぐわしい名前が「死港」という名に代わり、異様な空気が漂っている気がする。
▼言論の自由の制限と飲酒制限は「心のうさ」の捨てどころさえなく、国民の健全な精神を蝕んでいるのだろう。
▼さて、この名曲の作曲は古賀政男だ。作詞は函館の新聞社に勤務していた高橋掬太郎だ。この日本歌謡界のゴールデン・コンビは、戦争の色がただよい始めてきた時代に「5・7・5」の短い調べに、日本人の心の内を表現した。
▼私の文章も憲法が定める「表現の自由」を盾に長くなりすぎる。長くなれば長くなるほど、心に響かなくなってきたようだ。
▼これはひとえに我が国の政治の劣化によるものだと思うのだが、人のせいにしてはならない
。また歌を思い出すが
▼♪誰のせいでもありゃしないみんなおいらが悪いんだ♪という歌が口につく、戦後生まれの私は、メロディーはもちろんだが、歌詞にも興味を持っている。「歌は世につれ世は歌につれ」という言葉が染みついているからだ。
▼今日は川柳に目覚め、川柳らしい短いブログにしてみた。と言いながらも、もうちょっぴり続く。高橋掬太郎が飲み歩いた「函館銀座」の近くに、私は新婚時代に住んでいた。
▼函館山のふもとに位置するその場所には、芸者さんたちがたくさんいて「函館銀座」と呼ばれていた。私が生まれた頃は、すでに函館駅周辺に繁華街は移動していた。
▼でも、その近くに私が生まれた昭和23年から営業しているという、6人ほどの座席しかない、カウンターだけの焼鳥屋があった。
▼仕事帰りに立ち寄ると、常連客が椅子を移動し、座らせてくれた。コップ酒3杯と、焼き鳥3本。漬物はサービースだった。千円札1枚で間に合った。
▼店を出て、津軽海峡から吹き上げる心地よい風に吹かれ、護国神社の坂を上り石川啄木が住んでいた近くを通り、函館公園内を通過し、新妻が待っているアパートへと、いい気分で歩いたものだ。
▼啄木の歌を口ずさんだと思うが、歩きながらその曲を歌ったことは、たぶんなかったと思う。楽しい新婚時代だったからだ。・・・お終い。















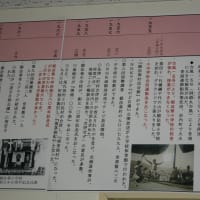




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます