▼世界中で猛威をふるっている新型コロナ。外出制限をしている世界の観光都市に、人気がない。ふと気が付けば、私が普段見慣れている光景だ?。人が歩いていないというのは、人口800人余りの我が過疎地域と、同じだということだ。生まれて初めての実感だ。
▼「アメージング」な「ダイバーシティー」!といわれる過密都市「トウキョウ」は、感染拡大が爆発的のようだ。春色の青さを増してきた太平洋。まもなく若緑色に変身するのを待っている、周囲の山々。海の青さに負けぬ、青空。空気もうまいし、水が美味しい我が故郷。
▼人々が暮らす、健康的で人間的な土地が、日本全土にたくさんある。そんな場所が過疎地と呼ばれているところだ。【過疎地=人間が住む最適な土地(広辞苑)】と「第7販」に、そう掲載してほしいものだ。「一極集中解消」・「地方創生」にも大きな変化が生まれるに違いない。
▼前置きはこの位にし、コロナウイルスで、町会の「カラオケ・サロン」も中止となっている。目的は「みんなで楽しく元気に、大きな声を出す」ということと、老人の「引きこもり防止」と「健康管理」などが目的だ。
▼まず歌う前に、歌に合わせた健康体操というプログラムがある。これから始める。みんな一生懸命に体を動かしている。カラオケに飽きると、再度、健康体操をしたりすることもある。
▼この体操は、様々な曲で構成されているが「青い山脈」は歌いながら体操ができ、体も動かしやすい。参加者は、戦前生まれの方も多い。子供の時には食糧難を経験してきた世代だ。この歌に【元気】を感じるのだろう。
▼昭和23年生まれの私の日常食も「いも・かぼちゃ」だった。そんな時代を思い出したくないという同級生もいるが、私は大好きだった。前浜はイカやイワシなどたくさんとれた。それを塩漬けにしたのが、食卓に添えられたからだ。
▼特にストーブの上に新聞紙を重ね、その上にイカの塩辛を焼く。不思議に新聞紙はやぶれることはなく、丸く縮んだイカの塩辛を、イモの上に乗せて食べるのが、とてもうまかったからだ。
▼数年前、七輪居酒屋で塩辛を頼んだ時、塩辛の量が多すぎたので「七輪で焼きたい」といったら、お姉さんが「年配の方に多いですね」と言って、ホタテの貝殻を出してくれた。
▼貝殻から海のエキスが出るなんてことを知っていたのかどうか知らないが、そんな気の利いたお姉さんがいる店は、長居をしてしまうのが私たち世代だ。
▼とにかく話しが脱線に次ぐ脱線を繰り返すのも、団塊世代の特徴だ。「青い山脈」に戻す。作詞・西城八十、作曲・服部一郎だ。歌は万年青年、藤山一郎と、美人の奈良光江だ。焦土と化した都会ににあの歌声が流れ「歌の力」のすごさを見せ付けたのは、想像に難くない。たぶん日本歌謡史上、最高傑作ではないかと考える。
▼さらに、作詞・サトウハチロウ、作曲・万城目正、歌・並木路子の【リンゴの唄】だ。この二つの曲は【国民栄誉賞】を与えてもいいのではないかと思っている。
▼当時、この曲がどんなに国民を勇気づけた、戦争の歴史を後から学んだ私たちでさえも、その歌のすばらしさは充分理解できる。戦争で病んだ日本人の心に、回復の風を吹き込んだのは間違いないだろう。半藤一利著「歴史と戦争」の中に、並木路子に関する次のような記述がある。
▼【浅草生まれの並木は、昭和13年に松竹歌劇団に入る。東京大空襲で、一緒に隅田川に飛び込んだ母は、遺体となって浮かんだ。父は南方で殉職死、次兄は千島列島で戦死。たたみかける戦争の傷みを抑えて、彼女は懸命に歌ったという。そんな悲しみがあったことも知らず、人々は明るい声に耳を傾けたが、よく聞くと、徹頭徹尾悲しい歌であると思えてくる。】
▼「リンゴの唄」は、戦後日本の最も一明るい歌だと思っていたが、実は、究極の悲しみが根底にあっての明るさだったと思えば「反戦歌」として、私のカラオケのレパートリーにしたいと思う。
▼コロナが終息してカラオケが再開されたら「リンゴの唄」の話を、みんなに教え「青い山脈」と「リンゴの唄」を合唱してみようと思う。そう言えば昨年、小説「青い山脈」の初版本を読んだ。
▼本の中からかび臭い匂いが漂ってきたが、女学生たちの戦後民主主義へのあこがれと、新しい社会への挑戦は、まさしく題名の「青い山脈」そのものに感じられたことを思い出している。
▼「コロナ戦争」の騒動に乗じ「憲法改正」へのきな臭さも漂い始めているいる中、ちょっと一休みし「リンゴの唄」に潜む反戦の思いに浸って見た次第です。















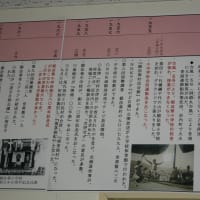




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます