▼道徳=(人のふみ行うべき道)。ある社会で、その成員の社会に対する、あるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として、一般に承認されている規範の総体。と「広辞苑」に書いてある。
▼何度か読み返すと、その本質が漠然ではあるがつかめてくる。人それぞれの価値観は多様だ。多様だから漠然としたままでいいのではない。より鮮明にしようという努力が必要だ。というのが、得意の妄想を捨てて、たまには真剣に考えてみる、私の道徳に対する見解だ。
※【辺野古基地埋め立てに関する県民投票について】
▼沖縄戦から現在に至るまで、米国の占領下にある沖縄だ。私が県民なら「反対」だ。「どちらでもない」などという選択を付け加えたのは、共同体に対し自己責任を回避する「卑怯な選択」を用意したと感じるからだ。
▼もっと言えば「反対」という、国策に反対することに躊躇している県民に「逃げ道を作る」そんなやり方だ。戦争のための新たな米軍基地建設だ。「どちらでもない」というのは、戦争してもいいという方に加担する選択なのだ。
「どちらでもない」に選択する人は「道徳」が希薄な人間ではないかと思う。
※【おとうさんにぼう力を受けています。先生どうにかできませんか】
▼そんな小4の女児の訴えを、父親からの脅迫に屈し、メモを渡した教育委員会の対応は、善悪の判断もつかない道徳が全く欠如した学校関係者が存在するという衝撃に、呆れかえってっしまう。というより、子供を死に追いやるのが教育現場だという事実だ。
▼平成18年度から小学校で「道徳教育」の教科化が始まった。しかし、教育関係者の近年の善悪の判断の劣化は、驚くべき件数に達する。そんな中、アベ政権には「教育勅語」容認論がある。
▼戦前の道徳は、戦争の遂行に大きな力を発揮した。道徳とは,国家に強制されるものではないというのを、戦前が証明している。それは国民一人一人が判断し、その基準の総体をつくり上げることが必要だと言っているのではないだろうか。つまり「道徳」というものは、民主主義の在り方を問うているのだ。
※【ある作家の講演会に出かけた、足が不自由なご婦人の話】
▼サイン会があるというので、作家の本を持って出かけた。講演は感動的なものだった。だが、二階でのサイン会だ。階段を登れず諦めていたら「私がサインをいただいてきましょうか」といい、係りの女性が列に並んで、しばらくしてサインの入った本を渡してくれた。その女性「いま私は先生と握手をしてきましたので私と握手をしましょう」と、そのご婦人の手を握ったという。・・・北海道新聞(2日)「朝の食卓」より。
▼沖縄県民投票の「どちらでもいい」。千葉県の教育委員会の対応。旭川市での「握手」。この3事案に「道徳」というものの在り方が、私たち国民に投げかけられているような気がする。
▼「道徳心」というものは「あったかい気持ち」を言うのであって「冷たく悲しい気持ちになる」というのは、道徳からほど遠い存在なのではないか。「心に愛がなければどんな言葉も相手には届かない」という言葉を改めてかみしめてみた。
▼普段道徳心が揺らいでるといわれる私だが、ちょっぴり道徳について考えてみた、寒さが肌身に染みる2月2日だ。















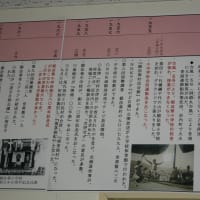




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます