17日のコロナ感染数、愛知県では48人(延26572人)の感染と1人(累563人)の死亡が確認され、全国ではあわせて1535人(延451984人)の感染と36人(累8738人)の死亡がレポートされている。
政府は、所得の少ない子育て世帯に対し、子ども1人あたり5万円の給付金を新たに支給することを決定。そのほか、孤独や孤立する弱者の援助活動をするNPO法人への支援の強化など、およそ60億円の予算措置を講じるとしている。弱者支援を大胆に実行中のバイデン大統領との首脳会談を前にして、首相もちょっと気張ってみせようという魂胆ではないか。
名古屋地方気象台は17日午後「名古屋市でサクラが開花した」と発表した。開花は平年より9日、去年より5日早く、昭和28年以来最も早い開花だという。この調子でゆけば、満開は1週間から10日後になるらしい。
地域のコロナ対策として、岡崎市は、市内の寺院を避難所として活用することを考え、市の仏教会と協定を結んだという。葬式仏教といわれて久しく、仏様は現世ご利益は下さらないのだろうと思っていたから、このニュースはちょっと意外だった。
南海トラフ地震が起きれば、岡崎市の避難者は3万4千人を超えると想定されているが、コロナ感染防止の三密対策をした避難所を運営しようとすると、体育館にして約50施設が不足するという計算になるのだという。今回の寺院協定はこれに対処する方策のひとつとして市役所が考えたもの。
寺院施設を災害避難所として使うことには、これまでに市仏教会加盟寺院の3分の1にあたる約九十寺が賛同しているという。今後も働きかけによって協力寺の数をふやしていくと仏教会は存外に乗り気の姿勢である。浸水地域や建物の耐震性をクリアした寺々が加入すれば、市の避難所スペースが一気に増加する。結構なことだ。
「檀家と布施」というカタチで寺と信者の内向きなつながりはあっても、「汝の隣人を愛せ」というキリスト教のように「貧者に対する慈善」への社会的アプロ-チがまったく弱い日本の仏教界だが、今回の地方行政に対する協力姿勢というのはいったいどんな背景があってのことだろうか。
大地震が起きた時、協力寺の僧侶たちはどんな行動をとるのだろう。今後は会議検討を重ねて、細かい方法論をまとめていくのだろうが、行政への「空間貸し」だけで終わるのならば、衆生の心の救済を謂う仏教教義とは違ったことになりはしないか。
布施は困窮する被災者にこそ与えられるべきだ。この避難所協定をきっかけにして、いつもは閉じている寺の山門が「生きている」人たちに向かって開くことになればと思う。











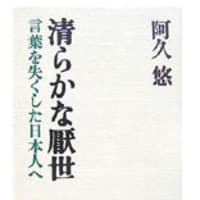






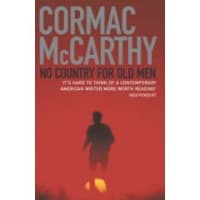
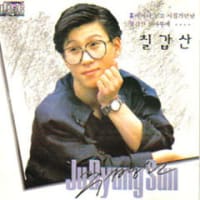
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます