小鯵を開いて骨を外したフィレを甘酢につけた一皿が昼食に出た。
半身5センチほどの小ささだが、なんとも旨い。綺麗におろしてあるのは魚屋の腕前である。家人が電話で今日のオススメを尋ね、意向にあえばそれを買う。今日はそれが小鯵だったというわけである。
坪内稔典の「季語集」、夏の動物のくくりでこの「小鯵」が出ている。まず、谷崎潤一郎の小説「猫と庄造と二人のをんな」の一節を引く。
「阪神電車の沿線にある町々、西宮、芦屋、魚崎、住吉あたりでは、地元の浜で獲れる鯵や鰯を、『鯵のとれとれ』『鰯のとれとれ』と呼びながら大概毎日売りに来る。」
庄造は小鯵を素焼きにして二杯酢につけたものを好んでいる。鯵にしみた酢を吸い、骨を噛み砕き、それを可愛がっている猫のリリーに与える。その様子を見た妻は、猫を前妻に譲るか、自分を離縁するのか、どちらかを選べと迫る。スッパスッパと鯵の酢を吸いながら、庄造の態度は煮え切らない。
小鯵や猫というささいなものへの拘りは、人という存在のせつなさをユーモラスに伝えてくる、と坪内は書いて、小鯵は江戸時代初期からある古い季語だとして、以下の二句を載せている。
「小鯵売 虹にそむきて 行きにけり」 五十崎古郷
「夕鯵を 分かちこころを 近くせり」 能村登四郎
「猫と庄造と二人のをんな」が書かれたのは戦前の1936年のこと。浜で獲れたばかりの小魚を売り歩いたのは戦後の50年代あたりまでだったろう。今の飼い猫は、主人が舐めた小魚の骨などには見向きもするまい。
すべてが小奇麗になった分、値段もばかにはならない。小皿に載せられた鯵の酢づけ(10枚くらいあったか)を、じっくりゆっくり味わいながら食べた。
今日は七夕。名古屋地方は一日中雨が降り続き、牽牛も織女も年一回の逢瀬を楽しむことが出来なかったようである。
半身5センチほどの小ささだが、なんとも旨い。綺麗におろしてあるのは魚屋の腕前である。家人が電話で今日のオススメを尋ね、意向にあえばそれを買う。今日はそれが小鯵だったというわけである。
坪内稔典の「季語集」、夏の動物のくくりでこの「小鯵」が出ている。まず、谷崎潤一郎の小説「猫と庄造と二人のをんな」の一節を引く。
「阪神電車の沿線にある町々、西宮、芦屋、魚崎、住吉あたりでは、地元の浜で獲れる鯵や鰯を、『鯵のとれとれ』『鰯のとれとれ』と呼びながら大概毎日売りに来る。」
庄造は小鯵を素焼きにして二杯酢につけたものを好んでいる。鯵にしみた酢を吸い、骨を噛み砕き、それを可愛がっている猫のリリーに与える。その様子を見た妻は、猫を前妻に譲るか、自分を離縁するのか、どちらかを選べと迫る。スッパスッパと鯵の酢を吸いながら、庄造の態度は煮え切らない。
小鯵や猫というささいなものへの拘りは、人という存在のせつなさをユーモラスに伝えてくる、と坪内は書いて、小鯵は江戸時代初期からある古い季語だとして、以下の二句を載せている。
「小鯵売 虹にそむきて 行きにけり」 五十崎古郷
「夕鯵を 分かちこころを 近くせり」 能村登四郎
「猫と庄造と二人のをんな」が書かれたのは戦前の1936年のこと。浜で獲れたばかりの小魚を売り歩いたのは戦後の50年代あたりまでだったろう。今の飼い猫は、主人が舐めた小魚の骨などには見向きもするまい。
すべてが小奇麗になった分、値段もばかにはならない。小皿に載せられた鯵の酢づけ(10枚くらいあったか)を、じっくりゆっくり味わいながら食べた。
今日は七夕。名古屋地方は一日中雨が降り続き、牽牛も織女も年一回の逢瀬を楽しむことが出来なかったようである。


















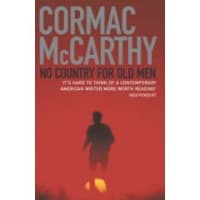

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます