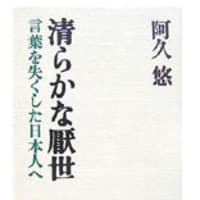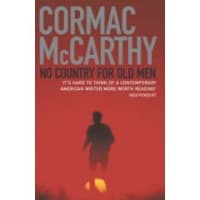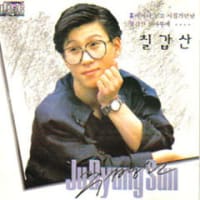三寒四温というのは冬のはなしのはずだか、4月中旬を過ぎても寒かったり暖かかったりが繰り返す。やはり天候不順の春だ。昨日は二十四節気で云う「穀雨」。穀雨とは穀物の成長を助ける雨のことだというが、タイミングをあわせて降った雨はあたたかい春の雨とは云いかねた。
今日は打って変わってぽかぽかの陽気。電車の窓外を走る景色は気づかぬ間にすべてが薄緑色に衣替えを済ませ、陽の光がまぶしく反射する。上着を着ていたのでは軽く汗をかきそうだ。気温の上下が続くせいかわが体調はAOKとはいえない。胃の調子はイマイチだし、小便が出にくい。眼はごろごろし、くしゃみや鼻水がでるのは花粉アレルギーの始まりだろうか。名古屋の最高気温は23.6度まで上がった。
それでも夕方になると気温が少し下がって身体がシャンとしてくる。万歩のコースでとった裏道の住宅路には玄関先に大小のプランターがずらりと並んで、とりどりの草花が咲き競っている。如雨露をもったおばさんが水やりの最中である。合間にはプランターの位置を変えたり、雑草をもいだり、育てた花たちを愛でながら夕食前のひとときをゆったりと楽しんでいる。
似たような水やりシーンは、ここ一箇所だけでなく方々で見られた。早めに帰宅したオヤジさんの仕事になっている家もある。それにしても、これだけ軒並みにプランターやポットが並ぶということは、「ガーデニング」を趣味とするシニア組が結構多いということなのだろう。
我が家にも庭はあるがプランターは並んでおらずフェンス代わりに植えた細木が数本植わっているだけ。世話の大変な「ガーデニング」は敬遠したい気持ち、血液型O型のものぐさな性格なのだ。
文芸春秋のベスト・エッセイ集に、園芸家の柳宗民が「水やり三年」と題して、ガーデニングの話題を取り上げている。
「植物を育てている時、まず何をおいても毎日欠かせないのが水やりだと思っている人が大変多い」と柳は云う。裏道のおじさん・おばさんも多分その類だろう。人間も植物も代謝で失われた水分をなんらかの方法で補給しているが、水の飲みすぎが人間の体によくないのと同様に、植物も水が必要だからといって、やたらにやるだけでは必ず具合がわるくなるというのだ。
水が必要なのはやり手の人間ではなくて植物の方で、その成長期には大量の水が必要だし、成長の止まる秋冬にはそれほどの水分は不必要だ。時々の天候によっても土の乾き方が変わってくる。だから人間の心が満たされるからといって、毎日安易に水だけやっていればいいというわけではない。水やりは園芸作業のなかでも微妙に難しいことだから「水やり三年」というのだそうだ。
緑や花を嫌いだという人は先ずいないだろうから、ガーデニングが盛んになるのは結構なハナシだが、これだけ全国通津浦裏、誰もが庭弄りを始めることになると、膨大な水道使用が環境問題化し始めていると柳は指摘する。
そういえば最近、お屋敷から億ションに住み替えたNさんも「毎日面倒な庭の水やりをしなくてよくなったのがイチバン嬉しい」という言い分だった。
鉢植えはたしかに乾きやすいから水やりが肝心だが、庭植えの植物にも連日かかさず水をやるのは、大変な無駄使い。自然の雨露に任せた方が却って丈夫に育つ。野山に育つ植物を見れば自明のはずだと柳は指摘する。
庭の草木への水やりをやめれば、全国の水道使用量は画然と減少するとはナルホドである。明日はまた雨模様という予報だから、おばんさんやおじさんも今日は水やりの必要はなかったというわけだ。
完全舗装で自動車の通過OKの裏道ばかりが延々続く。ここでは、雨が降っても汚水溝にすべて流れて、雨水は土にしみこまず。挙句、街はいつも乾いて、人は植物への水遣りの無駄を永遠に繰り返す。
水や植物のライフサイクルにも自動車万能社会がマイナスの効果を与えている。自動車道路=都市文明とする20世紀的な思考法はそろそろやめにしたがよかろう。
今日は打って変わってぽかぽかの陽気。電車の窓外を走る景色は気づかぬ間にすべてが薄緑色に衣替えを済ませ、陽の光がまぶしく反射する。上着を着ていたのでは軽く汗をかきそうだ。気温の上下が続くせいかわが体調はAOKとはいえない。胃の調子はイマイチだし、小便が出にくい。眼はごろごろし、くしゃみや鼻水がでるのは花粉アレルギーの始まりだろうか。名古屋の最高気温は23.6度まで上がった。
それでも夕方になると気温が少し下がって身体がシャンとしてくる。万歩のコースでとった裏道の住宅路には玄関先に大小のプランターがずらりと並んで、とりどりの草花が咲き競っている。如雨露をもったおばさんが水やりの最中である。合間にはプランターの位置を変えたり、雑草をもいだり、育てた花たちを愛でながら夕食前のひとときをゆったりと楽しんでいる。
似たような水やりシーンは、ここ一箇所だけでなく方々で見られた。早めに帰宅したオヤジさんの仕事になっている家もある。それにしても、これだけ軒並みにプランターやポットが並ぶということは、「ガーデニング」を趣味とするシニア組が結構多いということなのだろう。
我が家にも庭はあるがプランターは並んでおらずフェンス代わりに植えた細木が数本植わっているだけ。世話の大変な「ガーデニング」は敬遠したい気持ち、血液型O型のものぐさな性格なのだ。
文芸春秋のベスト・エッセイ集に、園芸家の柳宗民が「水やり三年」と題して、ガーデニングの話題を取り上げている。
「植物を育てている時、まず何をおいても毎日欠かせないのが水やりだと思っている人が大変多い」と柳は云う。裏道のおじさん・おばさんも多分その類だろう。人間も植物も代謝で失われた水分をなんらかの方法で補給しているが、水の飲みすぎが人間の体によくないのと同様に、植物も水が必要だからといって、やたらにやるだけでは必ず具合がわるくなるというのだ。
水が必要なのはやり手の人間ではなくて植物の方で、その成長期には大量の水が必要だし、成長の止まる秋冬にはそれほどの水分は不必要だ。時々の天候によっても土の乾き方が変わってくる。だから人間の心が満たされるからといって、毎日安易に水だけやっていればいいというわけではない。水やりは園芸作業のなかでも微妙に難しいことだから「水やり三年」というのだそうだ。
緑や花を嫌いだという人は先ずいないだろうから、ガーデニングが盛んになるのは結構なハナシだが、これだけ全国通津浦裏、誰もが庭弄りを始めることになると、膨大な水道使用が環境問題化し始めていると柳は指摘する。
そういえば最近、お屋敷から億ションに住み替えたNさんも「毎日面倒な庭の水やりをしなくてよくなったのがイチバン嬉しい」という言い分だった。
鉢植えはたしかに乾きやすいから水やりが肝心だが、庭植えの植物にも連日かかさず水をやるのは、大変な無駄使い。自然の雨露に任せた方が却って丈夫に育つ。野山に育つ植物を見れば自明のはずだと柳は指摘する。
庭の草木への水やりをやめれば、全国の水道使用量は画然と減少するとはナルホドである。明日はまた雨模様という予報だから、おばんさんやおじさんも今日は水やりの必要はなかったというわけだ。
完全舗装で自動車の通過OKの裏道ばかりが延々続く。ここでは、雨が降っても汚水溝にすべて流れて、雨水は土にしみこまず。挙句、街はいつも乾いて、人は植物への水遣りの無駄を永遠に繰り返す。
水や植物のライフサイクルにも自動車万能社会がマイナスの効果を与えている。自動車道路=都市文明とする20世紀的な思考法はそろそろやめにしたがよかろう。