竹本義太夫勧進特別公演終了後、引き続きファン感謝祭として「天地会『義経千本桜三段目すしやの段』」が催されました。天地会というのは三業(大夫・三味線・人形)の方たちがそれぞれ本来とは違う役どころを勤められるイベントのことです。
いやーぁ、めちゃくちゃ面白かったです。劇場は爆笑に継ぐ爆笑、大盛り上がりの1時間30分でした。いつもの公演と同じように出語り床に三味線・大夫をお勤めになる方が出てこられます。皆さん、ちゃんと裃をつけて、大夫さんは床本を捧げ持って祈念されますが、その時点で何だか可笑しいんです。客席からクスクスと笑いがもれます。三味線は勘十郎さんと呂勢大夫さんです。時間が押していたのか、早速呂勢大夫さんが演奏を始められます。どうも勘十郎さん、出でとちらはったのか、なかなか調子が上がらず、見ているほうがハラハラドキドキ。そのうち、中へ引っ込んでしまわれ、結局、最後まで呂勢大夫さんお一人で三味線を勤められました。呂勢大夫さんのお三味線、とてもお上手でびっくりしました。彼がいなかったら、「すしやの段」が最後までいけたかどうか、怪しいものです。
大夫は、いがみの権太を三味線の清介さん→人形の玉女さん→人形の勘十郎さんの順で勤められました。義太夫は三味線の人も人形の人も毎日聞いて、それぞれ三味線を弾き、人形を遣ったはるわけで、であれば、きっと覚えているような気がするんですが、そうではありません。途中で何回もつっかえるし、玉女さんなんかは「えーっと」という間投詞が入るし、お客さんのほうも何回もガクッとなりながら聞いておりました。勘十郎さん、こちらは結構調子よく語ったはって、「大したもんやねぇ~」と感心した矢先にとちらはって、一番の聞かせどころでお客さんは泣くには泣きましたが、悲しい涙ではなく笑いすぎての涙を流しておりました。
話が飛びますが、住大夫さんの「文楽のこころを語る」という本で、住大夫さんが「義太夫は大阪弁やから、普段から大阪弁しゃべらんとあきまへん」とおっしゃっていたんですが、勘十郎さんの義太夫って本当に大阪弁で、「義太夫が大阪弁ってほんまやねぇ」と今さらながらミョーに納得しながら聞かせていただきました。
人形はファン感謝祭ということで、全員が顔を出して遣います。でも、3人とも顔が見えると、舞台上がすごく煩雑というか、ごちゃごちゃします。ご本人たちは超真面目に遣ったはるんですが、その真面目さが可笑しい。笑えます。いつも何気に見ていますが、当たり前のことながら、三人の息がピッタリ合わない全然出来が違いますね。右遣いと足遣いの黒子姿も、無意識のうちにちゃんと「無いもの」としてこちらは認識しているようです。人形の手を動かす操作も指先が見えるか見えないかのギリギリのところで行われているし。舞台の敷居(っていうんでしょうか、前方と後方を行き来するところ)はいつもなら自動ドアみたいに開いたり閉まったりしていますが、これも三人のイキが合っているからで、段取りが悪いとそこでまた渋滞が起こっていました。
本当にとても楽しい会で、幕が下りても、お客さんの拍手が鳴り止まず、ご出演の方々がもう一度劇場に入ってこられ、ご挨拶してくださいました。今回、天地会を見て思ったのは、皆さん決して文楽の素人さんではなく、それなりというかかなりキャリアをお持ちの方たちばかりで、すぐに出来そうに思うんですが出来ないって、やっぱり「伝統芸能」って一朝一夕でこなせるものではないんですよね。いったん途切れてしまうと、修復はまず不可能、絶滅してしまいます。某市長もそうですが、国や自治体も考えていただきたいですね。
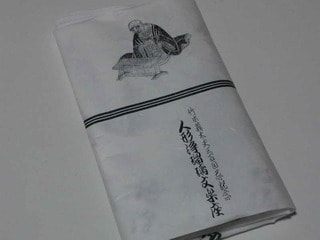

ロビーで売られていたサイン入り手ぬぐいです。もちろん、協力させていただきました。簑助さん のサインも見えます。
のサインも見えます。

いやーぁ、めちゃくちゃ面白かったです。劇場は爆笑に継ぐ爆笑、大盛り上がりの1時間30分でした。いつもの公演と同じように出語り床に三味線・大夫をお勤めになる方が出てこられます。皆さん、ちゃんと裃をつけて、大夫さんは床本を捧げ持って祈念されますが、その時点で何だか可笑しいんです。客席からクスクスと笑いがもれます。三味線は勘十郎さんと呂勢大夫さんです。時間が押していたのか、早速呂勢大夫さんが演奏を始められます。どうも勘十郎さん、出でとちらはったのか、なかなか調子が上がらず、見ているほうがハラハラドキドキ。そのうち、中へ引っ込んでしまわれ、結局、最後まで呂勢大夫さんお一人で三味線を勤められました。呂勢大夫さんのお三味線、とてもお上手でびっくりしました。彼がいなかったら、「すしやの段」が最後までいけたかどうか、怪しいものです。
大夫は、いがみの権太を三味線の清介さん→人形の玉女さん→人形の勘十郎さんの順で勤められました。義太夫は三味線の人も人形の人も毎日聞いて、それぞれ三味線を弾き、人形を遣ったはるわけで、であれば、きっと覚えているような気がするんですが、そうではありません。途中で何回もつっかえるし、玉女さんなんかは「えーっと」という間投詞が入るし、お客さんのほうも何回もガクッとなりながら聞いておりました。勘十郎さん、こちらは結構調子よく語ったはって、「大したもんやねぇ~」と感心した矢先にとちらはって、一番の聞かせどころでお客さんは泣くには泣きましたが、悲しい涙ではなく笑いすぎての涙を流しておりました。
話が飛びますが、住大夫さんの「文楽のこころを語る」という本で、住大夫さんが「義太夫は大阪弁やから、普段から大阪弁しゃべらんとあきまへん」とおっしゃっていたんですが、勘十郎さんの義太夫って本当に大阪弁で、「義太夫が大阪弁ってほんまやねぇ」と今さらながらミョーに納得しながら聞かせていただきました。
人形はファン感謝祭ということで、全員が顔を出して遣います。でも、3人とも顔が見えると、舞台上がすごく煩雑というか、ごちゃごちゃします。ご本人たちは超真面目に遣ったはるんですが、その真面目さが可笑しい。笑えます。いつも何気に見ていますが、当たり前のことながら、三人の息がピッタリ合わない全然出来が違いますね。右遣いと足遣いの黒子姿も、無意識のうちにちゃんと「無いもの」としてこちらは認識しているようです。人形の手を動かす操作も指先が見えるか見えないかのギリギリのところで行われているし。舞台の敷居(っていうんでしょうか、前方と後方を行き来するところ)はいつもなら自動ドアみたいに開いたり閉まったりしていますが、これも三人のイキが合っているからで、段取りが悪いとそこでまた渋滞が起こっていました。
本当にとても楽しい会で、幕が下りても、お客さんの拍手が鳴り止まず、ご出演の方々がもう一度劇場に入ってこられ、ご挨拶してくださいました。今回、天地会を見て思ったのは、皆さん決して文楽の素人さんではなく、それなりというかかなりキャリアをお持ちの方たちばかりで、すぐに出来そうに思うんですが出来ないって、やっぱり「伝統芸能」って一朝一夕でこなせるものではないんですよね。いったん途切れてしまうと、修復はまず不可能、絶滅してしまいます。某市長もそうですが、国や自治体も考えていただきたいですね。
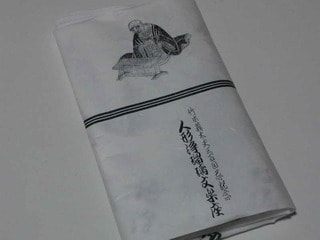

ロビーで売られていたサイン入り手ぬぐいです。もちろん、協力させていただきました。簑助さん
 のサインも見えます。
のサインも見えます。














