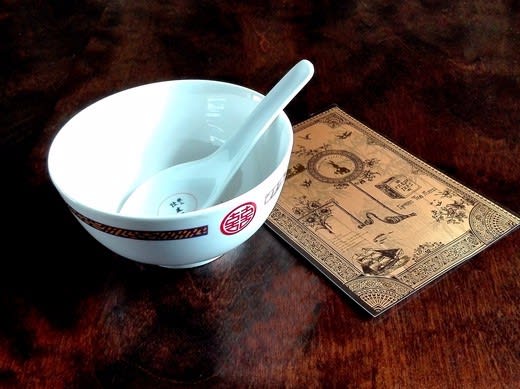きょうは夕焼けがきれいだった。
よく乾燥した秋の、薄い紙のような雲に誰かが火を点けたように、空はしずかに燃えていた。
急に空が広くなり、遠くの声が聞こえてきそうだった。
お~い、鎌をとげよ~と叫ぶ、おじいさんの声が聞こえてきそうだった。
夕焼けした翌日はかならず晴れるので、農家では稲刈りをすることになるのだった。
祖父は百姓だった。
重たい木の引き戸を開けて薄暗い家の中に入ると、そのまま台所も風呂場も土間つづきになっていた。
風呂場の手前で野良着を着替えて農具をしまう。その一角には足踏みの石臼が埋まっていて、夕方になると祖母が玄米を搗いていた。土壁に片手をあてて体を支えながら、片足で太い杵棒を踏みつづける。土壁の上の方には、鎌や鍬がなん本も並んで架かっていた。
祖父に聞いた話だが、祖父のおじいさんは刀で薪を割っていたという。どんな生活をしていた人なのだか、想像もつかない。
シンザエモン(新左衛門?)という名前だったので、シンザさんと呼ばれていたようで、その呼称が屋号のようにして残り、ぼくの父が子どもの頃でもまだ、村ではシンザさんとこのシゲちゃんという風に呼ばれていたという。
そのシンザさんとこのシゲちゃんは、家の障子やふすまに落書きをするのが好きな悪ガキだった。
祖父がいくら叱りつけても止めようとはしない。よくみると、子どものくせになかなか上手に画いているので、しまいには、祖父も叱れなくなったという。
悪ガキのぼくの父は次男坊だったので、学校もろくろく行かずに船場に丁稚に出されてしまった。そこで、商人としての父の人生が決まったのだった。
子どもの頃に、いちどだけ父が絵を画いたのをみたことがある。
画用紙のまん中に大きな赤いかたまりがあった。それは何なのかと聞くと、父は石だと言った。そんな赤い石があるのかと聞くと、夕焼けのせいで石が燃えているのだ、と父は言った。
九州の田舎を行商したときに見た、どこかの道端の風景だったのだ。
父が絵を画いたのを見たのは、それがいちどだけだった。金儲けに日々追われる商人に、絵を画いたりする余裕はなかったのだ。
小学生の時から、ぼくはソロバン学校に通わされ、夜は店を閉めたあとに、父の帳簿付けの計算をさせられた。
振り返ってみれば、ぼくが父の商売を手伝ったのはそれだけだ。高校を卒業すると、ぼくはすぐに家を飛び出した。人あしらいのうまい父の才覚がぼくにはなかったし、父もそれを知っていたのだと思う。
父はひとりで商売を続け、80歳で店を閉めた。そして6年後に死んだ。
父は生前、ぼんやり店の前に立って空を眺めていることがあった。釣りが好きだったから空模様を心配していたのかもしれない。あるいは、仕入れのためのカネの工面など考えていたのだろうか。
ひとは毎日、ほとんど空の存在など忘れて生活している。誰にもふり向かれなかった空の、夕焼けは一日の終わりのしずかな叫びなのかもしれない。
百姓の祖父も死に、商人の父も死んで、シンザさんとこの夕焼けだけが残った。
お~い、鎌をとげよ~、と誰かが叫んでいる夕焼けだ。
だがもう、シンザさんとこに百姓はいない。いまでは、鎌をとぐ者もいなくなった。