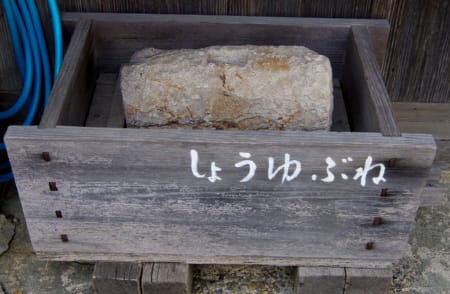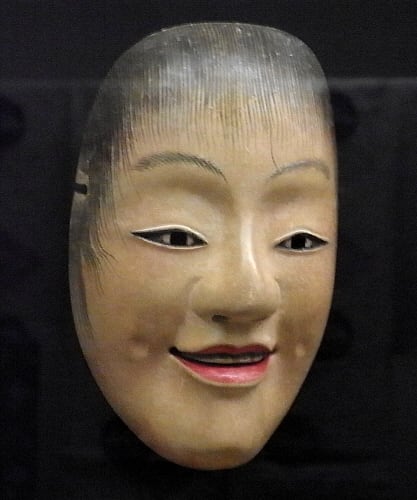今回急に勝浦へ向かったのは、西さんのヒジキを買いに行こうと思ったから。
実に久しぶりの勝浦行きで道中、車窓からの光景も新鮮に感じた。
9年前、那智駅にある那智交流センターで買ったヒジキがとてもおいしくて、この生産者である西さん宅へ直接買いに行ったものだった。
残念ながら西さんはもうヒジキは採っておられなくて、ご近所の方が採られたものを分けていただいた。

当時は那智交流センターの1階に直売所があったのだが、今は同じ敷地内に別棟で農産物や海産物などが直売されている。
地元民にも人気があり、当日は10:00の開店前から行列ができていて、ちょっと驚いた。
豊富な農産物に加えて、マグロの刺身などの海産物、かんきつ類の絞り汁を酢代わりに使ったばら寿司などが並んでいた。

那智の滝へ向かうが、2011年9月に襲った台風12号のすさまじい傷跡が未だに生々しく、アチコチで復旧作業が行われていた。
那智川沿いの被害は甚大だったようで、あの怪しげな秘湯「那智天然温泉」は跡形もなく、かろうじてここにあったと分かる土地が残っているだけだった。

35年ぶりに那智の滝を見に。

杉の大木がそそり立ち、コケもびっしり。


紅い欄干は滝が近くで見られる「御滝拝所」で、拝観料金300円が必要。
上がってみた。
滝の水しぶきがかかり、有難いマイナスイオンもたっぷりと。
しかし、料金を支払わなくても「滝見台」から見るので充分だ。

一人では座っていられないだろうが、二人なら。
こうすれば料金を支払った値打ちはあるだろう。

もう一つ買って帰りたいものがあった。

新宮の香梅堂。
創業が明治元年。

通販では買えるがこの店舗以外では買えない「鈴焼き」。
野菜カステラとかベビーカステラという名前で売られているあれ。
卵黄たっぷりという感じでさすがにおいしい。