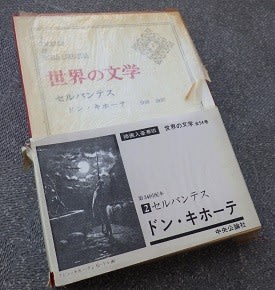初めてシベリウスの「フィンランディア」を聴いたのは中学時代だったろうか。
力強い旋律と華麗で厳粛な旋律が交錯するすばらしい曲だった。
レコードの解説を読むと、
帝政ロシアに対する国民の抵抗が主題だという意味のことが書いてあったように思う。
そういえば、この曲には劇的と思わせる要素が確かにある。
その国、フィンランドがこれまでの中立政策を転換して、
スウェーデンとともにNATOに加盟申請した。
「ウクライナ侵攻ですべてが変わり、
ロシアを隣にして平和な未来を信じることはできない」(マリン首相)

伝統的にロシアを刺激しない政策をとってきたフィンランドを
プーチン自身がNATOの側に追いやった形だ。
ある評者によれば「これはプーチンのオウンゴールだ」と。
「なるほど」と思わず笑みをうかべてしまう。
帝政ロシアからソビエト政権時代を経て、
今に至るまで慎重にふるまってきたフィンランドの人々。
その彼らがこうべを上げて新たな選択をしたことに惜しみない拍手を贈りたい。
初演から100年以上の時を経て、「フィンランディア」が再び鳴り響くかのようだ。
力強い旋律と華麗で厳粛な旋律が交錯するすばらしい曲だった。
レコードの解説を読むと、
帝政ロシアに対する国民の抵抗が主題だという意味のことが書いてあったように思う。
そういえば、この曲には劇的と思わせる要素が確かにある。
その国、フィンランドがこれまでの中立政策を転換して、
スウェーデンとともにNATOに加盟申請した。
「ウクライナ侵攻ですべてが変わり、
ロシアを隣にして平和な未来を信じることはできない」(マリン首相)

伝統的にロシアを刺激しない政策をとってきたフィンランドを
プーチン自身がNATOの側に追いやった形だ。
ある評者によれば「これはプーチンのオウンゴールだ」と。
「なるほど」と思わず笑みをうかべてしまう。
帝政ロシアからソビエト政権時代を経て、
今に至るまで慎重にふるまってきたフィンランドの人々。
その彼らがこうべを上げて新たな選択をしたことに惜しみない拍手を贈りたい。
初演から100年以上の時を経て、「フィンランディア」が再び鳴り響くかのようだ。