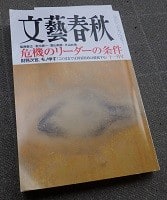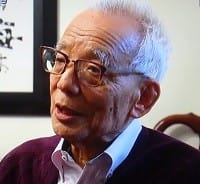有島武郎の「生まれ出ずる悩み」(1918年)を読む。
絵を志す若い木本と「私」(有島)との関わりの物語だ。
木本は北海道の岩内という漁師町の貧しい漁師家庭の次男。
卒業後は北海道の厳しい気候の下、過酷な肉体労働の毎日。
好きなスケッチは、漁に出られない荒天のときだけというゆとりのなさ。
しかも絵具さえ手元にないという環境だ。
町で彼のスケッチを見てくれるのは、文学に魅かれつつも
気難しい父親から調剤所を継ぐように半ば強いられた「K」のみ。
「K」だけは木本のスケッチに感心し、「画かきになれと勧めてくれる」。
しかし木本からすれば「K」に絵を見る力があるとは思えない。
木本はそんな漁師町で
「異邦人」のような自分を見出してはますます悩みをつのらせる。
木本はある荒天の夜、スケッチの帰りに崖の上に立ち、
思わず死を選ぼうとするが思いとどまる。
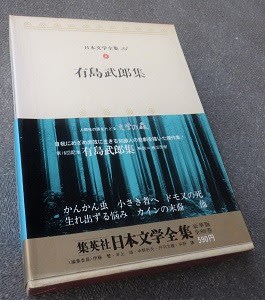
木本の物語はここで終わり、短い終章で有島が書く。
「君が一人の漁夫として一生を過ごすのがいいのか、一人の芸術家として終身働くのがいいのか、
僕は知らない。・・・それは神から直接君に示されなければならない。
僕はその時が君の上に一刻も早く来るのを祈るばかりだ。
・・・同時に、この地球の上のそこここに君と同じ疑いと悩みをとを持って
苦しんでいる人々の上に最上の道が開けよかしと祈るものだ・・・。」等々。
絵画、音楽などの芸術、あるいは学問、
さらに運動競技なども含め、夢に向かって進む人々の存在。
今も昔も変わりはすまい。
この書はそういう人々への声援のように見える一方、
最後に決めるのはその人にしか・・・という冷厳な事実をも指摘しているようにぼくには読める。
かつて夢をもっていたが結局ここでいう「漁夫」に伍して生きたぼくにはとても感慨深い。
本書を読んで思い当たるという人もおられよう。
おすすめの一冊だ。
* なお、引用文中の「神」は比喩であって、
宗教的な意味でないことをお断りしておく(参考)。
絵を志す若い木本と「私」(有島)との関わりの物語だ。
木本は北海道の岩内という漁師町の貧しい漁師家庭の次男。
卒業後は北海道の厳しい気候の下、過酷な肉体労働の毎日。
好きなスケッチは、漁に出られない荒天のときだけというゆとりのなさ。
しかも絵具さえ手元にないという環境だ。
町で彼のスケッチを見てくれるのは、文学に魅かれつつも
気難しい父親から調剤所を継ぐように半ば強いられた「K」のみ。
「K」だけは木本のスケッチに感心し、「画かきになれと勧めてくれる」。
しかし木本からすれば「K」に絵を見る力があるとは思えない。
木本はそんな漁師町で
「異邦人」のような自分を見出してはますます悩みをつのらせる。
木本はある荒天の夜、スケッチの帰りに崖の上に立ち、
思わず死を選ぼうとするが思いとどまる。
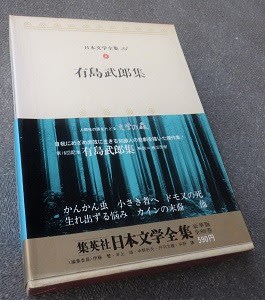
木本の物語はここで終わり、短い終章で有島が書く。
「君が一人の漁夫として一生を過ごすのがいいのか、一人の芸術家として終身働くのがいいのか、
僕は知らない。・・・それは神から直接君に示されなければならない。
僕はその時が君の上に一刻も早く来るのを祈るばかりだ。
・・・同時に、この地球の上のそこここに君と同じ疑いと悩みをとを持って
苦しんでいる人々の上に最上の道が開けよかしと祈るものだ・・・。」等々。
絵画、音楽などの芸術、あるいは学問、
さらに運動競技なども含め、夢に向かって進む人々の存在。
今も昔も変わりはすまい。
この書はそういう人々への声援のように見える一方、
最後に決めるのはその人にしか・・・という冷厳な事実をも指摘しているようにぼくには読める。
かつて夢をもっていたが結局ここでいう「漁夫」に伍して生きたぼくにはとても感慨深い。
本書を読んで思い当たるという人もおられよう。
おすすめの一冊だ。
* なお、引用文中の「神」は比喩であって、
宗教的な意味でないことをお断りしておく(参考)。