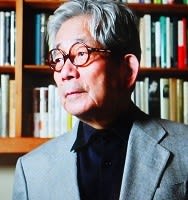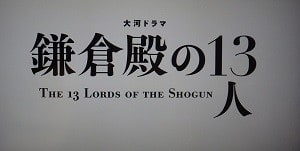右手小指の骨折から4週間が過ぎた。
医師はレントゲン写真を見ながら
「だいたいひっついたな、もう固定は要らん。
けど、関節が固まっとる。
釣りに行くのは指が動かせるようになってからやな」と。
確かに。
右手小指は伸びたままで、少ししか曲がらない。

曲げようとすると猛烈に痛いのだ。
リールを巻くのに差支えはないが、
転倒でなくともよろめいたときなど、周囲の岩や木に手をつくのはとても不安。
もうしばらくガマンの日々。
それはともかく、手や顔を両手で洗えるなど、やっと日常が少しずつもどってきたのが救い。
医師はレントゲン写真を見ながら
「だいたいひっついたな、もう固定は要らん。
けど、関節が固まっとる。
釣りに行くのは指が動かせるようになってからやな」と。
確かに。
右手小指は伸びたままで、少ししか曲がらない。

曲げようとすると猛烈に痛いのだ。
リールを巻くのに差支えはないが、
転倒でなくともよろめいたときなど、周囲の岩や木に手をつくのはとても不安。
もうしばらくガマンの日々。
それはともかく、手や顔を両手で洗えるなど、やっと日常が少しずつもどってきたのが救い。