Eテレで「消えた故郷へ帰るとき 高知・椿山50年の記録」があった。
とても心にしみいる記録作品(NHK高知)だった。
椿山(つばやま)という集落
高知県仁淀川町、標高700メートルの山間にある集落。

急峻な斜面に家々があり、古くから焼き畑農業や林業を生業としてきた。
平家の落人によって開かれたとも言われ、800年の歴史があるという。
が、人口は1965年あたりを最盛期に減り始め、2019年には最後の住人が山を去り消滅。
中内健一さんという人
2021年、中内健一さんが高知市からこの椿山に単身で移り住んだ。
健一さんはこの集落で生まれ育ったが、高知の高校を卒業後、椿山には戻らず、
高知市内で働くようになり、そこに家を構えて家族と暮らしてきた人だ。
その健一さんが早期退職して戻ってきたのだ。

健一さんは両親とのことを語る。
「両親は(椿山に)帰って来いとは言わなかったが、
帰って来てもらいたいという気持ちはじゅうじゅうわかっていた」と。
81歳で亡くなった健一さんの母は生前、
「(息子が)高校を卒業して就職したから、それが一番の幸せ」、
また「子どもを大きくしたけん、上等」と語っていたともいう。
両親の苦しいほどに揺れ動く胸の内が伝わってくる。
健一さんの新たな日々
さて、誰も住まなくなった椿山では、家々が朽ち始め、草木に飲み込まれそうになっていた。

健一さんは、故郷に移り住んでから、草刈り、
そして父の植えた杉の間伐や手入れ、また20年後に実るというゆずの苗木を植える。
「一気につぶして消滅集落にするのは申し訳ない」と語る。
健一さんのあとに続く者は誰もいない、それはよくわかっておられるようだ。
それでも「動けなくなるまで椿山にいるつもりだ」と。
各地の消滅集落、それぞれの思い
集落の消滅は決してめずらしいものではなかろう。
ぼくも郷里の古座川水系の奥深くに釣りに行ったとき、
すでに消滅した集落の跡、また消滅の日が遠くない集落をいくつかこの目にした。
共通するのは林業の衰退だ。
時代の波というものは実に容赦ないものだ。
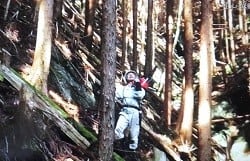
健一さんが汗だくになって格闘する姿を見て、ぼくは思わず「健一さん、
どんなにがんばっても消滅は避けられないのでは?」と言いたくなってしまう。
が、健一さんの心にあるのはそんなことではなさそうだ。
両親はじめ、先祖が子や孫のために代々大切に守ってきた畑や山林という贈り物への感謝、
そしてある種の贖罪意識なのかなと感じる次第だ。
健一さんのご健康を心から祈りたい。
とても心にしみいる記録作品(NHK高知)だった。
椿山(つばやま)という集落
高知県仁淀川町、標高700メートルの山間にある集落。

急峻な斜面に家々があり、古くから焼き畑農業や林業を生業としてきた。
平家の落人によって開かれたとも言われ、800年の歴史があるという。
が、人口は1965年あたりを最盛期に減り始め、2019年には最後の住人が山を去り消滅。
中内健一さんという人
2021年、中内健一さんが高知市からこの椿山に単身で移り住んだ。
健一さんはこの集落で生まれ育ったが、高知の高校を卒業後、椿山には戻らず、
高知市内で働くようになり、そこに家を構えて家族と暮らしてきた人だ。
その健一さんが早期退職して戻ってきたのだ。

健一さんは両親とのことを語る。
「両親は(椿山に)帰って来いとは言わなかったが、
帰って来てもらいたいという気持ちはじゅうじゅうわかっていた」と。
81歳で亡くなった健一さんの母は生前、
「(息子が)高校を卒業して就職したから、それが一番の幸せ」、
また「子どもを大きくしたけん、上等」と語っていたともいう。
両親の苦しいほどに揺れ動く胸の内が伝わってくる。
健一さんの新たな日々
さて、誰も住まなくなった椿山では、家々が朽ち始め、草木に飲み込まれそうになっていた。

健一さんは、故郷に移り住んでから、草刈り、
そして父の植えた杉の間伐や手入れ、また20年後に実るというゆずの苗木を植える。
「一気につぶして消滅集落にするのは申し訳ない」と語る。
健一さんのあとに続く者は誰もいない、それはよくわかっておられるようだ。
それでも「動けなくなるまで椿山にいるつもりだ」と。
各地の消滅集落、それぞれの思い
集落の消滅は決してめずらしいものではなかろう。
ぼくも郷里の古座川水系の奥深くに釣りに行ったとき、
すでに消滅した集落の跡、また消滅の日が遠くない集落をいくつかこの目にした。
共通するのは林業の衰退だ。
時代の波というものは実に容赦ないものだ。
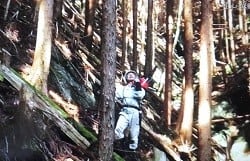
健一さんが汗だくになって格闘する姿を見て、ぼくは思わず「健一さん、
どんなにがんばっても消滅は避けられないのでは?」と言いたくなってしまう。
が、健一さんの心にあるのはそんなことではなさそうだ。
両親はじめ、先祖が子や孫のために代々大切に守ってきた畑や山林という贈り物への感謝、
そしてある種の贖罪意識なのかなと感じる次第だ。
健一さんのご健康を心から祈りたい。























