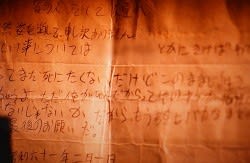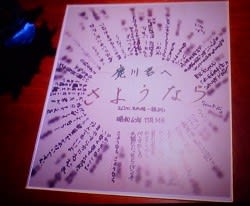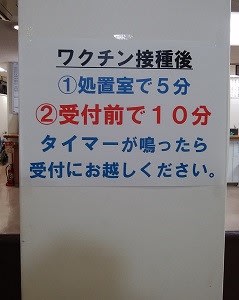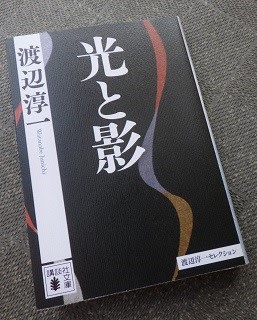「品薄」とのことで心配したが、予定通り二回目の接種を終えた。
なぜか一回目と違い、針を刺すときは痛かった。
それでも発熱など、案じた副反応もなく一安心。
英国などには届かないが、日本でも接種率が上がってきた。
ここにきて感染者や入院者の年齢が低くなってきているのは、
やはりワクチン効果なのだろう。
「宣言」発令の効果も薄く、結局これしかないということか。
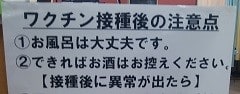
( 院内の注意書き )
ところで最近ワクチンに関するデマが話題になる。
接種すると「遺伝情報の書き換え」、「不妊」、「コロナへの感染」、
はては「接種箇所が磁石のようにひっつく」とかいう意味のわからないものまで・・・。
医療関係者らによって、これらの情報は否定されているが、
そう簡単に納得は得られないのか、なかなか根強いようだ。
ある意味では一笑に付されるべきこれらのデマ。
しかし、多くの人がそれを真実と信じ込み、そう行動して、ひとつのうねりにでもなれば、
世の中はとんでもない方向にねじ曲がるのでは?とおそろしくなってしまう。
人がデマから無縁になれるのは永遠にないのかも知れない。
なぜか一回目と違い、針を刺すときは痛かった。
それでも発熱など、案じた副反応もなく一安心。
英国などには届かないが、日本でも接種率が上がってきた。
ここにきて感染者や入院者の年齢が低くなってきているのは、
やはりワクチン効果なのだろう。
「宣言」発令の効果も薄く、結局これしかないということか。
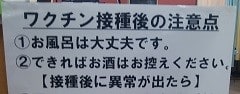
( 院内の注意書き )
ところで最近ワクチンに関するデマが話題になる。
接種すると「遺伝情報の書き換え」、「不妊」、「コロナへの感染」、
はては「接種箇所が磁石のようにひっつく」とかいう意味のわからないものまで・・・。
医療関係者らによって、これらの情報は否定されているが、
そう簡単に納得は得られないのか、なかなか根強いようだ。
ある意味では一笑に付されるべきこれらのデマ。
しかし、多くの人がそれを真実と信じ込み、そう行動して、ひとつのうねりにでもなれば、
世の中はとんでもない方向にねじ曲がるのでは?とおそろしくなってしまう。
人がデマから無縁になれるのは永遠にないのかも知れない。