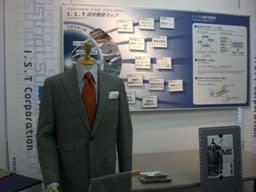今日は、中区曽我井にある㈱酒井精工を訪問させていただきました。国道427号線を通る際、会社の建物を見て何を製造されている会社なのかと興味を持っていました。八馬専務と藤本部長がお忙しい中、対応していただきました。㈱酒井精工は、昭和14年尼崎市で、酒井鉄工所の精密機械工具製造部門として操業され、昭和20年に現在の中区曽我井に戦時疎開をされています。本社は大阪市にあり、名古屋営業所と製造部門の工場が中区曽我井にあります。
㈱酒井精工は、創業当初から雌ネジ(ナット)加工工具であるタップの研究開発と製造販売を一筋に行われています。私も、こんなにも様々な種類のタップ見せていただいて驚きました。主に、自動車業界から受注を受け、生産を行っています。新しい製品の開発が出来るように、技術部に力を入れ、業界からの様々な要望に応えられるようにされているとのことでした。他社が参入できない自社ブランドとして、特殊な物を生産することにより、安定的に経営を行われているようです。事実、タップについては、様々な特許をとられています。そして、タップ技術の延長として、手術用の医療器具の開発も行うようになっています。
工場内も見学させていただいたのですが、一つ一つの製品を大切に扱っている社員の方の姿を見せていただきました。根気強く正確に仕事をしてくれる人を社員として迎えたいと言われていた専務の言葉が、よく分かりました。偶然、黒田庄中学校のバレー部の教え子に出会いました。彼は、身長は低かったけれど、レシーバーとして真面目に練習に取り組み、レギュラーの座を勝ち取りました。身長の高い下級生にも、自分の練習態度で指導をしてくれていました。そんな彼が、良い会社で働いていることに嬉しくなりました。
部品を研磨する特殊な機械は高額ですが、数多く設置されています。ただし、日本製よりヨーロッパ製の方が良いとのことでした。現在、様々な原材料費が高騰し生産費用がかかっていますが、製品に付加させられないこと、むしろ受注会社からは値下げを迫られることもあり、経営上大変だとの話も聞きました。
今回の㈱酒井精工訪問で、あらためて日本の技術の素晴らしさを感じさせていただきました。そして、その技術を支えているのは、やはり人であることも再認識をしました。そのため、根気強く仕事ができ、自分で考えることのできる人材の育成が大切だと感じました。
㈱酒井精工は、創業当初から雌ネジ(ナット)加工工具であるタップの研究開発と製造販売を一筋に行われています。私も、こんなにも様々な種類のタップ見せていただいて驚きました。主に、自動車業界から受注を受け、生産を行っています。新しい製品の開発が出来るように、技術部に力を入れ、業界からの様々な要望に応えられるようにされているとのことでした。他社が参入できない自社ブランドとして、特殊な物を生産することにより、安定的に経営を行われているようです。事実、タップについては、様々な特許をとられています。そして、タップ技術の延長として、手術用の医療器具の開発も行うようになっています。
工場内も見学させていただいたのですが、一つ一つの製品を大切に扱っている社員の方の姿を見せていただきました。根気強く正確に仕事をしてくれる人を社員として迎えたいと言われていた専務の言葉が、よく分かりました。偶然、黒田庄中学校のバレー部の教え子に出会いました。彼は、身長は低かったけれど、レシーバーとして真面目に練習に取り組み、レギュラーの座を勝ち取りました。身長の高い下級生にも、自分の練習態度で指導をしてくれていました。そんな彼が、良い会社で働いていることに嬉しくなりました。
部品を研磨する特殊な機械は高額ですが、数多く設置されています。ただし、日本製よりヨーロッパ製の方が良いとのことでした。現在、様々な原材料費が高騰し生産費用がかかっていますが、製品に付加させられないこと、むしろ受注会社からは値下げを迫られることもあり、経営上大変だとの話も聞きました。
今回の㈱酒井精工訪問で、あらためて日本の技術の素晴らしさを感じさせていただきました。そして、その技術を支えているのは、やはり人であることも再認識をしました。そのため、根気強く仕事ができ、自分で考えることのできる人材の育成が大切だと感じました。