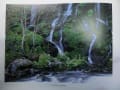12月31日と1月1日、中国福建省福州はかなり寒い。中国は1月1日だけが祝祭日となる。この二日間、日本では大晦日と元日となり、故郷に行ったり家族や親戚で集まったりして過ごす人も多いだろう。私は、中国のアパートで一人ポツンと二日間を過ごした。淋しさ(寂しさ)がつのる日でもある。Eメールでの「新年」のやりとりはあるが、音声での会話というものがない二日間でもあった。
「"寒いね"と 話しかければ "寒いね"と 答える人の いる あたたかさ」—これは『サラダ記念日』という短歌集にある俵万智の短歌。こんな短歌の世界が欲しい二日間。やはり、異国でポツリと過ごす年末・年始は、日本での一人暮らしの侘しさや寂しさとはまた違った「孤立・孤独」をより強く感じたりもする暮らし。中国14億人の人の海の中で、「大海に浮かぶ小舟」のような心細さも、やはりあるが、このような一人暮らしの「孤立・孤独」に慣れたといえば慣れたのだろうか‥‥。いや、「淋しさ・寂しさ」をやり過ごして日々生きることに、がまんと諦めにも似たものがあるといったほうがより正確なのかもしれない。
自由律詩の尾崎放哉と種田山頭火の句が心にしみてくる。「咳をしても 一人」という放哉の一句が心に沁みる。
「こんな よい月を 一人で見ている」「障子を開けておく 海も暮れ切る」「障子しめきって 淋しさを みたす」「雀のあたたかさ 握る はなしてやる」
「つくづく淋しい 我が影よ 動かしてみる」「淋しい からだから 爪がのび出す」「考え事をしてゐる 田にしが 歩いて居る」
尾崎放哉は なんとか生き続けてきたが、1926年、41才で没した。
北海道の富良野に行った時に買った一冊の「写真と山頭火の句」でつくられた『富良野で山頭火』。富良野在住の写真家が、自分の撮影した富良野の写真に山頭火の句を綴ったものだ。写真の下に一句書かれている。
「まっすぐな道でさみしい」「夕焼雲のうつくしければ 人の恋しき」「分け入っても分け入っても 青い山」「雪ふる一人 一人ゆく」
「かなかな ないて ひとりである」「ふりかえらない 道をいそぐ」「生きられるだけは生きよう 草萌ゆる」
「月が昇って 何を待つでもなく」「やっぱり一人はさみしい 枯草」「うしろすがたの しぐれていくか」
「こころおちつけば 水の音」「山暮れて 山の音を聴く」「へうへうとして 水を味ふ」「どうしようもない わたしが歩いている」
2年ほど前に、四国の松山にいった時、山頭火の終焉の地「一草庵」に行った。庵跡を管理している「松山山頭火会」の人から、山頭火の似顔絵に様々な山頭火の句を書いた短冊(全て手作り)を たくさんたくさん(50枚ほど)いただいた。中国に持ち帰り、大学の「日本近現代文学」の授業で学生達にそれを 一人に一枚ずつ好きな短冊をあげた。山頭火や放哉の自由律詩(句)や啄木の句について話をした。
「濁れる水の 流れつつ澄む」「さて どちらへ行こう」「ふくれた餅の あたたかさを味わう」「うどん供へて、母よ 私もいただきまする」「この旅 果もない旅の つくつくぼうし」
種田山頭火は、1940年、58才で没した。
石川啄木の短歌—「何となく 汽車に乗りたく 思いしのみ 汽車を下りしに ゆくところなし」「病のごと 思郷のこころ 湧く日なり 目に青空の 煙かなしも」「ふるさとの 山に向かひて 言うことなし ふるさとの山は ありがたきかな」「こころよき 疲れなるかな 息もつかず 仕事をしたる後の この疲れ」「ふるさとの 訛りなつかし 停車場に ふるさとのそを 聞きに行く」く」
日本には、放哉、山頭火、啄木がいた。そして、中国には杜甫がいた。大晦日と元日、この4人の句や漢詩を 毎年 手元で開いてみているような気がする6年間の、異国・中国での一人暮らし。