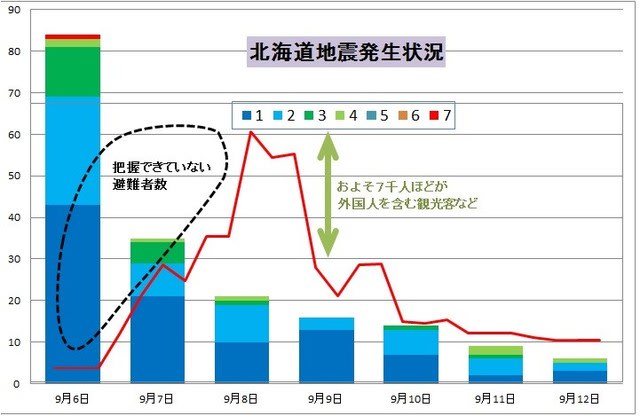さて、連日行くぞ(笑)
ガチンコだ。
世の中とは違った角度で眺めているので参考にするべし。
【図1】と【図2】は同じデータから作図していて、【図1】は単純な積上げ、【図2】は100%表示にしているだけのものだ。が、ここからわかることもある。

一般に、人口減少社会!キビシーぜ!みたいに思われるのは、【図1】の赤矢印のとおり、総人口が減少に転じたあたりから「おぉ!もしかしてダイジョブか?」みたいな報道のされかたをしているが、我々(ってダレ?)は、生産年齢人口がピークを迎えたあたり【図1】の黄矢印あたりから警鐘を鳴らしている。
で、ダ。
労働力人口は、昨日、見てもらったとおりなんだけど、1997年6月の68百万人超でいったんピークを迎えて減少に転じる。
そのあたりから一気に完全失業者が増加し、完全失業率が高くなっていく(黒の折れ線グラフね)。自殺対策の現場では常識化しているが、この時期に自殺者が年間2万人台から3万人台へと突入していく。ちなみにDV被害も急増しているノダ。なにがあったのか、世相を思い出してみよう!
2004年あたりから3百万人いた完全失業者がじょじょに減少傾向をたどるものの、2008年のリーマンショックを受けて、再び上昇に転じる。2014年あたりから沈静化し、2013年のアヘノホニャラカが功を奏したのかどうかは不明だが、完全失業率は、現在まで低下の一途をたどっている。
というのが一般的なトレンド。
ただ、【図2】を見てもらうと、わかると思うが、1960年代からすでに人口全体に占める労働力人口の割合は減少し始めているノダ。
それが何を意味するのかということは、置いておいても、そういうトレンドは今から60年も前から始まっているということなノダ。
うーむ、自治体も国家も右肩上がりの幻想に浸かり切って、ぬるま湯でふやけてノボセテ経営破たんの危機に陥っている原因がよくわかる。
マジでダイジョブか!?
で、これを踏まえて、日本の産業全体のトレンドを見てみよう。【図3】ダ。

ぬぅーーー、日本って、こんな国だっけ?
第3次産業主流の国家になってる。はい。もちろんわかってますとも。しかし、第1次産業、キビシーですね。食料自給率とか耕作放棄地とか農地中間管理機構とか、いろいろ言ってますが、ホントにダイジョブなんでしょうか?
ということで、いったん、農業に焦点を当てる。
農業の従事者数って、いろいろな捉え方があるわけだけど、ここでは農業センサスの基幹的農業従事者を見ていく。国勢調査での農業従事者とも大きくかい離はないので、兼業しながらも農業している人の数を補足するには、まぁまぁ適した項目だと思う。
基幹的農業従事者の説明は【図4】。

農業センサスから拝借しています。
あまり大昔まで遡ると悲しくなるばかりなので、ここ20年ほどの推移をみてみよう。平成2年からの基幹的農業従事者の水位が【図5】。
減ってるなーって感じで、黄矢印のようになだらかに減少していくのではないかと思われるが、自分の予測では【図6】くらいに急激に減少すると予想。

なんでかっていうと、もちろん根拠はあって、【図7】のとおりなわけだ。新規就農者は増えずに、そのまま高齢化が進んで行っている様子が手に取るようにわかる。
【図8】は平成2年と平成27年のトレンドを見たものだが、おおむねそのままスライドしていることが手に取るようにわかるだろう(15年スパンなので、年齢層は合致しないが、傾向はわかるだろう)。
こうした傾向から導き出したのが【図6】で、あと20年もすれば、基幹的農業従事者は1/3ほど、50万人を切ってしまうのではないかと危ぶまれる。
農業分野においてもIOT化は進んできているが、危機的状況に瀕していることは否めないだろう。

農業はあくまで一例にすぎず、次回はいよいよ外国人労働力の現状について、眺めてみたい。
っつーか、こういうことは、政府は当然、知ってるんだよね。当たり前だよね。政府統計だし、施策に生かすために「統計調査してます!」って、書いてあるし。マジで。無駄に統計調査してないよな。
施策の立案のために、外国人の多く住んでいる自治体や町内、企業など、なんとなく関係者にヒアリングしてみて、「こんなもんかなー」とかって思ってないよね。印象で語ってないよね。「対応方針案」とか出しているけど、みっちり統計データも見てるよね。
だって、関係者の人って、マクロ的な視点に立ってないでしょ?当たり前だけど。
政治家のことは知らんが、行政マンなら震えるほど仕事シロー!ってなことだ。
ガチンコだ。
世の中とは違った角度で眺めているので参考にするべし。
【図1】と【図2】は同じデータから作図していて、【図1】は単純な積上げ、【図2】は100%表示にしているだけのものだ。が、ここからわかることもある。

一般に、人口減少社会!キビシーぜ!みたいに思われるのは、【図1】の赤矢印のとおり、総人口が減少に転じたあたりから「おぉ!もしかしてダイジョブか?」みたいな報道のされかたをしているが、我々(ってダレ?)は、生産年齢人口がピークを迎えたあたり【図1】の黄矢印あたりから警鐘を鳴らしている。
で、ダ。
労働力人口は、昨日、見てもらったとおりなんだけど、1997年6月の68百万人超でいったんピークを迎えて減少に転じる。
そのあたりから一気に完全失業者が増加し、完全失業率が高くなっていく(黒の折れ線グラフね)。自殺対策の現場では常識化しているが、この時期に自殺者が年間2万人台から3万人台へと突入していく。ちなみにDV被害も急増しているノダ。なにがあったのか、世相を思い出してみよう!
2004年あたりから3百万人いた完全失業者がじょじょに減少傾向をたどるものの、2008年のリーマンショックを受けて、再び上昇に転じる。2014年あたりから沈静化し、2013年のアヘノホニャラカが功を奏したのかどうかは不明だが、完全失業率は、現在まで低下の一途をたどっている。
というのが一般的なトレンド。
ただ、【図2】を見てもらうと、わかると思うが、1960年代からすでに人口全体に占める労働力人口の割合は減少し始めているノダ。
それが何を意味するのかということは、置いておいても、そういうトレンドは今から60年も前から始まっているということなノダ。
うーむ、自治体も国家も右肩上がりの幻想に浸かり切って、ぬるま湯でふやけてノボセテ経営破たんの危機に陥っている原因がよくわかる。
マジでダイジョブか!?
で、これを踏まえて、日本の産業全体のトレンドを見てみよう。【図3】ダ。

ぬぅーーー、日本って、こんな国だっけ?
第3次産業主流の国家になってる。はい。もちろんわかってますとも。しかし、第1次産業、キビシーですね。食料自給率とか耕作放棄地とか農地中間管理機構とか、いろいろ言ってますが、ホントにダイジョブなんでしょうか?
ということで、いったん、農業に焦点を当てる。
農業の従事者数って、いろいろな捉え方があるわけだけど、ここでは農業センサスの基幹的農業従事者を見ていく。国勢調査での農業従事者とも大きくかい離はないので、兼業しながらも農業している人の数を補足するには、まぁまぁ適した項目だと思う。
基幹的農業従事者の説明は【図4】。

農業センサスから拝借しています。
あまり大昔まで遡ると悲しくなるばかりなので、ここ20年ほどの推移をみてみよう。平成2年からの基幹的農業従事者の水位が【図5】。
減ってるなーって感じで、黄矢印のようになだらかに減少していくのではないかと思われるが、自分の予測では【図6】くらいに急激に減少すると予想。

なんでかっていうと、もちろん根拠はあって、【図7】のとおりなわけだ。新規就農者は増えずに、そのまま高齢化が進んで行っている様子が手に取るようにわかる。
【図8】は平成2年と平成27年のトレンドを見たものだが、おおむねそのままスライドしていることが手に取るようにわかるだろう(15年スパンなので、年齢層は合致しないが、傾向はわかるだろう)。
こうした傾向から導き出したのが【図6】で、あと20年もすれば、基幹的農業従事者は1/3ほど、50万人を切ってしまうのではないかと危ぶまれる。
農業分野においてもIOT化は進んできているが、危機的状況に瀕していることは否めないだろう。

農業はあくまで一例にすぎず、次回はいよいよ外国人労働力の現状について、眺めてみたい。
っつーか、こういうことは、政府は当然、知ってるんだよね。当たり前だよね。政府統計だし、施策に生かすために「統計調査してます!」って、書いてあるし。マジで。無駄に統計調査してないよな。
施策の立案のために、外国人の多く住んでいる自治体や町内、企業など、なんとなく関係者にヒアリングしてみて、「こんなもんかなー」とかって思ってないよね。印象で語ってないよね。「対応方針案」とか出しているけど、みっちり統計データも見てるよね。
だって、関係者の人って、マクロ的な視点に立ってないでしょ?当たり前だけど。
政治家のことは知らんが、行政マンなら震えるほど仕事シロー!ってなことだ。