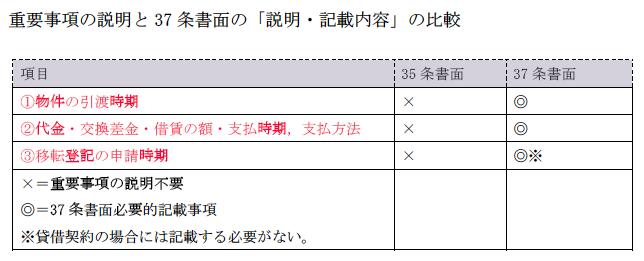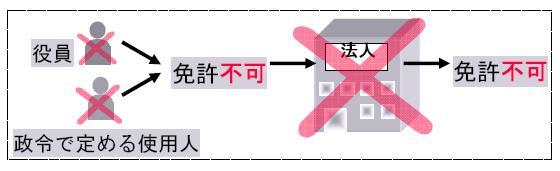権利金 【けんりきん】
賃貸借契約をする場合に、地主や家主に対して支払うのが権利金です。
借地権を設定するための対価、または家賃や地代の前払いという性格を持ちます。
いずれの場合も、借主が立ち退いた時に貸主から返還はされないのが一般的です。
そして、権利金は、土地の賃貸借(借地)や事業用として建物を貸す場合に定められることが多く、
借地の場合は何十年も貸すことに対する対価として、
事業用建物の賃貸の場合は、利益を生む建物に対しての対価としての性質を有します。
ちなみに、事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、
返還されないものは権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、
契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、
課税の対象にはなりません。
また、鑑定評価では、賃料の把握において、権利金の運用益および償却額は支払賃料とともに実質賃料の
構成要素となります。
国土利用計画法では、
・賃貸借・地上権設定契約で(設定の対価「権利金」がある場合)は
届出が必要な土地売買等の契約に該当します。
宅建業法の
貸借の報酬額の計算では
居住用建物以外
例:店舗・事務所・宅地では・・・
権利金等が授受されている場合は、権利金等の額を代金とみなして、売買の場合の報酬計算にしたがって算出し、
権利金等を基準として算出する報酬限度額と借賃の1カ月分を比較して高いほうが報酬限度額となります。
以上のようにいろいろな場面で登場します。
賃貸借契約をする場合に、地主や家主に対して支払うのが権利金です。
借地権を設定するための対価、または家賃や地代の前払いという性格を持ちます。
いずれの場合も、借主が立ち退いた時に貸主から返還はされないのが一般的です。
そして、権利金は、土地の賃貸借(借地)や事業用として建物を貸す場合に定められることが多く、
借地の場合は何十年も貸すことに対する対価として、
事業用建物の賃貸の場合は、利益を生む建物に対しての対価としての性質を有します。
ちなみに、事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、
返還されないものは権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、
契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、
課税の対象にはなりません。
また、鑑定評価では、賃料の把握において、権利金の運用益および償却額は支払賃料とともに実質賃料の
構成要素となります。
国土利用計画法では、
・賃貸借・地上権設定契約で(設定の対価「権利金」がある場合)は
届出が必要な土地売買等の契約に該当します。
宅建業法の
貸借の報酬額の計算では
居住用建物以外
例:店舗・事務所・宅地では・・・
権利金等が授受されている場合は、権利金等の額を代金とみなして、売買の場合の報酬計算にしたがって算出し、
権利金等を基準として算出する報酬限度額と借賃の1カ月分を比較して高いほうが報酬限度額となります。
以上のようにいろいろな場面で登場します。