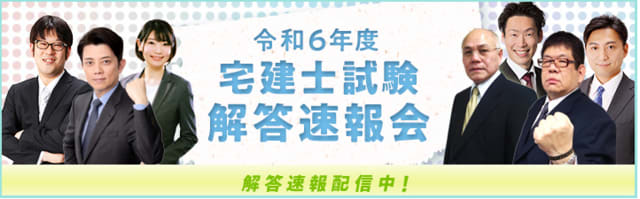【宅建令和06年問01】法律行為
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
2.公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
3.詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
4.他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
解説
① 正 意思能力を欠いている者の意思表示は無効である。
② 誤 公の秩序に反する法律行為は無効である。
③ 誤 強迫による意思表示も取り消すことによって初めから無効であったとみなされる。
④ 誤 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は有効である。
【宅建令和06年問02】委任契約・準委任契約
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、
業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、
買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
2.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
3.委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
4.委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
解説
① 正 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、
売主と一体となって一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、信義則上の義務を負うことがある(最判平17.9.16)。
② 正 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
③ 正 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨の合意がある場合、任意規定であるため、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
④ 誤 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。請負の定義である。
【宅建令和06年問03】共有
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
1.甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
2.甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、
所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
3.A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
4.Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額を
Aに対して支払うよう請求することができる。
解説
① 誤 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができない。過半数の同意ではない。
② 誤 保存行為は単独ですることができる。
③ 正 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる。土地の賃借権等は5年以内である。
④ 誤 所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、共有持分を取得・処分することができる。共有持分の時価相当額を支払うよう請求する期間は
3年以内に限定されない。
【宅建令和06年問04】相続
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における
次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、
本件契約を解除することができない。
2.Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
3.Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
4.本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
解説
① 誤 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告は不要である
② 誤 解除権は一身に専属した権利ではなく、相続される。
③ 誤 相続人は、当事者の関係にあり、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者ではない。
④ 正 相続人は、当事者の関係にあり、相手方は、詐欺による意思表示を取り消すことができる。
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
2.公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
3.詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
4.他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
解説
① 正 意思能力を欠いている者の意思表示は無効である。
② 誤 公の秩序に反する法律行為は無効である。
③ 誤 強迫による意思表示も取り消すことによって初めから無効であったとみなされる。
④ 誤 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は有効である。
【宅建令和06年問02】委任契約・準委任契約
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、
業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、
買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
2.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
3.委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
4.委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
解説
① 正 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、
売主と一体となって一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、信義則上の義務を負うことがある(最判平17.9.16)。
② 正 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
③ 正 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨の合意がある場合、任意規定であるため、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
④ 誤 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。請負の定義である。
【宅建令和06年問03】共有
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
1.甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
2.甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、
所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
3.A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
4.Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額を
Aに対して支払うよう請求することができる。
解説
① 誤 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができない。過半数の同意ではない。
② 誤 保存行為は単独ですることができる。
③ 正 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる。土地の賃借権等は5年以内である。
④ 誤 所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、共有持分を取得・処分することができる。共有持分の時価相当額を支払うよう請求する期間は
3年以内に限定されない。
【宅建令和06年問04】相続
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における
次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、
本件契約を解除することができない。
2.Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
3.Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
4.本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
解説
① 誤 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告は不要である
② 誤 解除権は一身に専属した権利ではなく、相続される。
③ 誤 相続人は、当事者の関係にあり、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者ではない。
④ 正 相続人は、当事者の関係にあり、相手方は、詐欺による意思表示を取り消すことができる。