
《『批評空間 Ⅱ 14』(太田出版)の表紙》
かつての私は、『宮澤賢治殺人事件』という刺激的なタイトルに戸惑いがあって、この本にもその著者の吉田司氏に対しても距離を置いていた。ところがその後、山折哲雄氏との対談『デクノボー「宮沢賢治の叫び』(朝日新聞出版)において、吉田氏の方がよくお調べになった上で対談しているのだということを知り、私はそれが切っ掛けで次第に認識を改めつつある。
たとえば、同氏は『宮澤賢治殺人事件』の中で賢治を〝即身仏〟になぞらえていたことを思い出して今見直してみると、こんなことが論じられていた。
飢饉の時、坊さんが地に掘った穴の中で飲まず食わず、ミイラになりながら、農民救済のために「五穀豊穣」を祈り続けて死んでゆく。文字通りの〈捨身〉である。ミイラ化した僧の遺体は、湯船できれいに洗って、金銀の法衣を着せ、お寺の中央の祭壇に飾る。光り輝くぶきみなミイラの仏様の誕生だ。…投稿者略…
ときどき坊さんの方が死ぬのが恐くなって逃げ出す場合があった。すると農民はこの坊主を捕らえてムリヤリ穴の中に投げ込んで土をかぶせたという。つまり自分たちの手で殺して〈聖なるミイラ〉を作ったわけだ。
〈『宮澤賢治殺人事件』(吉田司著、太田出版)252p~〉ときどき坊さんの方が死ぬのが恐くなって逃げ出す場合があった。すると農民はこの坊主を捕らえてムリヤリ穴の中に投げ込んで土をかぶせたという。つまり自分たちの手で殺して〈聖なるミイラ〉を作ったわけだ。
最初に吉田氏のこの主張を読んだときの私はかなり反発を感じたものだ。ところが、ここ十数年ほど私は「羅須地人協会時代」の賢治を中心にして検証作業を続けてきたのだがその結果だろう、今は同氏のこの主張をほぼ肯わざるを得ない。
そして最近、たまたま『批評空間 Ⅱ 14』(太田出版)を手に取って見ていたならば、その中に「共同討議 宮澤賢治をめぐって」という特集があって、それは、関井光男氏、村井紀氏、吉田司氏、柄谷行人氏の四者による討議であり、吉田司氏の『宮澤賢治殺人事件』を話題の中心にした討議だったので興味が引かれた。今であればもう反発はなくなっているし、その主張は本当の賢治を浮き上がらせてくれそうだから、これからしばらくこの討議に関連しての投稿をしてゆきたい。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 “〝「共同討議 宮澤賢治をめぐって」より〟の目次”へ。
“〝「共同討議 宮澤賢治をめぐって」より〟の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。













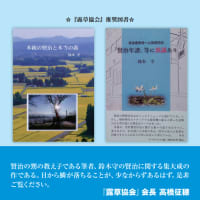
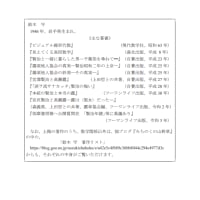
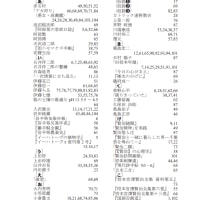
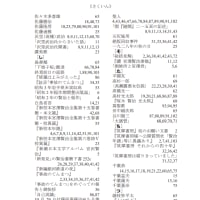

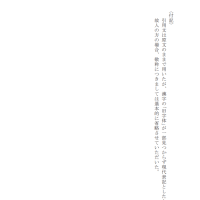
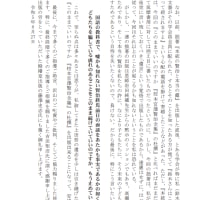
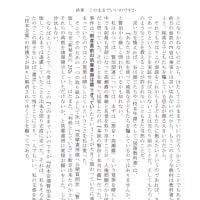
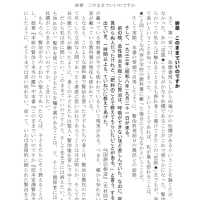






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます