
2011年の中山道 鵜沼宿 文化財MAP
所用で行ったついでに、太田宿の西にある鵜沼宿を訪れました。現代の中山道・国道21号線を車で走ると、木曽川の堤防沿いの道に「ロマンチック街道」という立て看板を発見。堤防の方が21号より高いので、どういう道路なのか見えなかったのを残念に思いながら、坂祝町勝山(さかほぎちょう かつやま)に至ります。ここは、一九先輩の『続膝栗毛五編上』に「かち山村の観音坂を過ぎ、あしどのひとつ茶屋」と記述された場所。現在も「えだ柿」が名物なのかどうか…。弥次喜多の頃は、山越え(うとう峠。現:うぬまの森)で大変だったでしょうが、21号線は木曽川沿いにJRと平行して山を迂回し、鵜沼にでます。
近年、勝山から北へ入り城山を貫通する新21号線バイパスができたので、そちらを走行。長いトンネルを抜け、高速道路並みのいい道路をまっすぐいくと、中山道鵜沼宿の東側に位置する交差点にでます。そこを右折して大安寺川を打ち過ぎ、宿場の駐車場へ行こうとしたところ、通行止め。イベント日にかちあってしまいました。

大安寺橋。この奥から街並み保存地区の鵜沼宿。
柳の向うにある、町屋を利用した釜飯屋さんで食事をしようと思っていたので、駐車場を探すと、すぐ向かいにありスペースも一台あったので、素早く駐車。駐車場に旧大垣城鉄門(平成21年に現在地へ移設。移築する前は個人宅の表門に使用されていた)があり、旧中山道を挟んで向かい側に歴史民俗資料館(旧武藤家)、その隣りにある釜飯屋さん(旧:宇留摩庵)へ入って、美味しい釜飯定食でお腹を満たし、散策を開始。
尺八の音色がして、振り向くと虚無僧が現る
鵜沼宿は平成18年から景観と建築物の保存・修復・復元、電線類を地下に埋めるなどしていて、平成23年のこの日「中山道鵜沼宿完成記念祭」をやっていたのでした。ラッキー!
奥に見える家が歴史民俗資料館(中山道鵜沼宿町屋館)
鵜沼宿の資料館は↑上の民俗資料館と脇本陣坂井家を復元した中山道鵜沼宿脇本陣で、共に無料公開されています。
普段非公開の町屋の住居内公開部分
ラッキーなことに、普段は表しか見られない文化財指定の旧家の土間(玄関)や座敷(一部)など見学できました。時計や屏風、棚の器物など博物館行きのお宝です。各住宅にガイドさんが居て、入ると丁寧に説明してくださったので、家の作りなど勉強になりました。
二ノ宮神社の石垣に取り込まれた古墳の石室
鵜沼宿辺りから加納宿辺りまでの中山道には、考古学ファンには有名な古墳群遺跡があり、鵜沼宿内にも脇本陣の隣り(裏山:一部芝生公園に使用)に二ノ宮神社と化して、円墳があります。古墳の石室が石垣に取り入れられていて、自由に見ることができます。
石室の上はこんな風になっています
神社はスタンプラリーのスタンプ会場になっていたので、親子連れなどが来てましたが、残念なことに古墳についての説明や立て看板などがないので、石室を見る人はいませんでした。古墳は原型をとどめていませんが、裏側は円形の名残がみられます。
神社の境内から鵜沼宿を望む
 本陣跡。現代の一般住宅が建っていました
本陣跡。現代の一般住宅が建っていました 車両進入禁止地区の西端まで来たので、駐車場まで戻り、そこから車で迂回して中山道に入り西へ少し行くと、空安寺の隣りに古墳があります。

結構大きな円墳
前にある駐車場に車を止めて、獣道のような路を分け入ってみると

坊の塚古墳北側、後円墳側にある説明板
この古墳の周囲は住宅密集地なので、知らないとわからないです。古墳の周囲を道路がぐるっと回っていますが、一部自動車が通れないので、徒歩でめぐると前方後円墳の形がわかります。ここは、立ち入れるような路はありませんでした。古墳の南側には国道21号線がはしってます。古墳は他にもたくさんありますが、調査後宅地化して住宅が建っているところが多く、残してある古墳も存在感がありません。私は、もし自分の住んでいる家が、もと古墳の上だったらどんな感じかしらん、と想像してみました。現代の墓地だったら気持ち悪いと感じるでしょうが、古墳なら何故かしら誇らしい(嬉しい?)気分になるなと思いました。
ところで、一九は『続膝栗毛』の鵜沼宿の段で、弥次さん喜多さんを飛脚との同道で往復させているにもかかわらず、古墳については一毛も触れていません。二ノ宮神社の石室についても。触れているのは、奈良漬(守口漬)の大根畑くらいです(現代の鵜沼の特産は人参)。因みに、宿の西の棒鼻にあった門田屋という茶屋はありませんが、架空の名前の茶屋だったのでしょうか。膝栗毛によく出てくる笹屋という旅籠名と同様に。
そういえば、埼玉県の岡部村の段でも、岡部六弥太の古跡(源平合戦の時代)は綴られていますが、中宿古代倉庫群跡(平成3年に第一次調査)については触れられていません。江戸時代には未だ考古学はないのですね。














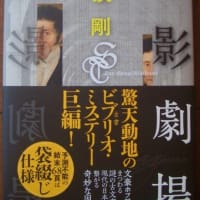

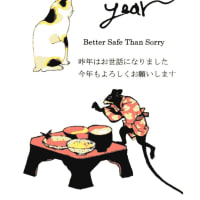
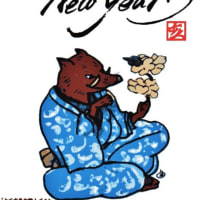
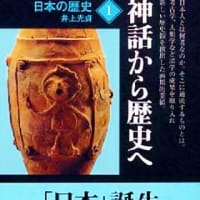






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます