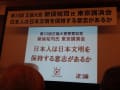5月1日(火)日本記者クラブにおいて「日本人は日本文明を保持する意志があるか」と題して満席の300人の前で1時間ほどの講演であった。新保氏は文芸批評家として活躍され、神武天皇の東征を題材にした奉祝曲「海道東征」の演奏復活に尽力された方で熟慮された言葉での執筆、講演、新聞への投稿などその活躍が期待される方である。現在64歳益々の活躍を期待したい。
米国の国際政治学者・サミュエル・ハンチントンは「文明の衝突」、日本が一国一文明であることを述べている。日本がユニークなのは、日本国と日本文明が合致しているからである。そのことによって日本は孤立しており、世界のいかなる他国とも文化的に密接につながりをもたない。これを基盤に「今後の日本人に、この悲劇的な栄光を保持し続ける精神的エネルギーがあるかどうかが今、問われていると。今の現状から懐疑的な話をされた。そして北畠親房と吉田兼好を比較された。
北畠親房…神皇正統記のなかで「代くだれりとて自らいやしむべからず、天地の始は今日を始とする理なり」と。
吉田兼好…徒然草に「何事も、古き世のみぞ慕わしき。今様は、無下にいやしくこそなりゆくめれ」とある。しかし、このような慨嘆はいつの時代にも繰り返されたものにすぎないと述べられた。
皇太子さまの即位・改元が来年5月1日に決定し、126代の天皇となられる。まさに親房の「天地の始は今日を始めとする」と決意し、戦後の惰眠から覚醒して日本文明の復興に取り組むべきと語る。そして新保氏が明治の精神を最も感じる作家のひとりが国木田独歩で、「非凡なる凡人」という短編小説がある。その中で「貧しく特別な才能や環境に恵まれなくとも、一歩一歩実直に努力することで自分の人生を切り開いた友人を描いた。この主人公こそが明治の人の典型であると考える。こんな「非凡なる凡人」が多くいたからこそ(数百万人)、明治という時代は躍動したのだろうと語られた。
現代の主要文明…①中華文明、②日本文明、③ヒンドゥー文明、④イスラム文明、⑤西欧文明、⑥東方正教会文明、⑦ラテンアメリカ文明、⑧アフリカ文明と大別される。
文明…機械、技術、物質的要素にかかるもの
文化…価値観や理想、高度に知的、芸術的、道徳的な社会の質にかかるも
そこで新保氏は、今年は明治維新150年。明治の日本は、西洋文明と遭遇し、それに果敢に応戦した。いかにして日本人は西洋文明に対峙し、日本文明を保持しえたのか。明治の精神を、壮大な気風を持って改装しなければならない。自らの民族の歴史を回想す力を失うことはトインビー的にいえば文明の衰退の兆候なのだ。
明治の精神とは何か。
1つ目は、明治の精神は日本人の伝統精神という台木に西洋文明という接ぎ木がされていたということである。その見事な枝ぶりを示したのが明治の日本だった。
2つ目は、明治の精神の典型は、国木田独歩の名作の題名である「非凡なる凡人」の精神である。
3つ目は、「義の精神」だ。日本文明は美の文明とおもわれるかもしれないが、その中でまれに義を愛する人たちがでてくる。西郷隆盛、勝海舟など義を貫く人間たちが活躍した。ある意味この明治維新で活躍した人たちは”日本人離れ”した人たちであった。
昭和15年完成の交声曲「海道東征」の復活を「戦前の復活だ」という人もいるが、決して戦前の復活ではなく「明治70年代の復活」なのだ。日本文明の一番の問題は、戦前ならぬ明治70年代と戦後とで文明が断絶してしまったことであい、敗戦を機にふういんされた「海道東征」が今、復活sつつあることは、明治70年代の復活だ。これは日本文明の将来にとって大きな意義を持つ出来事だろうと。
そして、「海道東征」演奏されアンコールに応え「海ゆかば」を聴きながら、戦後70余年がたって、ついに日本文明の復興が始まったのではとも語られていた。「海道東征」の演奏会には川崎で行われたときに夫婦で出かけた。新保祐司氏の著書の一つ「『海道東征』への道」購入しその精神の一端ン時に触れていたので講演内容をある程度理解しながら聴衆した。

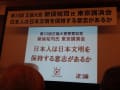




米国の国際政治学者・サミュエル・ハンチントンは「文明の衝突」、日本が一国一文明であることを述べている。日本がユニークなのは、日本国と日本文明が合致しているからである。そのことによって日本は孤立しており、世界のいかなる他国とも文化的に密接につながりをもたない。これを基盤に「今後の日本人に、この悲劇的な栄光を保持し続ける精神的エネルギーがあるかどうかが今、問われていると。今の現状から懐疑的な話をされた。そして北畠親房と吉田兼好を比較された。
北畠親房…神皇正統記のなかで「代くだれりとて自らいやしむべからず、天地の始は今日を始とする理なり」と。
吉田兼好…徒然草に「何事も、古き世のみぞ慕わしき。今様は、無下にいやしくこそなりゆくめれ」とある。しかし、このような慨嘆はいつの時代にも繰り返されたものにすぎないと述べられた。
皇太子さまの即位・改元が来年5月1日に決定し、126代の天皇となられる。まさに親房の「天地の始は今日を始めとする」と決意し、戦後の惰眠から覚醒して日本文明の復興に取り組むべきと語る。そして新保氏が明治の精神を最も感じる作家のひとりが国木田独歩で、「非凡なる凡人」という短編小説がある。その中で「貧しく特別な才能や環境に恵まれなくとも、一歩一歩実直に努力することで自分の人生を切り開いた友人を描いた。この主人公こそが明治の人の典型であると考える。こんな「非凡なる凡人」が多くいたからこそ(数百万人)、明治という時代は躍動したのだろうと語られた。
現代の主要文明…①中華文明、②日本文明、③ヒンドゥー文明、④イスラム文明、⑤西欧文明、⑥東方正教会文明、⑦ラテンアメリカ文明、⑧アフリカ文明と大別される。
文明…機械、技術、物質的要素にかかるもの
文化…価値観や理想、高度に知的、芸術的、道徳的な社会の質にかかるも
そこで新保氏は、今年は明治維新150年。明治の日本は、西洋文明と遭遇し、それに果敢に応戦した。いかにして日本人は西洋文明に対峙し、日本文明を保持しえたのか。明治の精神を、壮大な気風を持って改装しなければならない。自らの民族の歴史を回想す力を失うことはトインビー的にいえば文明の衰退の兆候なのだ。
明治の精神とは何か。
1つ目は、明治の精神は日本人の伝統精神という台木に西洋文明という接ぎ木がされていたということである。その見事な枝ぶりを示したのが明治の日本だった。
2つ目は、明治の精神の典型は、国木田独歩の名作の題名である「非凡なる凡人」の精神である。
3つ目は、「義の精神」だ。日本文明は美の文明とおもわれるかもしれないが、その中でまれに義を愛する人たちがでてくる。西郷隆盛、勝海舟など義を貫く人間たちが活躍した。ある意味この明治維新で活躍した人たちは”日本人離れ”した人たちであった。
昭和15年完成の交声曲「海道東征」の復活を「戦前の復活だ」という人もいるが、決して戦前の復活ではなく「明治70年代の復活」なのだ。日本文明の一番の問題は、戦前ならぬ明治70年代と戦後とで文明が断絶してしまったことであい、敗戦を機にふういんされた「海道東征」が今、復活sつつあることは、明治70年代の復活だ。これは日本文明の将来にとって大きな意義を持つ出来事だろうと。
そして、「海道東征」演奏されアンコールに応え「海ゆかば」を聴きながら、戦後70余年がたって、ついに日本文明の復興が始まったのではとも語られていた。「海道東征」の演奏会には川崎で行われたときに夫婦で出かけた。新保祐司氏の著書の一つ「『海道東征』への道」購入しその精神の一端ン時に触れていたので講演内容をある程度理解しながら聴衆した。