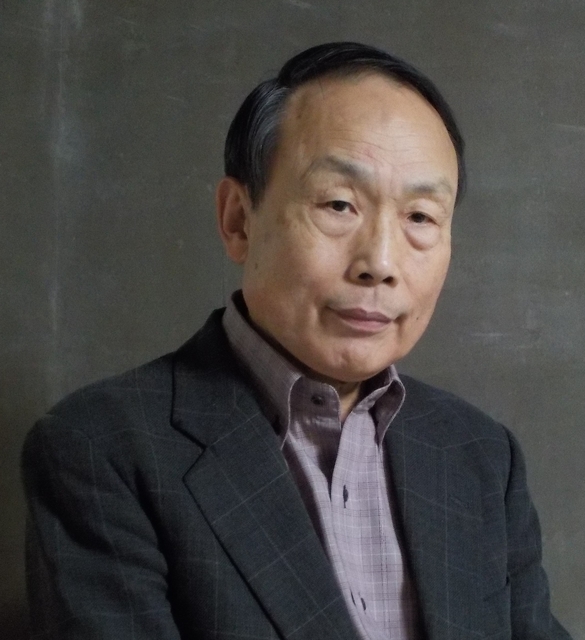詩と詞は、小説と戯曲(脚本)の関係に近い。それは鑑賞の方法が、本を読むという行為と俳優の演技を見つめるという行為とに分かれるからである。それと同様に、詩poemと詞words;lyricsとは異なる。広い意味での詩形式poetryは共有するが、前者は読書を通して鑑賞され、後者は歌手の歌唱によって聴衆に届けられる。
「詞」は読まれるのではなく聴かれることを想定し、歌手や合唱団による歌唱表現を前提にして書かれている。戯曲(脚本)のセリフが俳優の言語および演技表現を前提にして書かれると同様、「詞」は詩人の言葉のみによって完結する「詩」とは異なり、作者から離れた言語および演技的・音楽的表現を通して成立する文芸だということになる。
オペラ“Opera”はクラシック音楽に分類されていてそのほとんどがドイツ・イタリアを中心とする西欧古典作品であり、“lyric drama”とも呼ばれる叙情詩の歌劇である。日本人歌手はそれを原語で歌唱することになるが、オペラファンは演じられる歌劇のストーリーも有名なアリアや重唱もよく知っているので、外国語であっても楽しめる。しかし、オペラ体験の浅い聴き手にとっては言葉の壁は厚い。公演プログラムには「物語・登場人物・各景ごとの内容」が掲載されているが、やはり、歌手が歌う言葉そのものが理解できないと楽しめない。たとえ字幕で訳語が映されたとしても直に心に響かない。
そこで、私は日本語による新作オペラの制作を企画し、オペラユニット「東京ミニオペラカンパニー」を立ち上げ、タイプの違う二つの作品を創作し上演することでオペラファンの裾野を広げたいと願った。これまでも創作オペラ・日本語による新作オペラは発表されてきたが、そこに見られる問題点を検討し演劇的にも音楽的にも魅力ある現代オペラを生み出したいと考えたわけである。

 最初は、シェイクスピア劇『ハムレット』原作のミニオペラ『悲恋~ハムレットとオフィーリア』(2016年JTアートホールアフィニス)。次に日本の伝説から『雪女の恋』(2019年東京文化会館小ホール)をオペラ作品として制作した。その意図や目的、また具体的な制作過程は、下記のブログに掲載したのでご覧頂きたい。
最初は、シェイクスピア劇『ハムレット』原作のミニオペラ『悲恋~ハムレットとオフィーリア』(2016年JTアートホールアフィニス)。次に日本の伝説から『雪女の恋』(2019年東京文化会館小ホール)をオペラ作品として制作した。その意図や目的、また具体的な制作過程は、下記のブログに掲載したのでご覧頂きたい。


東京ミニオペラカンパニーと創作ミニオペラ公演①
2016/07/18 16:30:06 カテゴリー:オペラ
新作オペラ『雪女の恋』制作過程1<脚本①>
2018/03/10 20:14:52 カテゴリー:オペラ
今後、オペラにおける母語の詞とは/ドラマティックな構成台本とは/一般に親しまれる作品世界とはを追求するとともに、歌手やコーラスの歌唱表現に求められることにも言及していきたい。












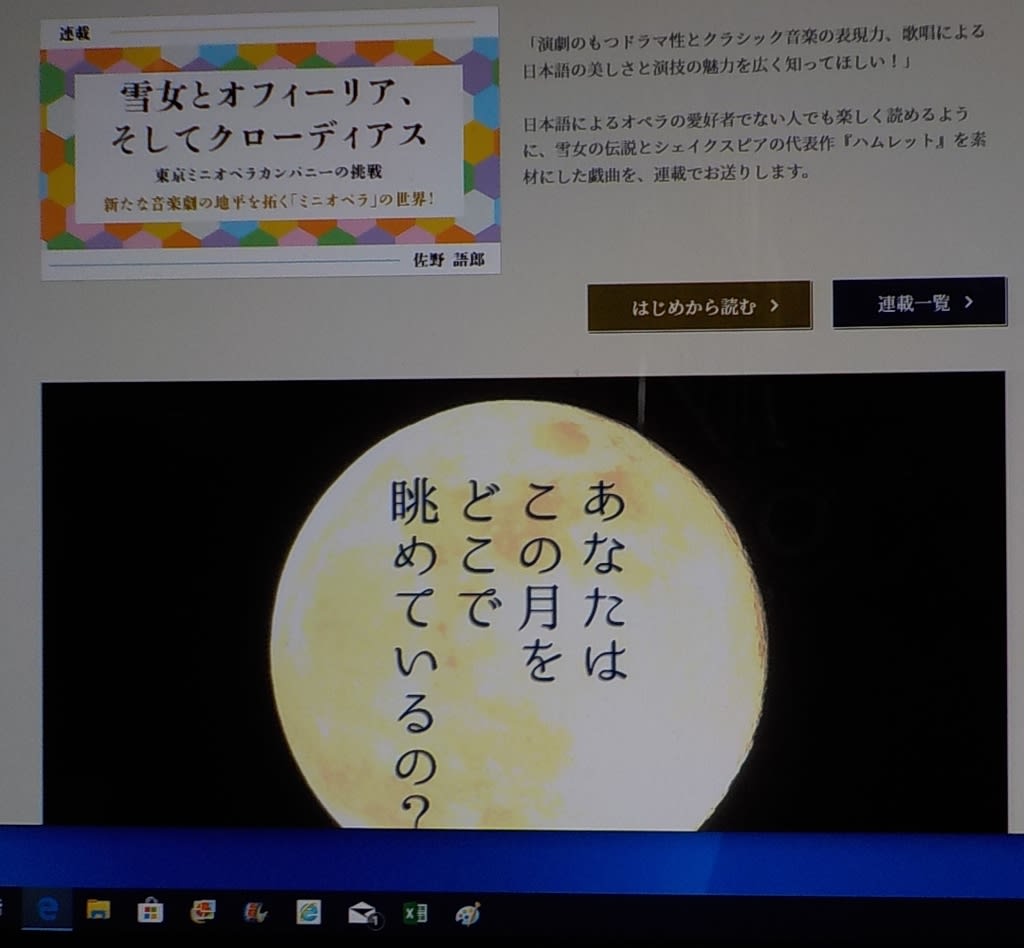




 その経緯および理由は当ブログの「語られる歌と歌われる音楽」(2017年8・9・10月)などに詳しいが、オペラの専門家による客観的な視点からその上演活動や創作内容を批評した論考が、近著『雪女とオフィーリア、そしてクローディアス 東京ミニオペラカンパニーの挑戦』(2019年・幻冬舎刊)に収められている。
その経緯および理由は当ブログの「語られる歌と歌われる音楽」(2017年8・9・10月)などに詳しいが、オペラの専門家による客観的な視点からその上演活動や創作内容を批評した論考が、近著『雪女とオフィーリア、そしてクローディアス 東京ミニオペラカンパニーの挑戦』(2019年・幻冬舎刊)に収められている。 また、同書には「オペラにおける演劇」をいわゆるグランドオペラにおける演劇性ではなく「ミニオペラ」という小歌劇ならではのドラマ性や劇的展開について、さらに「日本語オペラ」の可能性と重要性について制作サイドから述べられた文章がまとめられており、以下にその一部を抄録する。
また、同書には「オペラにおける演劇」をいわゆるグランドオペラにおける演劇性ではなく「ミニオペラ」という小歌劇ならではのドラマ性や劇的展開について、さらに「日本語オペラ」の可能性と重要性について制作サイドから述べられた文章がまとめられており、以下にその一部を抄録する。
 …東京ミニオペラカンパニーの目指すところは、「うた」ということに尽きるのだと思う。オペラの舞台から不用なものを差し引いてゆくと、最後に残るのが人間の声。「うた」で人間を表現できる声。私の演出の仕事は、うたに潜むドラマを引き出し、うたを支える身体を発見し、ギリシャ古典劇以来、舞台芸術が創り上げてきた様々な演技の様式を、その発想にまで溯り、単なる型でも形でもない、身体感覚のリアリティとして捉え直す作業にあった。…【十川 稔 オペラ演出家 東京藝術大学音楽学部、二期会オペラ研修所にて舞台演技を指導】
…東京ミニオペラカンパニーの目指すところは、「うた」ということに尽きるのだと思う。オペラの舞台から不用なものを差し引いてゆくと、最後に残るのが人間の声。「うた」で人間を表現できる声。私の演出の仕事は、うたに潜むドラマを引き出し、うたを支える身体を発見し、ギリシャ古典劇以来、舞台芸術が創り上げてきた様々な演技の様式を、その発想にまで溯り、単なる型でも形でもない、身体感覚のリアリティとして捉え直す作業にあった。…【十川 稔 オペラ演出家 東京藝術大学音楽学部、二期会オペラ研修所にて舞台演技を指導】