先週末(10月28日)の地域漁業学会の報告の要旨です。
一応,解禁だろう…
東村玲子*・大西学**
(*福井県立大学・**名古屋外国語大学)
1.問題意識
現在,日本では7魚種を対象にTACによる漁業管理が行われている。TACの下での漁業管理の方法として個別割当(IQ)や譲渡可能個別割当(ITQ)を採用している国も多い。また,そうした事例が漁業管理の成功事例として紹介され,逆に日本のTAC管理が「オリンピック方式」として批判されることもある。それでは,IQやITQを導入しない日本のTACでは漁業管理は上手く行っていないのであろうか。本報告のタイトルにある「日本型TAC」とは,次の特徴を特に意識している。①TACは政府が決めるが,その運用は原則的に業界団体が行う,②漁獲量は産地市場での仕切り伝票から導き出される。
2.目的と課題
本報告の目的は,TAC以前より漁業者(組織)による自主的管理が行われて来た日本海A海域(富山県沖から島根県沖)のズワイガニの大臣管理分の漁業管理の実態を明らかにすることにより,日本型TACの実態を詳しく見て行くこと,及びその過程で,日本型TACがなぜ上手く機能しているのかを明らかにする。その上で,個別割当について考察する。
日本海A海域のズワイガニ漁業管理の流れは次の様になっている。5月の水産政策審議会において,その年の11月~翌年3月までのTACが決定される。同時に大臣管理分と知事管理分に分けられ,後者は府県にさらに分けられる。大臣管理分は過去3年間の実績を基に予め決められた配分方式によって各府県に割り当てられ,以降は各府県の底曳網漁業の業界団体による管理となる。
日本海ズワイガニ特別委員会が9月末から10月初旬に開催されて各府県別割当が確認されるが,この会合の本来の目的は,自主的管理規制を決めることである。その内容は,漁期,サイズ,1航海辺りの漁獲量,そしてミズガニ禁漁に関わることである。
A海域のズワイガニ漁獲量は,2005年以降はTACを超えたことがほぼない。しかし,漁業者への聞き取り調査では,自分のズワイガニの漁獲金額は全員が把握していたが,量については,誰も把握していなかったし,府県別の割当数量も頭になかった。すなわち,自主的管理規制を守っていればTACに達しない様になっているのである。また,全国的な業界団体と各府県の業界団体との責任の分離とその所在が明確であるのも特徴的である。
個別割当についての聞き取り調査では反対が圧倒的に多かった。現状で上手く行っているのだから,何もわざわざ新しい規制を加える必要もないとの結論である。
キーワード:日本型TAC,自主的管理規制,業界団体,ズワイガニ,個別割当
一応,解禁だろう…
東村玲子*・大西学**
(*福井県立大学・**名古屋外国語大学)
1.問題意識
現在,日本では7魚種を対象にTACによる漁業管理が行われている。TACの下での漁業管理の方法として個別割当(IQ)や譲渡可能個別割当(ITQ)を採用している国も多い。また,そうした事例が漁業管理の成功事例として紹介され,逆に日本のTAC管理が「オリンピック方式」として批判されることもある。それでは,IQやITQを導入しない日本のTACでは漁業管理は上手く行っていないのであろうか。本報告のタイトルにある「日本型TAC」とは,次の特徴を特に意識している。①TACは政府が決めるが,その運用は原則的に業界団体が行う,②漁獲量は産地市場での仕切り伝票から導き出される。
2.目的と課題
本報告の目的は,TAC以前より漁業者(組織)による自主的管理が行われて来た日本海A海域(富山県沖から島根県沖)のズワイガニの大臣管理分の漁業管理の実態を明らかにすることにより,日本型TACの実態を詳しく見て行くこと,及びその過程で,日本型TACがなぜ上手く機能しているのかを明らかにする。その上で,個別割当について考察する。
日本海A海域のズワイガニ漁業管理の流れは次の様になっている。5月の水産政策審議会において,その年の11月~翌年3月までのTACが決定される。同時に大臣管理分と知事管理分に分けられ,後者は府県にさらに分けられる。大臣管理分は過去3年間の実績を基に予め決められた配分方式によって各府県に割り当てられ,以降は各府県の底曳網漁業の業界団体による管理となる。
日本海ズワイガニ特別委員会が9月末から10月初旬に開催されて各府県別割当が確認されるが,この会合の本来の目的は,自主的管理規制を決めることである。その内容は,漁期,サイズ,1航海辺りの漁獲量,そしてミズガニ禁漁に関わることである。
A海域のズワイガニ漁獲量は,2005年以降はTACを超えたことがほぼない。しかし,漁業者への聞き取り調査では,自分のズワイガニの漁獲金額は全員が把握していたが,量については,誰も把握していなかったし,府県別の割当数量も頭になかった。すなわち,自主的管理規制を守っていればTACに達しない様になっているのである。また,全国的な業界団体と各府県の業界団体との責任の分離とその所在が明確であるのも特徴的である。
個別割当についての聞き取り調査では反対が圧倒的に多かった。現状で上手く行っているのだから,何もわざわざ新しい規制を加える必要もないとの結論である。
キーワード:日本型TAC,自主的管理規制,業界団体,ズワイガニ,個別割当










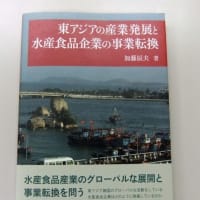
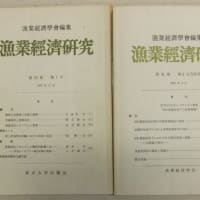
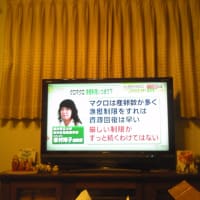
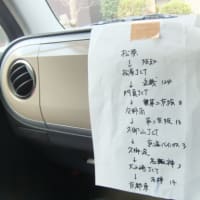


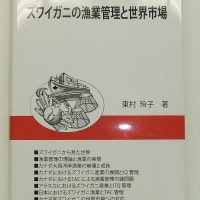
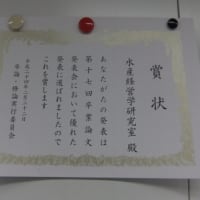








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます