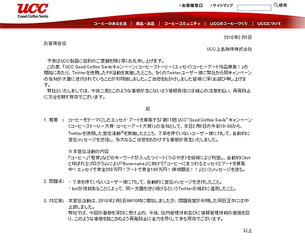アップルの新メディア機器ipadの日本発売5月28日を前に購入予約が開始され、行列ができるなどの話題を提供するとともに、雑誌メディアでは続々ipad特集が組まれちょっとした騒ぎになっています。でもipadってそんなに新しいものなの?って個人的にはちょっと思っています。アップルの戦略を紐解くとipadは決して最新鋭のメディア機器が出たということではないという結論になるような気がするのですが・・・。
iphoneですっかりスマートフォン市場を先導する形になったアップルが、アマゾン=キンドル、SONY=リーダーにぶつけてきた新しいメディア機器がipadであるというのが当初のマスコミ発の触れ込みだったのですが、どうやら全貌が明らかになるにつれてそうではないと言う事が明確になってきました。そう、ipadはキンドルやリーダーのようなブック・リーダーではなくて“本も読める”多機能メディア機器なのですね。アップルはituneストアで音楽メディアやゲームをはじめとしたアプリケーションを販売していますが、「今度は本も読みやすいメディア機器をご用意しましたので、ぜひこの新しいアップルの機器を使ってituneストアをご利用ください」が彼らのビジネスにおける今回の狙いな訳です。
そもそもiphoneだって彼らは電話機を作りたかった訳ではなくて、ipodに電話機能を持たせることでより多くの人をituneストアに呼び込もうとした訳なのです。携帯電話の機能で戦おうなどとはハナから思っていないのです。忘れてはいけないことは、彼らの現在のビジネスのメインはituneストアでいかに買い物をしてもらうかであり、そのためにソフト開発プラットフォームを公開していかに多くの便利なアプリケーションを第三者に自発的に作らせるかである訳です。その意味でアップルの基本メディア機器は、どこまで行ってもパソコンのMACと携帯デジタルメディア機器のipodなのです。ipodだってそもそもが携帯音楽機器ではなかったのです。携帯音楽機器ウォークマンのSONYは、ipodが音楽機器ではない総合携帯デジタルメディアであったがためにipodに負けた訳です。まずは音楽ファンを取り込んでその次がスマートフォン購買層、そして今度が愛読家。ちなみに書籍のネット販売に関しては、先行し圧倒的な電子書籍数をほこるアマゾンとの共同戦線が得策という訳で、アマゾンから購入できるソフトもダウンロードできるのです。
さてさて話を戻してipadです。でそう考えてくるとやはり今回のipadは書籍購入者を新たなターゲットとしてituneストアに引き込むためのメディア機器であり、書籍を読みやすくするために画面を大きくしたipodであるということになるのではないかと思うのです。ipodは音楽鑑賞を入口にして利用者を囲い込み、ipadは読書を入口にして利用者を囲い込む、アップルのituneストア引込戦略であるのです。機器を安く提供して消耗品で儲けるという商売はコピー機器やPCプリンタなど古くからあるのですが、トナーなインクカートリッジの代わりに音楽データやアプリケーションや書籍販売で同じ形式の商売を展開している訳なのです。な~んだ、って感じでしょ。と言う訳で、ipadはどうしても画面で本が読みたいとか、大きな画面でipodやiphoneでのダウンロード・ゲームを楽しみたいとかいう人向きのメディア機器であるという感じがしております。なので私は当面購入見送りです。確かに仕事柄、多くの書籍を持ち歩く私としては、700グラム弱の薄型端末一つでいろいろな書籍を持ち歩ける利便性は魅力ではありますが、まだちょっと様子見かなと。
このように中身は決してピカピカに新しいメディア機器ではないipadが、こんなにも最新鋭機器的に注目されてしまうのは、アップルのブランドイメージのなせる技に他なりません。そのブランド・イメージは、もちろん商品やPRやIRなど様々な要素が総合した結果なのですが、忘れていけないのはその企業で働くスタッフのプライドやモラールも重要な要素になっているということです。先日ゴールデン・ウィーク期間中に銀座のアップル・ストアに出かけてみたのですが、大混雑の店内にありながらどのフロアにいってみてもスタッフの楽しそうに動きまわる姿や明るさに驚かされました。経営者の方にはぜひ一度足を運ばれることをおススメいたします。店内のスタッフと商品を見るにつけ、やはり「企業を光らせるのは人であり、その人をその気にさせるのは経営である」と、つくづく実感させられる空間であります。「当面アップルに敵なし」を感じさせられる今のアップルのブランド力は、人と商品が共に活きてこそなし得たモノであることを雄弁に物語っているのです。
iphoneですっかりスマートフォン市場を先導する形になったアップルが、アマゾン=キンドル、SONY=リーダーにぶつけてきた新しいメディア機器がipadであるというのが当初のマスコミ発の触れ込みだったのですが、どうやら全貌が明らかになるにつれてそうではないと言う事が明確になってきました。そう、ipadはキンドルやリーダーのようなブック・リーダーではなくて“本も読める”多機能メディア機器なのですね。アップルはituneストアで音楽メディアやゲームをはじめとしたアプリケーションを販売していますが、「今度は本も読みやすいメディア機器をご用意しましたので、ぜひこの新しいアップルの機器を使ってituneストアをご利用ください」が彼らのビジネスにおける今回の狙いな訳です。
そもそもiphoneだって彼らは電話機を作りたかった訳ではなくて、ipodに電話機能を持たせることでより多くの人をituneストアに呼び込もうとした訳なのです。携帯電話の機能で戦おうなどとはハナから思っていないのです。忘れてはいけないことは、彼らの現在のビジネスのメインはituneストアでいかに買い物をしてもらうかであり、そのためにソフト開発プラットフォームを公開していかに多くの便利なアプリケーションを第三者に自発的に作らせるかである訳です。その意味でアップルの基本メディア機器は、どこまで行ってもパソコンのMACと携帯デジタルメディア機器のipodなのです。ipodだってそもそもが携帯音楽機器ではなかったのです。携帯音楽機器ウォークマンのSONYは、ipodが音楽機器ではない総合携帯デジタルメディアであったがためにipodに負けた訳です。まずは音楽ファンを取り込んでその次がスマートフォン購買層、そして今度が愛読家。ちなみに書籍のネット販売に関しては、先行し圧倒的な電子書籍数をほこるアマゾンとの共同戦線が得策という訳で、アマゾンから購入できるソフトもダウンロードできるのです。
さてさて話を戻してipadです。でそう考えてくるとやはり今回のipadは書籍購入者を新たなターゲットとしてituneストアに引き込むためのメディア機器であり、書籍を読みやすくするために画面を大きくしたipodであるということになるのではないかと思うのです。ipodは音楽鑑賞を入口にして利用者を囲い込み、ipadは読書を入口にして利用者を囲い込む、アップルのituneストア引込戦略であるのです。機器を安く提供して消耗品で儲けるという商売はコピー機器やPCプリンタなど古くからあるのですが、トナーなインクカートリッジの代わりに音楽データやアプリケーションや書籍販売で同じ形式の商売を展開している訳なのです。な~んだ、って感じでしょ。と言う訳で、ipadはどうしても画面で本が読みたいとか、大きな画面でipodやiphoneでのダウンロード・ゲームを楽しみたいとかいう人向きのメディア機器であるという感じがしております。なので私は当面購入見送りです。確かに仕事柄、多くの書籍を持ち歩く私としては、700グラム弱の薄型端末一つでいろいろな書籍を持ち歩ける利便性は魅力ではありますが、まだちょっと様子見かなと。
このように中身は決してピカピカに新しいメディア機器ではないipadが、こんなにも最新鋭機器的に注目されてしまうのは、アップルのブランドイメージのなせる技に他なりません。そのブランド・イメージは、もちろん商品やPRやIRなど様々な要素が総合した結果なのですが、忘れていけないのはその企業で働くスタッフのプライドやモラールも重要な要素になっているということです。先日ゴールデン・ウィーク期間中に銀座のアップル・ストアに出かけてみたのですが、大混雑の店内にありながらどのフロアにいってみてもスタッフの楽しそうに動きまわる姿や明るさに驚かされました。経営者の方にはぜひ一度足を運ばれることをおススメいたします。店内のスタッフと商品を見るにつけ、やはり「企業を光らせるのは人であり、その人をその気にさせるのは経営である」と、つくづく実感させられる空間であります。「当面アップルに敵なし」を感じさせられる今のアップルのブランド力は、人と商品が共に活きてこそなし得たモノであることを雄弁に物語っているのです。