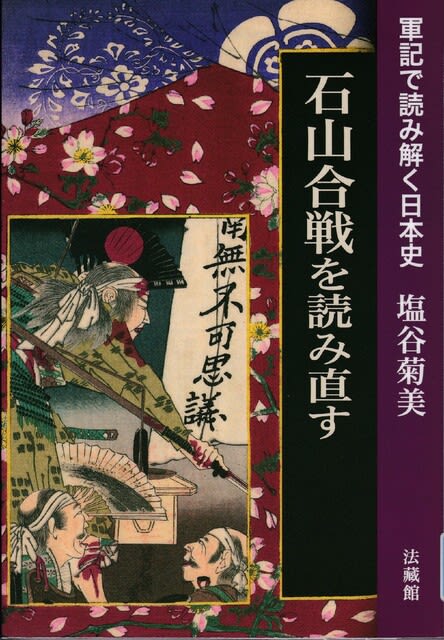
『石山合戦を読み直す』(2021/12/10・塩谷菊美著)、図書館の新刊本のコーナーにあった本です。「そんなんだ」と思った記述を一つ。
「石山本願寺」が十年問も信長の「支配」に「反抗」し続ける。有名人が有名の度を競い合うような歴
史教科書で、無名人の集団が。方の主人公となる希有な一場面である。
だが、「一向一揆」や「石山本願寺」という語句は、戦国時代には存在していないことが明らかになっている。2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」でも「大阪本願寺」とされ、「石山本願寺」とは呼ばれなかった。
まず、「一向一揆」の語は、明治半ばに東京葷国大学文科大学足東京大学)の学者たちが使い始めてから広まったのであって、戦国時代はおろか江戸時代にもごくわずかな用例しか見出せない。史料上では単に「一揆」か、江戸時代には「一向の乱」「一向の一揆」「一向宗の一揆」などとされている。
本願寺門徒の一揆であってもなくても、一揆は一般に「紀州の一揆」「土民の一揆」など、「どこそこの一揆」や「だれそれの一揆」の形で呼ばれてきた。「一向の一揆」であれば、そうした多様な一揆の中の一というだけだが、「一向一揆」と一語に熟すると、一揆一般と異なる特別な一揆という感じが強まる。
戦国時代や江戸時代には、本願寺門徒の一揆を指す特別な語が存在しなかった。これはすなわち、そういう認識が存在しなかったということだ、本願寺門徒の一揆も明治半ば以前はただの一揆で、特別な何かではなかったという見方が出てくることになる。(以上)
次に「石山」については、「大坂」にあった本願寺の焼失後、跡地に建てられた豊臣秀吉の城に「石山」の異名があったことがわかっている。仙台城が青葉城、姫路城が白鷺城と呼ばれたように、前代未聞の壮大な石垣で囲まれた豊巨大坂城は石山城と呼ばれたのだが、この城も慶長二〇年(匸二万の大坂夏の陣で焼け落ち、徳川家康はその上に盛り土をして新たな城を築いた。
現在の大坂城はこの徳川大坂城の遺構である。江戸時代に「石山」はかつての本願寺の所在地として用いられるようになった。本願寺のあった場所が「石山」になれば、豊臣大阪城や徳川大坂城も「石山」にあったと言われそうなものだが、そうなっていない。「石山」はあくまでも「本願寺」とセットである。
その意味では「石山」は一度も実際に使われたことのない、架空の地名といった方が適切だろう。歴史学は架空や虚構を避けようとするから、近年では「大坂本願寺」「豊臣大坂城」「徳川大坂城」と呼ぶことで一致を見ている。(以上)





























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます