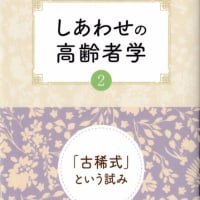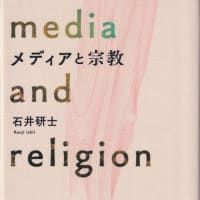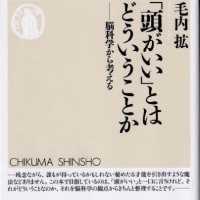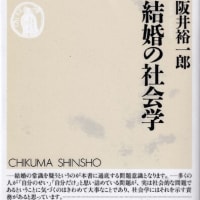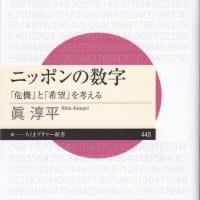『理想的な利他: 仏教から考える』(2023/2/2・平岡聡著)からの転載です。
宗教の本質
ここでは宗教の本質について考える。宗教の定義は多種多様だが、ここでは西谷[1961]の宗教論を取り上げよう。西谷は冒頭で「宗教は我々にとって、何のためにあるか」という問いは、宗教の本質からいって、問いとして間違っているという。問題なさそうな表現だが、ここにこそ宗教の本質が隠されている。この間違った問いを破るには、「我々自身が何のためにあるか」という問いを立てなければならないと西谷は言う。これは「我々自身が絶対なるもの(人間を超越したもの)に対いし、いかにあるべきか」といい換えてもよい。宗教は基本的に、“人間(相対者)”と、“人間を越えた存在(絶対者)”との関係を基軸にする。そして人間を越えた存在との関わりの中で、現実の人間のあり方に何らかの変化が生じる。この変化は「アイデンティティの変更」であり、私はこれを「自我の相対化」と表現する。こうして人間の生が根底から更新されることで、人生の根本問題が解決され、人生を有意にとらえ直す地平が開ける。ここに宗教の本質があるなら、さきほどの問題は氷解する。「宗教は我々にとって、何のためにあるか」という問いは、その問い自体がすでに“白己中心性”を含んでいる。これは、我々白身を円の中心に置いて宗教を周辺に迫いやり、「宗教が自分にとってプラスかマイナスか」という、功利的な自己中心性を言外に含んだ問いであることを図らずも暴露した問いなのだ。
だが、宗教は円の中心に自我を越えた存在を置き、それによって自我を相対化する。人間は中心から円周に場所を移さなければならない。だから「人間を越えた存在にとって、我々の方がどうあるべきか」が問われなければならない。宗教は自我中心的な人間のあり方を否定し、自我を相対化するので、必ず自分自身の変容を伴う。キリスト教なら中心に位置するのは神(あるいは神の子イエス)であり、その神にたいして我々がどうあるべきかが問われる。一方、神の存在意義を認めない仏教が中心に据えるべきは「法(真理二(この場合の「法」は「法身」としての仏も含まれる)であり、これによって自我を相対化する。
仏教の中でも浄土教では阿弥陀仏が中心に坐り、その阿弥陀仏にとって我々がどうあるべきかが問われる。つまり、自分自身の変容を伴うのが宗教であり、自分がすべての中心に坐り、したがって自分自身の変容を伴わず、かえって自我が肥大化するようなあり方は、宗教とは正反対なのだ。宗教において、我々の存在は絶対なるもの(人間を超越したもの)によって相対化されなければならない。
この他力の概念は、親鸞をもってそのクライマックスを迎える。親鸞はすべてを阿弥陀仏からの一方的な働きかけと理解し、念仏しようという並‥なる心持ちさえも「如来より賜りたる信心」の働きととらえるので、親鸞の説く他力は「絶対他力」と形容される。(以上)
宗教の本質
ここでは宗教の本質について考える。宗教の定義は多種多様だが、ここでは西谷[1961]の宗教論を取り上げよう。西谷は冒頭で「宗教は我々にとって、何のためにあるか」という問いは、宗教の本質からいって、問いとして間違っているという。問題なさそうな表現だが、ここにこそ宗教の本質が隠されている。この間違った問いを破るには、「我々自身が何のためにあるか」という問いを立てなければならないと西谷は言う。これは「我々自身が絶対なるもの(人間を超越したもの)に対いし、いかにあるべきか」といい換えてもよい。宗教は基本的に、“人間(相対者)”と、“人間を越えた存在(絶対者)”との関係を基軸にする。そして人間を越えた存在との関わりの中で、現実の人間のあり方に何らかの変化が生じる。この変化は「アイデンティティの変更」であり、私はこれを「自我の相対化」と表現する。こうして人間の生が根底から更新されることで、人生の根本問題が解決され、人生を有意にとらえ直す地平が開ける。ここに宗教の本質があるなら、さきほどの問題は氷解する。「宗教は我々にとって、何のためにあるか」という問いは、その問い自体がすでに“白己中心性”を含んでいる。これは、我々白身を円の中心に置いて宗教を周辺に迫いやり、「宗教が自分にとってプラスかマイナスか」という、功利的な自己中心性を言外に含んだ問いであることを図らずも暴露した問いなのだ。
だが、宗教は円の中心に自我を越えた存在を置き、それによって自我を相対化する。人間は中心から円周に場所を移さなければならない。だから「人間を越えた存在にとって、我々の方がどうあるべきか」が問われなければならない。宗教は自我中心的な人間のあり方を否定し、自我を相対化するので、必ず自分自身の変容を伴う。キリスト教なら中心に位置するのは神(あるいは神の子イエス)であり、その神にたいして我々がどうあるべきかが問われる。一方、神の存在意義を認めない仏教が中心に据えるべきは「法(真理二(この場合の「法」は「法身」としての仏も含まれる)であり、これによって自我を相対化する。
仏教の中でも浄土教では阿弥陀仏が中心に坐り、その阿弥陀仏にとって我々がどうあるべきかが問われる。つまり、自分自身の変容を伴うのが宗教であり、自分がすべての中心に坐り、したがって自分自身の変容を伴わず、かえって自我が肥大化するようなあり方は、宗教とは正反対なのだ。宗教において、我々の存在は絶対なるもの(人間を超越したもの)によって相対化されなければならない。
この他力の概念は、親鸞をもってそのクライマックスを迎える。親鸞はすべてを阿弥陀仏からの一方的な働きかけと理解し、念仏しようという並‥なる心持ちさえも「如来より賜りたる信心」の働きととらえるので、親鸞の説く他力は「絶対他力」と形容される。(以上)