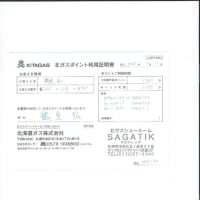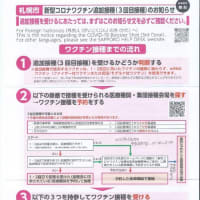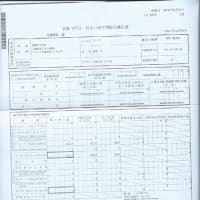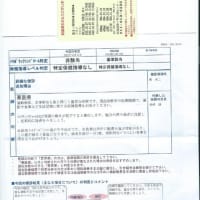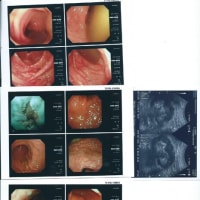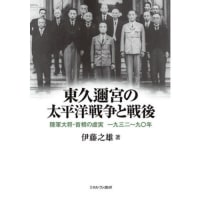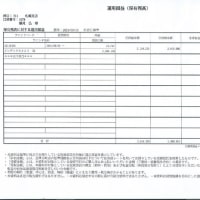今日の日記は、今読んでいるアントニー・ビーヴァー著『ノルマンディー上陸作戦 1944 上・下』(平賀秀明訳・2011年白水社刊)のことです。添付した写真は、その著書(上)の表紙です。
この著書は、10月2日読売新聞朝刊のよみうり書評<書評者:山内昌之(歴史学者・東京大教授)>で紹介されていました。私は、その興味が湧く書評を読んで、この著作をとても読みたくなって、書店で購入し今読んでいます。その著評を以下に引用・掲載します。
『・・激烈な戦い巡る群像・・第二次大戦の欧州戦線を終結に追い込んだのは、連合軍のノルマンディー上陸作戦である。映画「史上最大の作戦」を観ると、この作戦がオマハビーチの上陸を除くと、さほどの苦労もなく行われたような印象を与える。しかし、戦史とノンフィクションが結合したこの力作は、1944年夏の3カ月間のフランス北西部の戦いが東部戦線にも匹敵するほど熾烈なものだったことを改めて実証した。ドイツ側は24万近い将兵が犠牲となり、米軍の死者は約13万、英軍やカナダ軍らの犠牲者はおよそ8万にも上ったのである。本書の凄みは、連合軍とドイツ軍の厖大(ぼうだい)な史料や多彩な証言を基盤にしながら、戦場や戦闘の描写に留まらず、リーダーシップや指導責任の問題にも公平に踏み込んでいることだ。英国人ながら、指揮官としての資質に恵まれた一方で評価の低かった悲劇的な将軍、モントゴメリーのエゴと仲間にさえ嫌われた秘密主義を指摘する。また、チャーチルが「この間違っても決して改めることのない、野心満々の、唾棄すべきアングロ・サクソン恐怖症男」と呼んだ英国亡命中のドゴールの小心さと名誉欲も興味深い。冷静な分析はドイツ側にも向けられる。優秀な将帥でありながら、防衛責任者から解任されヒトラーに自殺を強いられるロンメルやクルーゲの悲劇も克明に描かれる。目立たぬ人物の描写も的確だ。食肉加工の徒弟からナチ党に馳(は)せ参じて武装親衛隊の大将にまでなったゼップ・ディートリッヒは、貴族出身者の多い国防軍の将軍と違って、庶民出のヒーローにまつりあげられた。正直者であっても、性格は粗暴で知性に欠ける野戦司令官という評価も適切である。いずれにせよ、現実的に「すべて計画通り」には進まなかったノルマンディーの戦いを米軍中心の英雄劇でなく、多面的な人間ドラマとして描いた本書の魅力は尽きない。平賀秀明訳。』
私は、書評している山内昌之東大教授が指摘した”映画「史上最大の作戦」ではさほどの苦労もなく行われたが、その後3カ月間のフランス北西部の戦いが熾烈なものだった”に、映画はよく知っていながら、その後の熾烈な戦史をまったく知らない私はとても興味を持ちました。だから、上下あわせて900ページにもなる長編の歴史書ですが、何も迷わず購入しました。
そして、実際読んでみて、著者アントニー・ビーヴァーの冷静な歴史分析にも、私は強く共感しました。私が強く共感したナチス親衛隊と連合軍兵士との比較記述を、本書(下)から、以下に一部引用・掲載します。
『本質的に民主主義国家の市民兵である連合軍兵士と、たとえ一人残らず殺されても、祖国だけは絶対に守るのだと決意する、ナチの教義を叩きこまれた武装親衛隊を単純比較し、あれに劣らぬ自己犠牲の精神を発揮せよと期待することのほうが、そもそも無理なのである。・・負傷し連合軍に拘束された若いナチ党員は、輸血治療するイギリス軍医に「そいつはイギリス人の血か?」と詰問しその輸血を拒み、「私はヒトラー総統のために死ぬのだ!」と高らかに宣言した。』
時代や国が変わっても、この世界には”独善的な教義を信奉する者”は必ず存在するのだと、私はその時強く得心しました。
この著書は、10月2日読売新聞朝刊のよみうり書評<書評者:山内昌之(歴史学者・東京大教授)>で紹介されていました。私は、その興味が湧く書評を読んで、この著作をとても読みたくなって、書店で購入し今読んでいます。その著評を以下に引用・掲載します。
『・・激烈な戦い巡る群像・・第二次大戦の欧州戦線を終結に追い込んだのは、連合軍のノルマンディー上陸作戦である。映画「史上最大の作戦」を観ると、この作戦がオマハビーチの上陸を除くと、さほどの苦労もなく行われたような印象を与える。しかし、戦史とノンフィクションが結合したこの力作は、1944年夏の3カ月間のフランス北西部の戦いが東部戦線にも匹敵するほど熾烈なものだったことを改めて実証した。ドイツ側は24万近い将兵が犠牲となり、米軍の死者は約13万、英軍やカナダ軍らの犠牲者はおよそ8万にも上ったのである。本書の凄みは、連合軍とドイツ軍の厖大(ぼうだい)な史料や多彩な証言を基盤にしながら、戦場や戦闘の描写に留まらず、リーダーシップや指導責任の問題にも公平に踏み込んでいることだ。英国人ながら、指揮官としての資質に恵まれた一方で評価の低かった悲劇的な将軍、モントゴメリーのエゴと仲間にさえ嫌われた秘密主義を指摘する。また、チャーチルが「この間違っても決して改めることのない、野心満々の、唾棄すべきアングロ・サクソン恐怖症男」と呼んだ英国亡命中のドゴールの小心さと名誉欲も興味深い。冷静な分析はドイツ側にも向けられる。優秀な将帥でありながら、防衛責任者から解任されヒトラーに自殺を強いられるロンメルやクルーゲの悲劇も克明に描かれる。目立たぬ人物の描写も的確だ。食肉加工の徒弟からナチ党に馳(は)せ参じて武装親衛隊の大将にまでなったゼップ・ディートリッヒは、貴族出身者の多い国防軍の将軍と違って、庶民出のヒーローにまつりあげられた。正直者であっても、性格は粗暴で知性に欠ける野戦司令官という評価も適切である。いずれにせよ、現実的に「すべて計画通り」には進まなかったノルマンディーの戦いを米軍中心の英雄劇でなく、多面的な人間ドラマとして描いた本書の魅力は尽きない。平賀秀明訳。』
私は、書評している山内昌之東大教授が指摘した”映画「史上最大の作戦」ではさほどの苦労もなく行われたが、その後3カ月間のフランス北西部の戦いが熾烈なものだった”に、映画はよく知っていながら、その後の熾烈な戦史をまったく知らない私はとても興味を持ちました。だから、上下あわせて900ページにもなる長編の歴史書ですが、何も迷わず購入しました。
そして、実際読んでみて、著者アントニー・ビーヴァーの冷静な歴史分析にも、私は強く共感しました。私が強く共感したナチス親衛隊と連合軍兵士との比較記述を、本書(下)から、以下に一部引用・掲載します。
『本質的に民主主義国家の市民兵である連合軍兵士と、たとえ一人残らず殺されても、祖国だけは絶対に守るのだと決意する、ナチの教義を叩きこまれた武装親衛隊を単純比較し、あれに劣らぬ自己犠牲の精神を発揮せよと期待することのほうが、そもそも無理なのである。・・負傷し連合軍に拘束された若いナチ党員は、輸血治療するイギリス軍医に「そいつはイギリス人の血か?」と詰問しその輸血を拒み、「私はヒトラー総統のために死ぬのだ!」と高らかに宣言した。』
時代や国が変わっても、この世界には”独善的な教義を信奉する者”は必ず存在するのだと、私はその時強く得心しました。