Twにて、イマジズムの詩というタグ付けで詩を発信していますと、時々、ご質問を受けることがあります。個別にお答えすることが度々ありますが、noteに書いておこうと思いました。
あくまでも、私の興味が座標軸となる詩史の大まかなまとめと雑感です。学生の頃と違って、資料が手元にないので、論考ではなく、お茶飲みながらの雑談だと思って、、どうぞお読みください。
日本の詩は、短歌、俳諧(俳句)、自由詩に大別されます。
“自由詩“はいかなる形からも解放され、言葉の文学として、新しく生まれ歩き出したのだと思います。
明治の「言文一致運動」。自由詩にとっても言葉の獲得の歴史です。
自由詩の始まりは訳詩からでした。上田敏の「海潮音」は記念碑です。島崎藤村が賛美歌の訳者の詩を転用したり、自由な言葉を詩に取り込み、口語詩への道を歩き始めました。
三木露風や北原白秋等の「象徴詩」の時代があり、その後、萩原朔太郎が「口語自由詩」を確立します。現代の詩の祖と言えると思います。
朔太郎からは、西脇順三郎(モダニズムの流れへ)と三好達治(叙情派四季派の流れへ)が分かれて行くと考えています。
当時イギリスから戻った西脇順三郎は、モダニズムを持ち帰りました。昭和初期の日本のモダニズム運動を進める春山行夫らの若い詩人たちに大歓迎されます。
またイマジズムの詩人としての業績は、なんと言っても北園克衛でしょうか。エズラ・パウンドとの交友も有名です。
瀧口修造の活躍もあり、昭和初頭から戦前が、詩のモダニズム全盛の頃でした。
シュールレアリスム、ダダ(高橋新吉)…。外国のモダニズムの芸術運動が、昭和初期、日本の詩人たちに大きな影響をもたらしました。
しかし残念なことに、戦争の時代に入り、日本の詩から、モダニズムは姿を消します。
文学者、詩人も、転向を余儀なくされ、戦争加担詩か、沈黙か、皆作風が変わります。
そして、「歴程」(草野心平 渋沢孝輔 吉原幸子ら)は戦前戦後と続きましたが、終戦後は、「列島」(関根弘、長谷川龍生ら)や「荒地」(鮎川信夫 田村隆一 三好豊一郎 黒田三郎)から、さらに重要な詩人たちが出ています。
“荒地“、この誌名はもちろんT.Sエリオットの「荒地」からとっています。敗戦後の荒涼とした場所から立ち上がっていく、そんな詩の出発に見立てたのだと言われています。
尚、戦前の叙情派四季派(三好達治 立原道造ら)からは、戦後「櫂」が生まれ、谷川俊太郎、茨木のりこ、大岡信らの多数の重要な詩人が今に続きました。
大きく分けて、戦前の以下の流れは→右の戦後詩のように位置づけられています。(他にももちろんありますが。)
・モダニズム詩 → 「荒地」グループ
・プロレタリア詩 → 「列島」グループ
・四季派の叙情詩三好達治 →「櫂」グループ
非常に主要な詩の大雑把な流れです。この他にも重要な詩誌のグループや著名な詩人はたくさんいます。
そして、60年代以降の現代詩の難解な方面への移行。それは詩にとっての経験であったと思います。ただ、民衆の気持ちからは離れて行きます。
今でも、好きな日本の詩人は誰ですか?という質問に、宮沢賢治や中原中也や金子みすゞと言われることに抵抗があります。
彼らが優れた詩人であることは間違いありません。ただ、今を生きている詩人ではないのです。彼らが今を生きていたら、もっと鮮烈な言葉を私たちに共有してくれたかもしれません。時代の言葉として、ヒップホップだったかもしれないし、リーディングや音楽だったかもしれない。
好きな詩人の質問に、谷川俊太郎さんの名前が出てくることで、少しホッとしますが、ただ現実は、谷川さんさえ知らない一般の方も多いのです。
人が心に享受し共有していく言葉、というシンプルに詩が担うべき役割を、現代詩は放棄してきた一面があると思います。その代わり日本人は“歌“を共有財産に持ったのだと思っています。
ユーミン、陽水、サザン、ドリカム等々の歌の言葉を、日本人は自分の時間に取り込んでいったように思います。
現代詩の歴史を細かく書き出すと、どんどん長くなってしまうので、ダイジェストで途中に致しますが。
ところで、私が今関わっている日本の自由詩というのは、このような歴史があることからも言えるかと思うのですが、西洋のあり方とは少し違うのかなと思っております。
あえて冒険的な言葉を使ってしまうなら、言語や固有の思想を、形としては、踏襲しない文学形式。これが日本の今までの現代詩の歩みであるとも思うのです。
ただ、見えない部分の踏襲があるとすれば、
それは唯一、私は日本の詩歌の伝統に(それは歌謡曲まで)続いているものは、“もののあわれ感“だと思っています。
四季の移ろいの中で、海に囲まれた島国で培われた情趣、哲学と言ってもいいのだと思いますが。
西脇順三郎は、それを永遠という言葉で捉えました。永遠ではない人間の、永遠への思慕です。淋しさが漂いますが、それは硬質の叙情に歌うことで、至上の美に変わるものですね。
日本人である、そこに立って、言葉を発して行く時に、もののあわれの意識、それはある時は無常であるが、決してなくなるものでないという、宇宙的な禅的な視点を合わせて、俯瞰していく立ち位置。静かにそこの地下水脈に届いていれば、日本の詩歌の水脈に続いていられるように感じます。
ところで、最初に戻りますが。
私が、現在使う“イマジズムの詩“という意味ですが。
私の思うかつての北園克衛のイマジズムの詩は、実験的で前衛の騎手でした。どこまでも芸術的で、硬質の叙情が光っていたと思います。奇抜な言葉や形式の新しさへの追求があり、素晴らしい詩の仕事だったと思います。
私がイマジズムの詩を、と使う時、この北園克衛の仕事が頭の隅に浮かびますが、モダニズムのイマジズムを踏襲するものではないです。言葉に絵画的でビジュアル性があって、硬質の叙情を目指しますが、形式主義にならない、新しい詩でありたいと思う立場なのです。
それにしても、失われた時代ですが、私には戦前のモダニズム全盛の頃が、詩のひとつの憧れの時代でもあります。
ありがとうございます。応援してネ♪
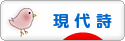 にほんブログ村
にほんブログ村
あくまでも、私の興味が座標軸となる詩史の大まかなまとめと雑感です。学生の頃と違って、資料が手元にないので、論考ではなく、お茶飲みながらの雑談だと思って、、どうぞお読みください。
日本の詩は、短歌、俳諧(俳句)、自由詩に大別されます。
“自由詩“はいかなる形からも解放され、言葉の文学として、新しく生まれ歩き出したのだと思います。
明治の「言文一致運動」。自由詩にとっても言葉の獲得の歴史です。
自由詩の始まりは訳詩からでした。上田敏の「海潮音」は記念碑です。島崎藤村が賛美歌の訳者の詩を転用したり、自由な言葉を詩に取り込み、口語詩への道を歩き始めました。
三木露風や北原白秋等の「象徴詩」の時代があり、その後、萩原朔太郎が「口語自由詩」を確立します。現代の詩の祖と言えると思います。
朔太郎からは、西脇順三郎(モダニズムの流れへ)と三好達治(叙情派四季派の流れへ)が分かれて行くと考えています。
当時イギリスから戻った西脇順三郎は、モダニズムを持ち帰りました。昭和初期の日本のモダニズム運動を進める春山行夫らの若い詩人たちに大歓迎されます。
またイマジズムの詩人としての業績は、なんと言っても北園克衛でしょうか。エズラ・パウンドとの交友も有名です。
瀧口修造の活躍もあり、昭和初頭から戦前が、詩のモダニズム全盛の頃でした。
シュールレアリスム、ダダ(高橋新吉)…。外国のモダニズムの芸術運動が、昭和初期、日本の詩人たちに大きな影響をもたらしました。
しかし残念なことに、戦争の時代に入り、日本の詩から、モダニズムは姿を消します。
文学者、詩人も、転向を余儀なくされ、戦争加担詩か、沈黙か、皆作風が変わります。
そして、「歴程」(草野心平 渋沢孝輔 吉原幸子ら)は戦前戦後と続きましたが、終戦後は、「列島」(関根弘、長谷川龍生ら)や「荒地」(鮎川信夫 田村隆一 三好豊一郎 黒田三郎)から、さらに重要な詩人たちが出ています。
“荒地“、この誌名はもちろんT.Sエリオットの「荒地」からとっています。敗戦後の荒涼とした場所から立ち上がっていく、そんな詩の出発に見立てたのだと言われています。
尚、戦前の叙情派四季派(三好達治 立原道造ら)からは、戦後「櫂」が生まれ、谷川俊太郎、茨木のりこ、大岡信らの多数の重要な詩人が今に続きました。
大きく分けて、戦前の以下の流れは→右の戦後詩のように位置づけられています。(他にももちろんありますが。)
・モダニズム詩 → 「荒地」グループ
・プロレタリア詩 → 「列島」グループ
・四季派の叙情詩三好達治 →「櫂」グループ
非常に主要な詩の大雑把な流れです。この他にも重要な詩誌のグループや著名な詩人はたくさんいます。
そして、60年代以降の現代詩の難解な方面への移行。それは詩にとっての経験であったと思います。ただ、民衆の気持ちからは離れて行きます。
今でも、好きな日本の詩人は誰ですか?という質問に、宮沢賢治や中原中也や金子みすゞと言われることに抵抗があります。
彼らが優れた詩人であることは間違いありません。ただ、今を生きている詩人ではないのです。彼らが今を生きていたら、もっと鮮烈な言葉を私たちに共有してくれたかもしれません。時代の言葉として、ヒップホップだったかもしれないし、リーディングや音楽だったかもしれない。
好きな詩人の質問に、谷川俊太郎さんの名前が出てくることで、少しホッとしますが、ただ現実は、谷川さんさえ知らない一般の方も多いのです。
人が心に享受し共有していく言葉、というシンプルに詩が担うべき役割を、現代詩は放棄してきた一面があると思います。その代わり日本人は“歌“を共有財産に持ったのだと思っています。
ユーミン、陽水、サザン、ドリカム等々の歌の言葉を、日本人は自分の時間に取り込んでいったように思います。
現代詩の歴史を細かく書き出すと、どんどん長くなってしまうので、ダイジェストで途中に致しますが。
ところで、私が今関わっている日本の自由詩というのは、このような歴史があることからも言えるかと思うのですが、西洋のあり方とは少し違うのかなと思っております。
あえて冒険的な言葉を使ってしまうなら、言語や固有の思想を、形としては、踏襲しない文学形式。これが日本の今までの現代詩の歩みであるとも思うのです。
ただ、見えない部分の踏襲があるとすれば、
それは唯一、私は日本の詩歌の伝統に(それは歌謡曲まで)続いているものは、“もののあわれ感“だと思っています。
四季の移ろいの中で、海に囲まれた島国で培われた情趣、哲学と言ってもいいのだと思いますが。
西脇順三郎は、それを永遠という言葉で捉えました。永遠ではない人間の、永遠への思慕です。淋しさが漂いますが、それは硬質の叙情に歌うことで、至上の美に変わるものですね。
日本人である、そこに立って、言葉を発して行く時に、もののあわれの意識、それはある時は無常であるが、決してなくなるものでないという、宇宙的な禅的な視点を合わせて、俯瞰していく立ち位置。静かにそこの地下水脈に届いていれば、日本の詩歌の水脈に続いていられるように感じます。
ところで、最初に戻りますが。
私が、現在使う“イマジズムの詩“という意味ですが。
私の思うかつての北園克衛のイマジズムの詩は、実験的で前衛の騎手でした。どこまでも芸術的で、硬質の叙情が光っていたと思います。奇抜な言葉や形式の新しさへの追求があり、素晴らしい詩の仕事だったと思います。
私がイマジズムの詩を、と使う時、この北園克衛の仕事が頭の隅に浮かびますが、モダニズムのイマジズムを踏襲するものではないです。言葉に絵画的でビジュアル性があって、硬質の叙情を目指しますが、形式主義にならない、新しい詩でありたいと思う立場なのです。
それにしても、失われた時代ですが、私には戦前のモダニズム全盛の頃が、詩のひとつの憧れの時代でもあります。
ありがとうございます。応援してネ♪









