とぐろ巻くヘビをまえに
牙むく動物をまえに
子供を守るために
自分の体を投げ出す
母とは そういうもの
本当は
女も男も
大切ないのちを愛して
そんな覚悟をもって生きている
誰もが
(そうやって)
守られて育った子供
忘れないで
大人になった全ての人よ
人は 誰かを大切にする時間を
生き続けるのだと
気がつくことができたら
いのちを得たお礼に
美しい詩の一行を
そこに置いて行きなさい
誰もが触れることのできる
美しい一行の流れを
大きな河の流れのなかに
ひとしずくの輝きをふやして
立ち去っていく
次の人へ また次の人へ
この美しいペイズリーは
胎児のように 宇宙の時間に
つながっていく
ありがとうございます。応援してネ♪
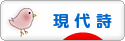
にほんブログ村
牙むく動物をまえに
子供を守るために
自分の体を投げ出す
母とは そういうもの
本当は
女も男も
大切ないのちを愛して
そんな覚悟をもって生きている
誰もが
(そうやって)
守られて育った子供
忘れないで
大人になった全ての人よ
人は 誰かを大切にする時間を
生き続けるのだと
気がつくことができたら
いのちを得たお礼に
美しい詩の一行を
そこに置いて行きなさい
誰もが触れることのできる
美しい一行の流れを
大きな河の流れのなかに
ひとしずくの輝きをふやして
立ち去っていく
次の人へ また次の人へ
この美しいペイズリーは
胎児のように 宇宙の時間に
つながっていく
ありがとうございます。応援してネ♪
にほんブログ村













