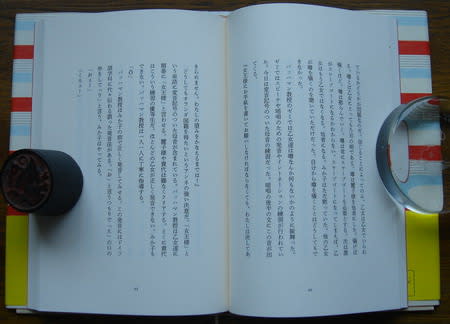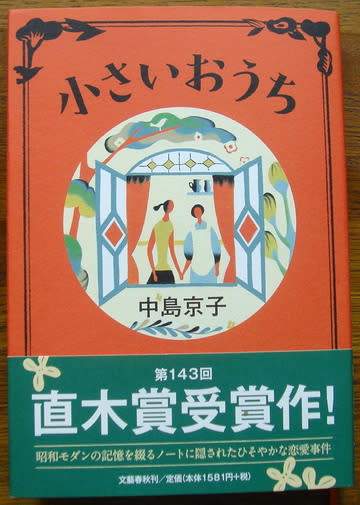一昨日、外出した折りに「吉野家」の前を通りかかったら牛丼270円のビラが目に入った。また安売り合戦の始まり?と思ったら案の定、昨日の朝日朝刊に次のような記事が出ていた。

これを見ると牛丼並盛りが通常は「吉野家」380円、「すき家」280円、「松屋」320円ということになる。私はこれまで「吉野家」と「すき家」では食べたことがあるが、いずれもそれなりに美味しくて、食べるとしたら店の選り好みはせずに先に目に入った方に入ることだろうと思う。「松屋」は未体験ゾーンであるが同じようなものだろう。ただ私が「吉野家」や「すき家」を利用するのは年に数えるほどしかないので、店の特徴とか味に好みがあるわけでもなく、要は空腹を満たせば良いのである。
そういう立場で「牛丼バトル」を見ると、なんだか無駄をしているような気がする。吉野屋にしても値下げの期間は客足も増えるかもしれないが、それがある程度の利益を産むにせよ、通常の値段に戻るとまた元の売れ行きに戻るのではなかろうか。私もかなり前に「吉野家」が一時値下げした時にミーハーよろしく、わざわざ車で近くに店に出かけてテイクアウトを持って帰ったことがあったが、そういうことを経験すると、次の値下げサービスまで待とうという気になってしまう。
私は「吉野家」の380円が高いとは思わない。270円に一時的にせよ値下げが出来るなら、350円ぐらいにしていつも変わらないサービスを続けた方が逆に安堵感があって、リピーターをがっちりと確保出来るのではなかろうか。今回の値下げ合戦でも、後発二社が「吉野家」と同じく270円に値段を統一して売れ行きを競うのであれば、自ずと客筋の特徴が見えてきて面白いと思うのに、低価格が売り物で客足を引こうとするのはどうも低次元での争いに見える。新聞記事では『企業側は生き残りをかけた「体力勝負」』なんて嗾けているようだが、お互いがそれぞれの特徴を出してそれを好む客層をそれぞれ引き寄せ、共存共栄を図ったらいいのに、と思ってしまう。安値だけに釣られる消費者を相手にするのではなくて、この出来ならこれぐらいは払って当たり前、と思う顧客を引きつける努力を重ねるのが商売の本道ではなかろうか。納得のいく金額なら払うつもりでいる消費者にただ安値を押し付けることは、消費者の人格を軽く見ているような気さえする。
ところで先ほど、少しサイズの合わないTシャツを着ている妻が目に入った。不審そうな視線を感じたのか「安い出物があったので買ったの。いくらだと思う?」と「上手な買い物をしたのよ」と誇らんばかりの口調で聞いてきた。思い知らせてやれとばかり「200円」と声をかけるとなんと「すごい、当たり!」と拍手が戻ってきた。ああ、やんぬるかな!

これを見ると牛丼並盛りが通常は「吉野家」380円、「すき家」280円、「松屋」320円ということになる。私はこれまで「吉野家」と「すき家」では食べたことがあるが、いずれもそれなりに美味しくて、食べるとしたら店の選り好みはせずに先に目に入った方に入ることだろうと思う。「松屋」は未体験ゾーンであるが同じようなものだろう。ただ私が「吉野家」や「すき家」を利用するのは年に数えるほどしかないので、店の特徴とか味に好みがあるわけでもなく、要は空腹を満たせば良いのである。
そういう立場で「牛丼バトル」を見ると、なんだか無駄をしているような気がする。吉野屋にしても値下げの期間は客足も増えるかもしれないが、それがある程度の利益を産むにせよ、通常の値段に戻るとまた元の売れ行きに戻るのではなかろうか。私もかなり前に「吉野家」が一時値下げした時にミーハーよろしく、わざわざ車で近くに店に出かけてテイクアウトを持って帰ったことがあったが、そういうことを経験すると、次の値下げサービスまで待とうという気になってしまう。
私は「吉野家」の380円が高いとは思わない。270円に一時的にせよ値下げが出来るなら、350円ぐらいにしていつも変わらないサービスを続けた方が逆に安堵感があって、リピーターをがっちりと確保出来るのではなかろうか。今回の値下げ合戦でも、後発二社が「吉野家」と同じく270円に値段を統一して売れ行きを競うのであれば、自ずと客筋の特徴が見えてきて面白いと思うのに、低価格が売り物で客足を引こうとするのはどうも低次元での争いに見える。新聞記事では『企業側は生き残りをかけた「体力勝負」』なんて嗾けているようだが、お互いがそれぞれの特徴を出してそれを好む客層をそれぞれ引き寄せ、共存共栄を図ったらいいのに、と思ってしまう。安値だけに釣られる消費者を相手にするのではなくて、この出来ならこれぐらいは払って当たり前、と思う顧客を引きつける努力を重ねるのが商売の本道ではなかろうか。納得のいく金額なら払うつもりでいる消費者にただ安値を押し付けることは、消費者の人格を軽く見ているような気さえする。
ところで先ほど、少しサイズの合わないTシャツを着ている妻が目に入った。不審そうな視線を感じたのか「安い出物があったので買ったの。いくらだと思う?」と「上手な買い物をしたのよ」と誇らんばかりの口調で聞いてきた。思い知らせてやれとばかり「200円」と声をかけるとなんと「すごい、当たり!」と拍手が戻ってきた。ああ、やんぬるかな!