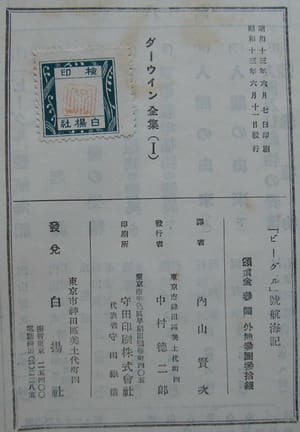平成9年7月16日に成立した「臓器の移植に関する法律」の附則に次のような条文がある。
この第一項の定めを受けて臓器移植法の改正A案が去る6月18日に衆議院を通過し、目下参議院で審議が始まっている。この「臓器移植法改正A案」を現行法と比較すると次のようになる(産経新聞より)。

現行法では臓器移植を前提にした場合のみ脳死が人の死と定義づけられるのに反して、改正A案では脳死が一般的に人の死となり、死の定義が大きく変わる。というのも改正A案はとにもかくにも臓器移植をより推進するために使える臓器の供給量を増やすことが狙いで、そのためには死の定義をこのように変える方が都合がよいからであろう。しかしこれが国民的合意の上に立った法改正の方向とは私には思えない。なぜか、を説明する。
上記の附則にある「この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加え」の部分に注目して、まず「この法律の施行の状況を勘案」してみよう。ちなみに【勘案】とは「諸般の事情を十分に考え合わせ、適切な処置をすること」(新明解国語辞典第五版)なのである。まず法律の施行の状況であるが、端的にいえば臓器移植法が施行されたことで脳死による臓器移植が何件行われたかがそれに当たる。そこで国内移植年表を見ると、平成9(1997)年10月にこの法律が施行されてから初めて脳死ドナーからの臓器移植がなされたのは平成11年2月で、今年平成21年2月で81例に達していることが分かる。これが現時点における法律の施行の状況なのである。次にこれを勘案することにする。
河野太郎衆議院議員が平成17年10月に「なぜ臓器移植法の改正が必要なのか」と意見を述べているが、そのなかで「現行の臓器移植法の問題-2 * 我が国では、移植を必要としている待機患者数に対して、脳死からの臓器提供の数が圧倒的に足りない。」とその考えをはっきりと打ち出している。河野太郎議員はよく知られているように生体肝移植のドナーという個人的体験をお持ちなので、臓器移植の有効性に間違いなく確信を抱いており、だからこそ臓器提供数をとにかく増やすために法改正をしたいという発想が素直に出てくるのであろう。すなわち河野議員にしてみると、平成9年10月から平成21年2月までの81例という「この法律の施行の状況」ではあまりにも移植に使える臓器の数が少なすぎて、だからこそ例数を増やすための法改正をすべきであると勘案されたのであろう。
臓器移植法の附則は、「この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案」することにもともとなっているので、施行後三年の平成12年10月までに何例あったかをみてみるとわずか8例に過ぎない。確かに8例は少なすぎる。だからこそ積極的な判断を下せなくて改正作業が今日まで延引せざるを得なくなったと見ることができようが、それはともかく、10年あまり経た現時点でもまだ81例に過ぎない。河野議員の立場に立てば、だからこそ件数を増やすために法改正が必要との発想になるのであるが、10年あまりに81例という法律の施行の状況に、河野議員とは異なった視点で私は判断を下すのである。
10年あまりに81例を実効という立場から見ればどうなるのか。まさに焼け石に水で例数が少なすぎる。その点では河野議員と見解を同じくするかと思う。どの程度に焼け石に水なのか、たとえば心臓移植数をアメリカでみると、1990年以降では例年2000件を超え、年平均2200件ほどになる。一方日本では、2001年から2008年までの8年間に67件で年平均8件強(2009年5月までの総数は81件)で、アメリカでの200分の1以下にすぎない。これが何を表すのかはきわめて明白で、いくら法律が出来ても、脳死による臓器移植が現実には日本国民により支持されていないのである。ちなみにわが国におけるこの同期間での心停止後の心臓移植は667件で、脳死移植の約10倍であるが、両者を合わせても年平均92件に過ぎない。
今、麻生内閣、自民党の支持率が低迷している。麻生内閣、自民党の支持者なら低い支持率を上げるための手段を必死に講じるだろうが、民主党を始めとする野党は低い支持率こそ国民の意志の現れであるとして麻生内閣、自民党に下野を迫っている。これと同じように、臓器移植推進派の河野議員は10年あまりに81例があまりにも少なすぎるので、法改正により例数の増加を図ろうとするが、合理的思考をならいとする私は10年あまりに81例は、脳死臓器移植が国民に支持されていない結果と見るのである。この視点が臓器移植法改正案を審議する国会議員に欠けていたように私は思う。この法律の施行の状況を勘案した結果、臓器移植法改正の必要なしとの判断があってもよかったのである。
私は現行の臓器移植法に一定の評価を与えているので、現行のままでよいと思っている。それが「臓器移植法改正A案」となると、この案が大きな問題点を抱えているので反対せざるを得なくなる。
「さるの生肝」という説話がある。私も子供の頃何かの本で読んだ覚えがあるが、すでに今昔物語集にもでているとのことで、日本国語大辞典(小学館、初版)は次のように説明している。
もともと自分の身体は自分のものである。法律なんてものが顔を出してくる遙か大昔から、人類が地球上に出現した時からそういう定めになっている。いや、上の説話にでてくる猿でも心得ている自然のことわりである。この説話のように、持ち主がもともとはっきりしている臓器をかすめ取るには騙すしか手がないのである。そう思ってみると「臓器移植法改正A案」に騙しのテクニックが巧妙に持ち込まれていると私の目に映った。臓器提供は「本人が拒否していなければ家族の同意で可能」と言っている強調の部分がそうである。わざわざ本人が拒否するまでもなく、自分の身体は自分のもので、誰一人として他人が自分の身体の一部をそもそも持ち出す権利などあるはずがない。本人が拒否していなければと、あたかも本人の意志を尊重するかのような言い回しで、自分の身体は自分のものという自然のことわりを包み隠しているのである。
現行法では本人が自分の臓器を移植術に使用されるために提供する意志を書面にて表示している場合がある。いわゆる「ドナーカード」であるが、元来自分のものである身体の一部をある条件下で移植に提供するとの意志を表明したもので、この流れは素直に理解できる。ところが「臓器移植法改正A案」では自分が「拒否カード」のようなもので、わざわざ臓器の提供に応じないとの意思表示をしない限り、家族の同意さえあれば臓器が持ち去られてしまうのである。「ドナーカード」であれば元来自分のものである身体の一部を、もしお役に立つのならお使いください、と自分の意志で提供を認めるもので、何か人の役に立ちたいと言うモーティベーションにも素直にかなうものである。それが「臓器移植法改正A案」では、わざわざ提供するなんて云って貰わなくても家族さえ説得できれば臓器は貰えるのだから、と、人の善意を不当に貶めることになってしまう。
自分の身体は自分のもの、たとえ家族といえども太古からの自然のことわりを侵す権利はないのである。われわれは自分の臓器が他人に取られることをわざわざ拒否しなければならないという発想自体が自然のことわりを犯していることを心に銘記すべきなのである。自分の身体は誰のものでもない、文字どおり自分のものである。その自然のことわりを破壊する権利が国会議員なんぞにあるはずがない。参議院での審議が始まったにせよ、「臓器移植法改正A案」が否決されることを、それこそ『良識の府参議院』に期待する。
あらためて繰り返すが、私は現行の臓器移植法は「自分の身体は自分のもの」という基本理念の上に立っている妥当なものだと思っているので、この法の理念の下に行われる臓器移植は容認するというのが私の立場である。
(検討等)
第二条 この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
2 政府は、ドナーカードの普及及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 (省略)
第二条 この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
2 政府は、ドナーカードの普及及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 (省略)
この第一項の定めを受けて臓器移植法の改正A案が去る6月18日に衆議院を通過し、目下参議院で審議が始まっている。この「臓器移植法改正A案」を現行法と比較すると次のようになる(産経新聞より)。

現行法では臓器移植を前提にした場合のみ脳死が人の死と定義づけられるのに反して、改正A案では脳死が一般的に人の死となり、死の定義が大きく変わる。というのも改正A案はとにもかくにも臓器移植をより推進するために使える臓器の供給量を増やすことが狙いで、そのためには死の定義をこのように変える方が都合がよいからであろう。しかしこれが国民的合意の上に立った法改正の方向とは私には思えない。なぜか、を説明する。
上記の附則にある「この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加え」の部分に注目して、まず「この法律の施行の状況を勘案」してみよう。ちなみに【勘案】とは「諸般の事情を十分に考え合わせ、適切な処置をすること」(新明解国語辞典第五版)なのである。まず法律の施行の状況であるが、端的にいえば臓器移植法が施行されたことで脳死による臓器移植が何件行われたかがそれに当たる。そこで国内移植年表を見ると、平成9(1997)年10月にこの法律が施行されてから初めて脳死ドナーからの臓器移植がなされたのは平成11年2月で、今年平成21年2月で81例に達していることが分かる。これが現時点における法律の施行の状況なのである。次にこれを勘案することにする。
河野太郎衆議院議員が平成17年10月に「なぜ臓器移植法の改正が必要なのか」と意見を述べているが、そのなかで「現行の臓器移植法の問題-2 * 我が国では、移植を必要としている待機患者数に対して、脳死からの臓器提供の数が圧倒的に足りない。」とその考えをはっきりと打ち出している。河野太郎議員はよく知られているように生体肝移植のドナーという個人的体験をお持ちなので、臓器移植の有効性に間違いなく確信を抱いており、だからこそ臓器提供数をとにかく増やすために法改正をしたいという発想が素直に出てくるのであろう。すなわち河野議員にしてみると、平成9年10月から平成21年2月までの81例という「この法律の施行の状況」ではあまりにも移植に使える臓器の数が少なすぎて、だからこそ例数を増やすための法改正をすべきであると勘案されたのであろう。
臓器移植法の附則は、「この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案」することにもともとなっているので、施行後三年の平成12年10月までに何例あったかをみてみるとわずか8例に過ぎない。確かに8例は少なすぎる。だからこそ積極的な判断を下せなくて改正作業が今日まで延引せざるを得なくなったと見ることができようが、それはともかく、10年あまり経た現時点でもまだ81例に過ぎない。河野議員の立場に立てば、だからこそ件数を増やすために法改正が必要との発想になるのであるが、10年あまりに81例という法律の施行の状況に、河野議員とは異なった視点で私は判断を下すのである。
10年あまりに81例を実効という立場から見ればどうなるのか。まさに焼け石に水で例数が少なすぎる。その点では河野議員と見解を同じくするかと思う。どの程度に焼け石に水なのか、たとえば心臓移植数をアメリカでみると、1990年以降では例年2000件を超え、年平均2200件ほどになる。一方日本では、2001年から2008年までの8年間に67件で年平均8件強(2009年5月までの総数は81件)で、アメリカでの200分の1以下にすぎない。これが何を表すのかはきわめて明白で、いくら法律が出来ても、脳死による臓器移植が現実には日本国民により支持されていないのである。ちなみにわが国におけるこの同期間での心停止後の心臓移植は667件で、脳死移植の約10倍であるが、両者を合わせても年平均92件に過ぎない。
今、麻生内閣、自民党の支持率が低迷している。麻生内閣、自民党の支持者なら低い支持率を上げるための手段を必死に講じるだろうが、民主党を始めとする野党は低い支持率こそ国民の意志の現れであるとして麻生内閣、自民党に下野を迫っている。これと同じように、臓器移植推進派の河野議員は10年あまりに81例があまりにも少なすぎるので、法改正により例数の増加を図ろうとするが、合理的思考をならいとする私は10年あまりに81例は、脳死臓器移植が国民に支持されていない結果と見るのである。この視点が臓器移植法改正案を審議する国会議員に欠けていたように私は思う。この法律の施行の状況を勘案した結果、臓器移植法改正の必要なしとの判断があってもよかったのである。
私は現行の臓器移植法に一定の評価を与えているので、現行のままでよいと思っている。それが「臓器移植法改正A案」となると、この案が大きな問題点を抱えているので反対せざるを得なくなる。
「さるの生肝」という説話がある。私も子供の頃何かの本で読んだ覚えがあるが、すでに今昔物語集にもでているとのことで、日本国語大辞典(小学館、初版)は次のように説明している。
さるの生肝(いきぎも) (生きた猿から取り出した肝の意で)世界的に流布している説話の一つ。病気をなおす妙薬といわれる猿の生き肝を取りに竜王からつかわされた水母(くらげ)が、猿をだまして連れて帰る途中、その目的をもらしたために、「生き肝を忘れてきた」と猿にだまされて逃げられてしまい、その罰として打たれたため、それ以後水母には骨がなくなってしまったという内容のもの。
もともと自分の身体は自分のものである。法律なんてものが顔を出してくる遙か大昔から、人類が地球上に出現した時からそういう定めになっている。いや、上の説話にでてくる猿でも心得ている自然のことわりである。この説話のように、持ち主がもともとはっきりしている臓器をかすめ取るには騙すしか手がないのである。そう思ってみると「臓器移植法改正A案」に騙しのテクニックが巧妙に持ち込まれていると私の目に映った。臓器提供は「本人が拒否していなければ家族の同意で可能」と言っている強調の部分がそうである。わざわざ本人が拒否するまでもなく、自分の身体は自分のもので、誰一人として他人が自分の身体の一部をそもそも持ち出す権利などあるはずがない。本人が拒否していなければと、あたかも本人の意志を尊重するかのような言い回しで、自分の身体は自分のものという自然のことわりを包み隠しているのである。
現行法では本人が自分の臓器を移植術に使用されるために提供する意志を書面にて表示している場合がある。いわゆる「ドナーカード」であるが、元来自分のものである身体の一部をある条件下で移植に提供するとの意志を表明したもので、この流れは素直に理解できる。ところが「臓器移植法改正A案」では自分が「拒否カード」のようなもので、わざわざ臓器の提供に応じないとの意思表示をしない限り、家族の同意さえあれば臓器が持ち去られてしまうのである。「ドナーカード」であれば元来自分のものである身体の一部を、もしお役に立つのならお使いください、と自分の意志で提供を認めるもので、何か人の役に立ちたいと言うモーティベーションにも素直にかなうものである。それが「臓器移植法改正A案」では、わざわざ提供するなんて云って貰わなくても家族さえ説得できれば臓器は貰えるのだから、と、人の善意を不当に貶めることになってしまう。
自分の身体は自分のもの、たとえ家族といえども太古からの自然のことわりを侵す権利はないのである。われわれは自分の臓器が他人に取られることをわざわざ拒否しなければならないという発想自体が自然のことわりを犯していることを心に銘記すべきなのである。自分の身体は誰のものでもない、文字どおり自分のものである。その自然のことわりを破壊する権利が国会議員なんぞにあるはずがない。参議院での審議が始まったにせよ、「臓器移植法改正A案」が否決されることを、それこそ『良識の府参議院』に期待する。
あらためて繰り返すが、私は現行の臓器移植法は「自分の身体は自分のもの」という基本理念の上に立っている妥当なものだと思っているので、この法の理念の下に行われる臓器移植は容認するというのが私の立場である。