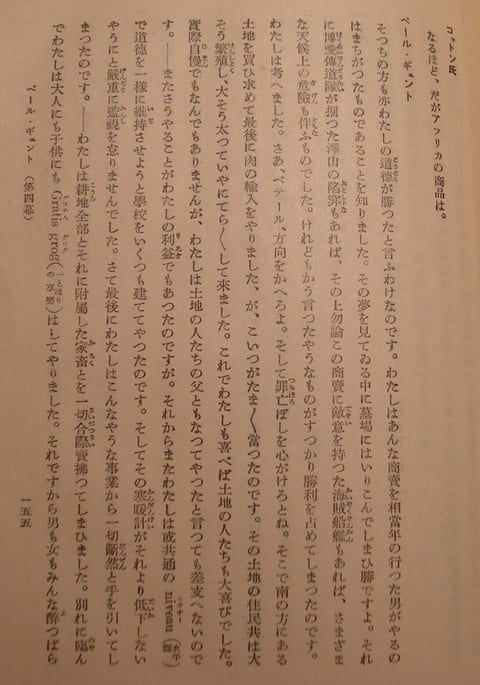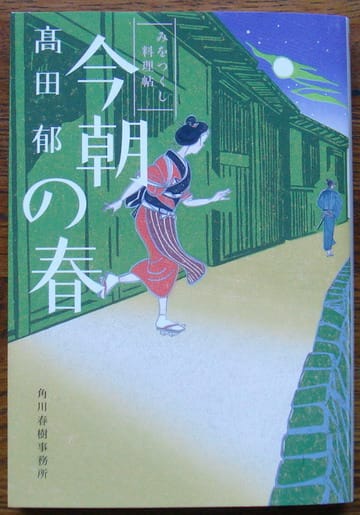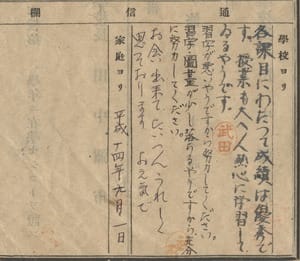昭和20年11月の末、朝鮮から引き揚げて来て落ち着いたのが兵庫県高砂市にある鐘紡社宅であった。台所の土間には竈があり、水道は家にあったのかもしれないが、屋外の共同井戸から水を汲んできた覚えがある。部屋は二畳、四畳半、六畳の三間でトイレはかろうじて付いていた。いわゆる工員住宅であった。そこに親子六人が住んでいたが、父は大阪の本部に単身赴任で、時々週末には帰ってきた。通勤できる様な交通事情ではなかったのである。
戦後間も無い頃で停電が日常茶飯事であった。予告なしに電気が消える、そのためにろうそくが用意されていた。停電の原因はもう一つあった。電気の使いすぎでヒューズがよくとぶのである。それを修理するのは私の役目であった。ヒューズ箱を開けて切れたヒューズをとりかえるのである。ヒューズと言っても細い鉛のハンダ糸のようなもので、容量は5アンペアはあっただろうか。その頃一般家庭でニクロム線の電熱器がよく使われていた。わが家ではせいぜい頂き物のおかきを焼いたりカラメル焼きを作るぐらいだった。時には小さなやかんでお湯を沸かした。いちいち七輪をおこすわけにはいかなかったからである。この電熱器の容量はどれくらいだったのだろう。大きくても2、3百ワットではなかっただろうか。うっかり余分の電灯を消し忘れてこの電熱器を点けるとヒューズがとんだのである。
電熱器のニクロム線もよく切れた。すると市販の接着剤でつなぐのである。接着剤というのは白い粉状のもので、切れたニクロム線同士を接触させそこに粉をまぶし通電すると粉が溶融し、ものの見事にニクロム線が接着して機能が回復したのである。この作業がなかなか面白かったことを思い出す。
昭和21年の夏神戸に転宅した。やはり停電がよく起こる。中学生になった頃だろうか試験の時期になりそれでも容赦なく停電する。ところが町の交番署だけはあかあかと電気が灯っている。一人ではいく勇気がなかったので友達を誘い、試験勉強をさせて欲しいとたのんだところ、こころよく許してもらった。理解のあるお巡りさん達で時々遊びに行くようになった。
今日は7月1日、東日本では電力使用制限が始まったとのこと。そのニュースについ昔のことを思いだした。
戦後間も無い頃で停電が日常茶飯事であった。予告なしに電気が消える、そのためにろうそくが用意されていた。停電の原因はもう一つあった。電気の使いすぎでヒューズがよくとぶのである。それを修理するのは私の役目であった。ヒューズ箱を開けて切れたヒューズをとりかえるのである。ヒューズと言っても細い鉛のハンダ糸のようなもので、容量は5アンペアはあっただろうか。その頃一般家庭でニクロム線の電熱器がよく使われていた。わが家ではせいぜい頂き物のおかきを焼いたりカラメル焼きを作るぐらいだった。時には小さなやかんでお湯を沸かした。いちいち七輪をおこすわけにはいかなかったからである。この電熱器の容量はどれくらいだったのだろう。大きくても2、3百ワットではなかっただろうか。うっかり余分の電灯を消し忘れてこの電熱器を点けるとヒューズがとんだのである。
電熱器のニクロム線もよく切れた。すると市販の接着剤でつなぐのである。接着剤というのは白い粉状のもので、切れたニクロム線同士を接触させそこに粉をまぶし通電すると粉が溶融し、ものの見事にニクロム線が接着して機能が回復したのである。この作業がなかなか面白かったことを思い出す。
昭和21年の夏神戸に転宅した。やはり停電がよく起こる。中学生になった頃だろうか試験の時期になりそれでも容赦なく停電する。ところが町の交番署だけはあかあかと電気が灯っている。一人ではいく勇気がなかったので友達を誘い、試験勉強をさせて欲しいとたのんだところ、こころよく許してもらった。理解のあるお巡りさん達で時々遊びに行くようになった。
今日は7月1日、東日本では電力使用制限が始まったとのこと。そのニュースについ昔のことを思いだした。