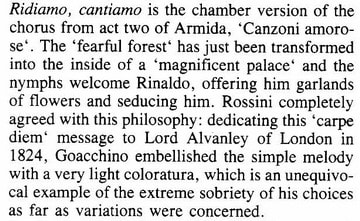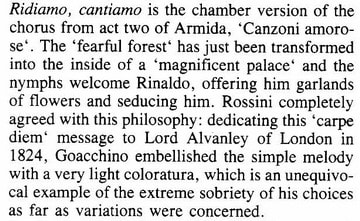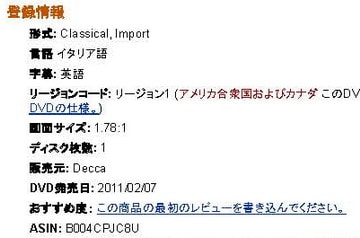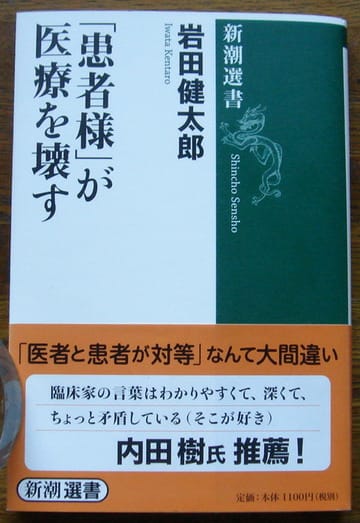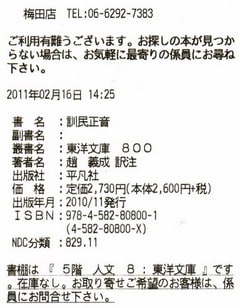この事件の速報は昨年夏にあったが、その最終調査結果が今回公表された。公表されたといっても、私が知り得たのは大阪大学のホームページからアクセス出来る「調査結果の概要」に過ぎない。一部の新聞は購入した物品について、低俗な興味を掻きたてるような報道をしているが、どのような経路でその情報を入手したのか分からない。
正直なところ、かっては私も身を置いていた大学での出来事が、このようなスキャンダルとして世間に広がるのは堪忍して欲しいという思いがある。苦しい財政状況であるにもかかわらず、教育・研究の灯をか細くさせまいと政府が来年度予算案で、科学研究費については本年度予算より230億円増の2230億円を計上し、目下国会で審議が進められている最中である。このスキャンダルが逆風を引き起こさないことを祈るのみである。
私はここで不正経理という言葉を使っているが、報道で使われているからそれを踏襲したまでで、具体的にその内容を理解しているわけではない。それでも定められたルールから外れた予算の使い方をしたことを指しているのだろうなとは想像出来る。しかし、そのルールが必ずしも研究現場の実態に合わないものであれば、研究者はきわめて合理的な判断をする能力に秀でている(筈だ)から、予算をより有効に使うために知恵を働かせるだろうとは容易に推測可能である。だから過去に不正経理にかかわったり見聞きしたことはありませんかと問われると、白鵬関に倣うわけではないが、「それはないとしか言えないじゃないですか」と公には言わざるを得なくなりそうである。
たとえば科研費を申請して、3年間で目標を達成する(つもりの)研究計画が認められたとする。研究が開始されると研究室は戦場である。といっても幸い実弾は飛んで来るわけではないから、3年間は休戦や停戦を抜きに一心不乱ひたすら勝利を目指して突進する。もしルール通りにまず1年目の予算を遣い終えたら、改めて事務手続きを済ませて継続が公に認められるまでの数ヶ月間、業者からは何を買っても借りてもいけないと決められると、否応なしに研究はストップしてしまう。そういう事態が生じないように研究者はそれぞれ知恵を働かせたのであるが、表面だけを眺めると不正経理になってしまうのであろう。こういう矛盾に長年苦しめられてきた研究者の切なる要望に応えて、「最先端研究開発支援プログラム」の研究費は多年度での運用が可能になったが、この手法が科研費にも適用されるようになったとのことである。そうなると「架空伝票操作による物品の購入」は根絶可能であり、また根絶すべきなのである。
私が大学院学生だったほぼ半世紀前は、年に一二回ある学会での研究発表に出席しようとすると、経費は旅費を含めてまったく自分で工面しなければならなかった。奨学金を貯めアルバイトで稼ぎ費用をひねり出していた。ところが私が教員となり、時代も遙かに下ってくるにつけ、大学院生に旅費を出す研究室も現れてきた。そのような使用が認められた寄付金でもない限り出来ないことである。ところが現実には大学院生に旅費を出す研究室が増えてきた。ではどこからお金をひねり出したかというと、これはもう豊かな想像力を働かせていただくしかない。しかし今や大学院生にも原則として旅費の支出が可能になっている。えらい様変わりであるが、ようやく研究の実態に即した予算の使い方に改められたことはご同慶の至りである。
このように社会の取り組みが前向きに進んできたのに反して、伝えられる限り阪大の今回の不正経理の手法があまりにも古典的なので、私はタイムスリップしたかのような錯覚を覚えた。今回の事件で阪大総長コメントが出ていて、次のような一節がある。
不正使用防止につきましては、本学においても、これまで、研究費の管理・監査体制や関係制度の整備、教職員の行動規範の策定等、様々な取組みを推進してまいりましたが、それでもこのような事態が生じたことを重く受け止め、本学において、二度とこのような事態を引き起こさないという決意の下、今回の事案を踏まえての再発防止策をとりまとめ、その一部については既に実施しているところです。
この強調部分が実際に働いているのなら今回のような不正経理が起こりようがないはずである。しかし現実に起こった以上、この強調部分がただの飾り文句にすぎなかったのか、それとも具体的な取り組みが実効を発揮しえなかったのかということになるが、いずれにせよ不正経理が行われたという現実の前には、この強調部分が色あせてしまうことは事実であろう。新機軸の「不正経理手技」が持ち込まれたのならともかく、旧態依然の手法がそのまままかり通ったのであるから、大学側の管理体制がなっていなかったことになる。しかし考えてみれば、この大阪大学の「おおらかさ」こそ学術研究の場に相応しいもので、糾弾されるべきなのはあくまでも不正を働いた側である。このようなスキャンダルがあったからとて、不正経理防止を旗印に煩雑な事務手続きを増やすことになれば、角を矯めて牛を殺すことになりかねない。理性的な対処を期待したい。
不正経理の状況を朝日新聞は次のように報じている。
研究費の不正使用が判明したのは、森本特任教授が昨年3月まで教授を務めていた環境医学講座の研究室。大阪大の調査委員会は2004年4月から6年2カ月分の資料を調べ、関係者に聞き取りをしてきた。
その結果、研究員のカラ出張1328万円、森本特任教授のカラ出張362万円や海外出張で事前の届け出と違う413万円、さらに消耗品を買ったことにして実際はパソコンや家族へのブルーレイ・ディスクプレーヤーを買うなど架空伝票操作での物品購入1593万円、タクシー代335万円など不適切な使い方をした分も含め計4176万円を不正使用と認定した。この間に受けた研究費は計約2億2500万円。不正支出は森本特任教授の指示や認識のもとで行われたとした。
これだけ巨額の研究費補助を受けていながら、研究目的の達成に何が不足だったのだろう。あり得るはずがないと思うのに、約2億2500万円の研究費のうち、不正使用と認定されたのが4176万円とは多すぎる。しかしこの4176万円の具体的な使い道が詳細に示されていないので、なぜそこまでして「裏金」を作らなければならなかったのか、動機が見えてこない。ただ断言出来るのは、この研究室には「金余り現象」が発生していたということである。
かって私は最先端研究開発支援プログラムを凍結出来なかった民主党で次のような引用をしたことがある。これは最先端研究開発支援プログラム問題についての引用であるが、科研費一般を対象にしても言えることであると思う。民主党科学技術政策ワーキングチームの一員である参議院議員藤末健三氏が、研究者のなかから指摘された問題点を紹介したものである。
採択プロジェクトが決定した後、本制度には直接関係がない私のところにも数多くの研究者や関係者から問題を指摘するメールが入りました。直接私の事務所まで来られた方も何人もいらっしゃいます。
こうした話をまとめると、
(1)すでに十分な研究費をもった研究者に研究費が集中しすぎ。若手研究者に研究費を回すべき。著名な研究者に数十億円の研究費が集まると、その研究者に多くの若手研究者が集まらざるを得ず、若い研究者が新しいテーマに挑戦する機会を逆に奪ってしまう
(2)巨額の研究費の配分を決めるにしては審査手続きが不十分。実際、相当な労力を使い申請書を書いたのに数十分くらいの審査で終わった。審査委員が研究分野の専門家ではないことも問題。
(3)研究費が大きすぎて、研究費がずさんな使われ方をするのではないか。例えば、研究評価は総合科学技術会議が実施することになっているが、これでいいのか疑問。プロジェクトを選択した組織が、自分自身が選択したプロジェクトを失敗だと評価するはずがないの3点に問題点はまとめられるように思います。
研究費が一部の研究者へ集中することの弊害が、研究者自身によって的確に指摘されている。「金余り現象」を生み出す一部の研究者への研究費集中、これを排除するための方策を立てることが焦眉の急であろう。
それと同時に、すでに実施されているのかも知れないが、科学研究費すべてに亘って、未使用予算の返却を義務づける制度がなければならない。水増し予算が通って処理に困っては大変だし、上手に予算を使って余らせたとやりくりの才を誇る人が出てくるのもよい。世の中万事、計算通りにことが運ぶわけではない。ただ辻褄合わせで見かけを飾るのがほとんどであろう。そうではなく、必要なものならコンドームであれ得体の知れない本であれ、何でも買いこめばよいのである。
私はかって研究費でパンティストッキングを買えるようにのような記事を書いたことがあるので、コンドームぐらいで驚きはしない。誰も思いつかなかった発想こそ研究者の命である。取材記者が不審を抱いたのであれば、とことん経緯を追求した上で、たとえばコンドームがいかに無駄な出費であったのかを読者に納得させるぐらいの意気込みが欲しいものである。それが今回は見えてこなかった。もちろん研究者が購入物品がどこでどのように研究に使われたのか、当然説明と報告の義務があるが、そこまで調査がなされたのかどうかも分からない。
少し脱線を元に戻せば、大阪大学の調査結果(概要)で私が注目したのは「特任研究員等の給与の支給と一部戻し」の部分である。
(4)特任研究員等の給与の支給と一部戻し
○ 特任研究員が欠勤している期間について、970,427円の給与が支払われている。
○ 特任研究員等5人が、支払われた給与から少なくとも合計3,781,057円を研究室に戻している。
過去の産経新聞に次のような記事があった。
大阪大学大学院医学系研究科・医学部の元教授(64)の研究室で、非常勤の研究員が毎月、大学から受け取った給与の約半額を“キックバック”の形で研究室内の事務担当者に返金するよう研究室側から指示され、その金は部外者に分からないようプールされていた疑いがあることが12日、産経新聞の取材で明らかになった。阪大は公金である研究員の給与が、返金させられた事態を重くみて、学内で調査委員会を立ち上げ本格調査に乗り出すとともに、文部科学省にも通報した。
阪大や複数の関係者によると、要求されていたのは中国籍の30代男性。
この男性は、独立行政法人「科学技術振興機構」(JST)から、この元教授の研究室が受託した研究に携わるため、平成20年5月から阪大と雇用契約を結び、「特任研究員」と呼ばれる非常勤の研究員として勤務していた。JSTは16~21年度の6年間、研究費として約5千数百万円を阪大に支給しており、阪大はこの中から研究員に給与を支払っていた。
研究員の給与は原則的に時給制で、就業時間などの雇用条件は研究室で決定できるといい、男性は当初、毎月約10万円の給与を受け取っていた。
ところが20年秋ごろ、研究室の会計担当者らから、「JSTの研究費が700万円余るので使い切りたい。手取り分として5万円を上乗せするから、振り込んだうち半分を返金してほしい」と持ちかけられ、了承した。
翌月から約1年間、男性の銀行口座には毎月三十数万円が振り込まれるようになったが、男性は約半額の15万円程度を毎回引き出し、事務担当者に現金で手渡していた。事務担当者はこの金を研究室関係者の名義とみられる口座に入金していたという。キックバックの総額は200万円前後に上るとみられるという。
男性は産経新聞の取材に「要求を断り切れなかった。働き続けたかったので、大学に通報もできなかった」と話している。
「キックバック」の実態についてことさら説明を付け加えるまでもなかろう。それにしても口入れ屋のピンハネまがいとはあまりにも古すぎる。これではまるでかっての政治家と変わりがないではないか。それよりも注目すべきなのは、この研究費の出所が独立行政法人「科学技術振興機構」(JST)になっていることなのである。文部科学省は広い意味の科学研究費を「日本学術振興会」と「科学技術振興機構」という二つの窓口を通じで研究者に研究費を配っている。文科省での日本学術振興会と科学技術振興機構の共存が基礎科学の発展を邪魔するで述べたが、この制度こそ《すでに十分な研究費をもった研究者に研究費が集中しすぎ》を生んでいるのであって、阪大のケースがそれに当たると言えよう。《すでに十分な研究費をもった研究者に研究費が集中しすぎ》を防ぐにはどうすればよいのか。具体策を作り上げていくのにぜひ考慮すべきなのは、この程度の仕事(研究)にどれぐらいお金がかかるのかを見抜く目の存在である。私は楽観的かも知れないが、ある程度の研究生活を経験している人なら、そのようなことは調べ上げる能力を確実に持っていると思う。そういう人たちをどんどん活用すればよいのである。
もう一つ気になったのが旅費がきわめて高額になっていることである。これも阪大の調査報告である。
(1)旅費
○ 森本教授について、平成16年度以降、3,626,310円のカラ出張等が認められる。
○ 研究室の助教等の名義の旅費について、平成16年度以降、13,288,670円のカラ出張等が認められる。
○ 森本教授の海外出張について、出張伺いと実際の出張の内容が不一致なものがあり、4,134,295円を返還する必要があると認められる。
○ 森本教授の海外出張における出張旅費の内453,690円については、森本教授の家族の旅費であると認められる。
「旅費」と名目がつくと阪大では無条件に支出が認められているようである。私の現役時代は確か旅費は総予算の何%以内と決められていたような気がするが、今やその制限がなくなったのだろうか。上記の産経新聞記事に次のような下りがある。
元教授は産経新聞の取材に対し「私は教授なので出張が多くすべて担当制にしていた。担当者に責任を持ってやってもらっている」と釈明し、関与を否定している。
世間の人は「私は教授なので出張が多い」と聞けば、なるほど、外での用事が多くなるんだ、と納得するかも知れない。さらには大学に、研究室にほとんど居ない教授ほど偉い人と思うかも知れないが、それは本末転倒である。自分の主宰する研究室を留守がちにしてまで政府関係の各種委員会を始めとして、各種学会の会議や研究会等々に顔を出すのを生き甲斐のようにしているような教授は、実験一筋の科学者には、うさんくさくてまともには見えないのである。(私はプロフェッショナルな「科学管理職」が日本に確立していないものだから、古手の教授がその役割のある面を担わされているのが現実だと認識している。それが米国では科学者や研究者がそれまで属していた研究分野から転進して担うべき職務になっている。日本でもたとえば一定年齢以上の教授を「科学管理職兼教育者」と「研究者」に制度的に分離すれば、論文に名前だけを載せる教授は存在し得なくてってすっきりとする。)もちろん政府関係委員会の仕事などは頼まれてのことであろうが、それも人の頼みを断れないただの尻軽なお人好しに過ぎないと言ってしまえばそれまでのことである。研究現場にでんと構えてこそ研究者なのである。私がここまで言いきるのは、学部長の要職を務めながらも、時間が少しでもあれば寸暇を惜しんで自ら実験に没頭し、また教室員をつかまえては、口角泡を飛ばす議論に引きずり込むのを常としていた、ある医学部教授を長年身近に見てきたからなのである。
現に「私は教授なので出張が多くすべて担当制にしていた。担当者に責任を持ってやってもらっている」と言っていた元教授だからこそ、世間から糾弾されるような不祥事を引き起こしたとも言えよう。若い研究者の妥協しない眼差しが、こうした似非研究者をいたたまれなくさせるようになれば、日本の科学研究環境が大きく変わることは間違いない。
お断り(2月17日)
少々修正した上、舌足らずを補うために加筆した。