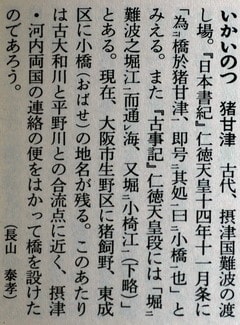黄砂がやって来るかと思ったのに雲一つない青空が広がっている。昨日はちょっと内緒の外出をしたので今日は家に居るつもりだったが、この快晴に身体がむずむずする。そして朝日朝刊の記事が火に油を注いだ。

《全国の20を超すレストランがほれ込んで取り寄せるハムやソーセージを作る神戸生まれの職人がいる》と言う記事である。《単身ドイツに渡って修業。身につけた600種類以上の製法を日本の食材に合わせて改良し、ヨーロッパ伝統の味を芦屋で再現している》とのこと。ランチはここと決め、場所を調べてパッと飛び出した。
阪神電車芦屋駅で下車、山側に出て東の方に数分歩くと宮塚公園に差し掛かり、南北に走る道路の向かい側にあるのがこの店である。中に入るとテレビカメラを担いだ四名ほどの取材陣がいて、男性が一人私に声をかけた。テレビ朝日のなんとかなんとかと番組名を告げて、「よくおいでになりますか」と聞く。「いや、はじめてで・・・」と答えるとサッと退いた。眼鏡違いであったらしい。大きなガラスケースに沢山の出来上がりの品物が並べられている。ドテッとした肉のかたまりがそのまま置かれ、お好みの量をお切りします、といった感じでちょっと日本離れしている。店内の一郭に小さな丸テーブルが四脚とそれぞれに椅子が二脚ずつ置かれ、「イートイン」が出来ることが分かってやれやれ。いろんな組み合わせで独自のメニューが可能であるが、「シュ-クル-ト・ガルニ」の文字が目についたのでこれを白ワインとともに注文した。わが家の定番メニューでもあるので、食べ比べである。

ザワークラウト(シュ-クル-ト)に塩漬けのすね肉、ソーセージ、ベーコンを煮込んだもの。ザワークラウトの酸味がそのまま残っているので私には少々きつい。わが家では軽く水洗いして酸味を下げている。ザワークラウトのないときはキャベツの千切りとキャラウエイシードをバターでよく炒め、レモン汁をたっぷりとたらし込んだものである。ソーセージがなかなか堅く、ドイツでもこんなに堅いソーセージはお目にかかったことがなかった。しかし味わいがあり、全体がまさにドイツ(アルザス?)風。さっぱりとした白ワインとで美味しくいただけた。
テリーヌが何種類もあるので決めるのが難しかったが、「テリーヌ クール ドゥ コション」と「テリーヌ ド パンタード アーモンド」なるものを買い求め、さっそく夕食にいただいた。田舎風というか質実剛健で素朴な味わいが私の好みに合う。夜も白ワイン、これでテレビを見始めたらコックリさん、間違いなしである。


《全国の20を超すレストランがほれ込んで取り寄せるハムやソーセージを作る神戸生まれの職人がいる》と言う記事である。《単身ドイツに渡って修業。身につけた600種類以上の製法を日本の食材に合わせて改良し、ヨーロッパ伝統の味を芦屋で再現している》とのこと。ランチはここと決め、場所を調べてパッと飛び出した。
阪神電車芦屋駅で下車、山側に出て東の方に数分歩くと宮塚公園に差し掛かり、南北に走る道路の向かい側にあるのがこの店である。中に入るとテレビカメラを担いだ四名ほどの取材陣がいて、男性が一人私に声をかけた。テレビ朝日のなんとかなんとかと番組名を告げて、「よくおいでになりますか」と聞く。「いや、はじめてで・・・」と答えるとサッと退いた。眼鏡違いであったらしい。大きなガラスケースに沢山の出来上がりの品物が並べられている。ドテッとした肉のかたまりがそのまま置かれ、お好みの量をお切りします、といった感じでちょっと日本離れしている。店内の一郭に小さな丸テーブルが四脚とそれぞれに椅子が二脚ずつ置かれ、「イートイン」が出来ることが分かってやれやれ。いろんな組み合わせで独自のメニューが可能であるが、「シュ-クル-ト・ガルニ」の文字が目についたのでこれを白ワインとともに注文した。わが家の定番メニューでもあるので、食べ比べである。

ザワークラウト(シュ-クル-ト)に塩漬けのすね肉、ソーセージ、ベーコンを煮込んだもの。ザワークラウトの酸味がそのまま残っているので私には少々きつい。わが家では軽く水洗いして酸味を下げている。ザワークラウトのないときはキャベツの千切りとキャラウエイシードをバターでよく炒め、レモン汁をたっぷりとたらし込んだものである。ソーセージがなかなか堅く、ドイツでもこんなに堅いソーセージはお目にかかったことがなかった。しかし味わいがあり、全体がまさにドイツ(アルザス?)風。さっぱりとした白ワインとで美味しくいただけた。
テリーヌが何種類もあるので決めるのが難しかったが、「テリーヌ クール ドゥ コション」と「テリーヌ ド パンタード アーモンド」なるものを買い求め、さっそく夕食にいただいた。田舎風というか質実剛健で素朴な味わいが私の好みに合う。夜も白ワイン、これでテレビを見始めたらコックリさん、間違いなしである。