最近私の楽しみがひとつ増えた。以前にノーベル医学生理学賞が日本に来ないのはなぜ?でご登場いただいた旧知の増井禎夫さんとSkypeで時々おしゃべりをさせていただいているのである。ご夫妻はカナダのトロントにお住まいで時差は13時間、こちらが午前10時とするとトロンとは午後9時でちょうど昼夜が逆転している。おしゃべりには絶好の時間帯(その逆も)で、つい話が弾んでしまう。先だってもゴシップ大好きの私がぞくぞくとする話が飛び出たので、増井さんにお断りした上でここに紹介させていただく。
増井さんがYale大学で所属したのは、当時生物学部のチェアーマンであったClement L. Markert教授の研究室であった。このマーカートさんが研究室に来て1週間経つかたたない増井さんをつかまえて、「日本に駐留している米軍のことをどう思うか」と聞かれたそうである。「いざとなれば日本を守ってくれるのでしょう」の答えに、「それは甘い。アメリカはよその国のために戦うようなことはしない」と言われたそうである。なんと風変わりなプロフェッサーと私は一瞬思ったが、それよりもっと凄いのがマーカートさんが学生時代に歴史にも名高いAAbraham Lincoln大隊に加わってスペインでフランコ軍を相手に戦ったという話であった。スペイン内戦>ヘミングウエイ>「誰がために鐘は鳴る」と連想が走って興奮してしまったのである。さらにはマッカーシズムの嵐をもろに受けてMichigan州立大学で停職処分になったりとか、すでにそれだけでも波乱万丈の生き方に感銘を受けてしまった。その経緯がよくまとめられているので、とわざわざ増井さんから送っていただいた次の冊子と「Clement Markert, 82, a Biologist Suspended in the McCarthy Era」と題したThe New York Timesの追悼記事(1999年10月10日)をもとに、私なりに要点をまとめてみた。
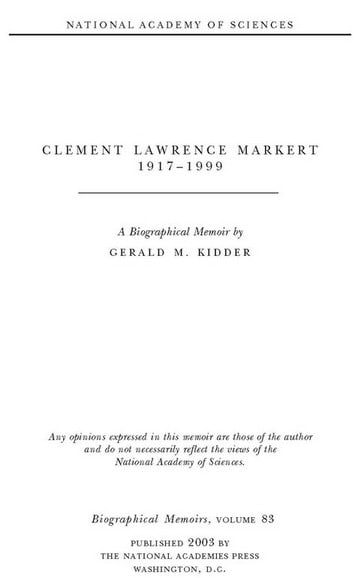
1917年にコロラド州(Las Animas)で生まれたマーカートさんの父親が製鋼所の労働者で、大恐慌時代に鉱山や製鋼所が閉ざされたためにその影響をもろに受けた。この経験がマーカートさんの社会的良心を育むことになった。学業成績が優秀だったので与えられた奨学資金のおかげでUniversity of Colorado at Boulderに進むことができ、生物学を学ぶことになった。その頃、国際舞台での出来事、とくに労働者階級が必要とするものが叶えられないのは、資本主義経済が破綻しているからであると感じられることに関心が向けられた。そして社会主義思想を受け入れ、大学で共産主義者のグループを組織するに至ったのである。ほどなく彼の社会理想を実践に移す機会が訪れた。スペインのフランコに象徴されるファシズムと戦うために、学業を中断して2800名からなるAbraham Lincoln Brigadeに加わることにした。そのために大学のルームメイトと貨車に乗って東海岸に出て、当時米国はスペインへの旅行を禁じていたのでフランス行きの商船で密航したのである。
スペイン内戦は1936年月7月17日にスペイン領モロッコで勃発してスペイン全土に拡大し、39年4月日に終結した。これで王制を覆して成立した第二共和制が崩壊し、フランコ政権が確立した。この内戦は世界的な反響と関心を呼び、単なる一国内の内戦として片付けられるべきものではなく、第二次大戦の序曲でその実験でもあった。ドイツ、イタリアがフランコ側につき、ソ連が共和政側についたある種の代理戦争のようなものでもあった。右派にとってこの内戦は共産主義に対する十字軍の戦いであり、左派にとってもファシズムに対する大十字軍であった。スペインで戦場となった地形がマーカートさんの育ったPueblo, Colo.の地形とよく似ていて、そこでの山岳体験が時には敵の背後にも回る偵察行動に生かされた。クラスメイトは戦死したが彼は数少ない生存者の一人となったのである。次の記事が残されている。
対ファシズムの戦いに敗れて帰国後はコロラド大学で学業を終え、UCLAの大学院で脊椎動物の発生学の研究を始めた。しかしアメリカが第二次大戦に参戦したのでマーカートさんはファシズムへの個人的な戦いを再開する道を選び、修士号を1942年に得てから米国陸軍に入隊しようとした。しかし当時の政治情勢では彼が米国とスペインの共産党員と関わったことが引っかかり、軍務に服すことができなかった。そこでサンディエゴで港湾労働者として働き、やがて商船隊に受け入れられて、太平洋上の米国艦隊への補給船で通信士として勤務したのである。
戦争の時期を通り抜け、マーカートさんはJohns Hopkins Universityで生物学の博士コースに入り、当時国内で最も注目されていた発生生物学者Benjamin H. Willier教授指導のもとで研究を進めて、1948年に学位を得た。1950年、University of Michigan in Ann Arborの生物学部でAssistant Professorの職を得て研究者として独立した。ところが幸せな研究生活を送っているそのさなか、あの「マッカーシー旋風」をもろに受けることになった。非米活動委員会で証言を拒んだことにより他の同僚二名と共に停職となった。しかし再審議の過程でマーカートさんの人間としての誠実さに揺るぎない信頼を抱いた大学の仲間達、そして科学的洞察力に深い感銘を受けた科学者たちの強い支持により、ただ一人だけ復職が認められた。これについて次の言葉が残されている。
マーカートさんの若い時代の社会主義者としての積極的行動は後々までも物議を醸した。1957年に彼の大学院の指導者であったWillier教授が退職することになったのでJohns Hopkins Universityの発生生物学のポストに応募した時のことである。選考委員会は彼を推薦したが、大学管理部門が異を唱えたのである。しかしその膠着状態は時の学長であるMilton Eisenhower博士(Eisenhower米国大統領の弟)がマーカートさんを直接に面接したことで一挙に解決した。彼を正教授に推薦して、もし任命が認められなければ自分が辞職するとまで主張したからである。Yale大学生物部のチェアーマに任命されるにあたっても、時の学長Kingman Brewster博士が彼の過去の全てと、これからも社会の大義名分を追って活動を続けていくつもりであることを承知してもらうことに心を砕いたのである。ちなみにこのBrewster学長は時の人とかでTime誌の表紙を飾ったこと、そして学長主催の留学生歓迎パーティでは私立ち握手で出迎えてくださったことを今でも覚えている。増井さんご夫妻と出会ったのもこの時であった。
この誠実なお人柄があってこそ、ノーベル医学生理学賞が日本に来ないのはなぜ?で引用させていただいた増井さんの次の言葉が心にしみ入るのである。
The New York Timesの追悼記事は次のように締めくくられる。
社会活動家として、科学者として、理想と行動に道を極めた巨人にしてはじめて言える言葉だと思う。こんな人が実在していたのである。
院生時代、今、デモに参加すべきなのか実験に集中すべきなのか、仲間たちと侃侃諤諤の論議を交わしていたことを、ふと思い出した。
増井さんがYale大学で所属したのは、当時生物学部のチェアーマンであったClement L. Markert教授の研究室であった。このマーカートさんが研究室に来て1週間経つかたたない増井さんをつかまえて、「日本に駐留している米軍のことをどう思うか」と聞かれたそうである。「いざとなれば日本を守ってくれるのでしょう」の答えに、「それは甘い。アメリカはよその国のために戦うようなことはしない」と言われたそうである。なんと風変わりなプロフェッサーと私は一瞬思ったが、それよりもっと凄いのがマーカートさんが学生時代に歴史にも名高いAAbraham Lincoln大隊に加わってスペインでフランコ軍を相手に戦ったという話であった。スペイン内戦>ヘミングウエイ>「誰がために鐘は鳴る」と連想が走って興奮してしまったのである。さらにはマッカーシズムの嵐をもろに受けてMichigan州立大学で停職処分になったりとか、すでにそれだけでも波乱万丈の生き方に感銘を受けてしまった。その経緯がよくまとめられているので、とわざわざ増井さんから送っていただいた次の冊子と「Clement Markert, 82, a Biologist Suspended in the McCarthy Era」と題したThe New York Timesの追悼記事(1999年10月10日)をもとに、私なりに要点をまとめてみた。
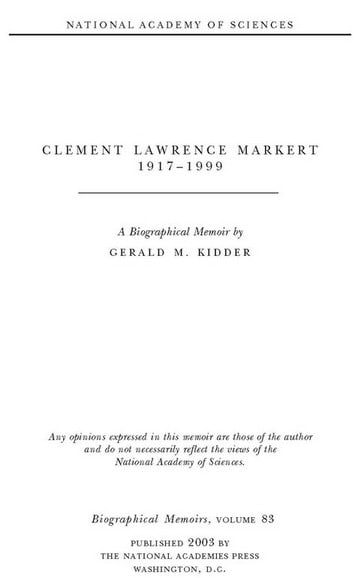
1917年にコロラド州(Las Animas)で生まれたマーカートさんの父親が製鋼所の労働者で、大恐慌時代に鉱山や製鋼所が閉ざされたためにその影響をもろに受けた。この経験がマーカートさんの社会的良心を育むことになった。学業成績が優秀だったので与えられた奨学資金のおかげでUniversity of Colorado at Boulderに進むことができ、生物学を学ぶことになった。その頃、国際舞台での出来事、とくに労働者階級が必要とするものが叶えられないのは、資本主義経済が破綻しているからであると感じられることに関心が向けられた。そして社会主義思想を受け入れ、大学で共産主義者のグループを組織するに至ったのである。ほどなく彼の社会理想を実践に移す機会が訪れた。スペインのフランコに象徴されるファシズムと戦うために、学業を中断して2800名からなるAbraham Lincoln Brigadeに加わることにした。そのために大学のルームメイトと貨車に乗って東海岸に出て、当時米国はスペインへの旅行を禁じていたのでフランス行きの商船で密航したのである。
スペイン内戦は1936年月7月17日にスペイン領モロッコで勃発してスペイン全土に拡大し、39年4月日に終結した。これで王制を覆して成立した第二共和制が崩壊し、フランコ政権が確立した。この内戦は世界的な反響と関心を呼び、単なる一国内の内戦として片付けられるべきものではなく、第二次大戦の序曲でその実験でもあった。ドイツ、イタリアがフランコ側につき、ソ連が共和政側についたある種の代理戦争のようなものでもあった。右派にとってこの内戦は共産主義に対する十字軍の戦いであり、左派にとってもファシズムに対する大十字軍であった。スペインで戦場となった地形がマーカートさんの育ったPueblo, Colo.の地形とよく似ていて、そこでの山岳体験が時には敵の背後にも回る偵察行動に生かされた。クラスメイトは戦死したが彼は数少ない生存者の一人となったのである。次の記事が残されている。
In an obituary for Markert in The New York Times(October 10, 1999) he was quoted as having said in a 1986 interview, “I felt the most concrete thing I could do at the time was to destroy fascism, and Spain was the battleground on which to do that.”
対ファシズムの戦いに敗れて帰国後はコロラド大学で学業を終え、UCLAの大学院で脊椎動物の発生学の研究を始めた。しかしアメリカが第二次大戦に参戦したのでマーカートさんはファシズムへの個人的な戦いを再開する道を選び、修士号を1942年に得てから米国陸軍に入隊しようとした。しかし当時の政治情勢では彼が米国とスペインの共産党員と関わったことが引っかかり、軍務に服すことができなかった。そこでサンディエゴで港湾労働者として働き、やがて商船隊に受け入れられて、太平洋上の米国艦隊への補給船で通信士として勤務したのである。
戦争の時期を通り抜け、マーカートさんはJohns Hopkins Universityで生物学の博士コースに入り、当時国内で最も注目されていた発生生物学者Benjamin H. Willier教授指導のもとで研究を進めて、1948年に学位を得た。1950年、University of Michigan in Ann Arborの生物学部でAssistant Professorの職を得て研究者として独立した。ところが幸せな研究生活を送っているそのさなか、あの「マッカーシー旋風」をもろに受けることになった。非米活動委員会で証言を拒んだことにより他の同僚二名と共に停職となった。しかし再審議の過程でマーカートさんの人間としての誠実さに揺るぎない信頼を抱いた大学の仲間達、そして科学的洞察力に深い感銘を受けた科学者たちの強い支持により、ただ一人だけ復職が認められた。これについて次の言葉が残されている。
Markert would later relate this experience to his students to emphasize the importance of standing up for one’s convictions, whether scientific or political, regardless of the cost.
マーカートさんの若い時代の社会主義者としての積極的行動は後々までも物議を醸した。1957年に彼の大学院の指導者であったWillier教授が退職することになったのでJohns Hopkins Universityの発生生物学のポストに応募した時のことである。選考委員会は彼を推薦したが、大学管理部門が異を唱えたのである。しかしその膠着状態は時の学長であるMilton Eisenhower博士(Eisenhower米国大統領の弟)がマーカートさんを直接に面接したことで一挙に解決した。彼を正教授に推薦して、もし任命が認められなければ自分が辞職するとまで主張したからである。Yale大学生物部のチェアーマに任命されるにあたっても、時の学長Kingman Brewster博士が彼の過去の全てと、これからも社会の大義名分を追って活動を続けていくつもりであることを承知してもらうことに心を砕いたのである。ちなみにこのBrewster学長は時の人とかでTime誌の表紙を飾ったこと、そして学長主催の留学生歓迎パーティでは私立ち握手で出迎えてくださったことを今でも覚えている。増井さんご夫妻と出会ったのもこの時であった。
この誠実なお人柄があってこそ、ノーベル医学生理学賞が日本に来ないのはなぜ?で引用させていただいた増井さんの次の言葉が心にしみ入るのである。
マーカートの研究室では最初、ペンギンの発生に関係する酵素の分析を手伝ったが、一つ論文ができたところで、「君の好きなことをやりなさい」と言われた。ニ、三アイディアをもっていくと、日本でもできる安上がりの仕事にしたらどうかと言う。とても現実的な対応だ。夢は夢、その中から現実性の高いものを選んでいくのが本当の選択だと教えられた。それで、若い時からの夢である核と細胞質の相互作用が、卵の成熟の時にどのように起きるかをテーマにすることにした。これだったら、材料はカエル。あとはガラス管と顕微鏡とリンガ一液があればできる。しかも、たった一つの卵細胞が一つの方向に変化していくのを追っていけばよいのだから、系としても簡単だった。
The New York Timesの追悼記事は次のように締めくくられる。
Associates said Dr. Markert never lost his interest in politics over the years or his commitment to what he believed was justice. But in his 1986 interview, Dr. Markert said he had had to forgo his activism.
''I made the conscious decision that I could not be both a first-rate scientist and a social activist,'' he said.
''I made the conscious decision that I could not be both a first-rate scientist and a social activist,'' he said.
社会活動家として、科学者として、理想と行動に道を極めた巨人にしてはじめて言える言葉だと思う。こんな人が実在していたのである。
院生時代、今、デモに参加すべきなのか実験に集中すべきなのか、仲間たちと侃侃諤諤の論議を交わしていたことを、ふと思い出した。






















