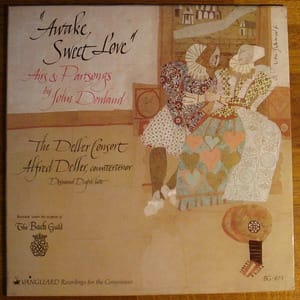12月28日の私のエントリーにたいして29日の早朝にコメントを頂き、東京大学立花ゼミが渦中の多比良和誠氏をインタビューした取材風景の動画の存在を知った。「研究捏造問題」から動画のサイトにアクセスできる。
動画は7本に分割しているようだ。単純に計算すると総時間数は57分22秒に及ぶ。この動画公開に際して、《多比良氏本人に了解をいただき、多比良氏取材の動画を、急遽、ほぼ編集なしで公開することにしました。ゼミの取材班が体験したのと同じように多比良氏の話をそのまま聞くことで、果たして東京大学の処分が適切だったか、また、多比良氏の人間像がいかようなものかなどを、皆様一人ひとりに考えていただきたいからです。》のコメントが付されている。取材場所は見当がつくが、取材日時はなぜか明らかにされていない。
『象牙の塔』の中で発生した『不祥事』の当事者が、たとえ一人でもこのような形で自分の主張を述べ、またその映像記録が公開されたというのは画期的な出来事である。
多比良氏はまことに能弁で、淀みなく話が流れ出る。インタビュー相手にこれだけ喋らすことができるとは、聞き上手だな、とも思った。しかし聞く側が多比良氏の弁舌に酔ったような気配もある。そのせいかどうか、聞く側の突っ込みらしい突っ込みがほとんどないのが気になった。それが取材方針だったのだろうか。
論文の書き方を学生に指導する話が出てくる。多比良氏がたとえ学部の学生でも先ず学生に書かせて、それを原型が残らないぐらいまで学生とやり取りをしながら修正をしていくというのだ。私も多比良氏のこの指導法にここまでは100%賛成である。ところが続いてこのような話になる。「昼間電話その他で忙しいので、夜、学生には可哀相なんだけれど夜中に呼び出して朝までに終わるとか」。聞く側はそれで感心してしまっったのか、ただ承るのみである。
教育・研究が本務である筈の大学教授が「昼間電話その他で忙しいので」なんて云うと、「電話と研究指導とどちらが大事なんだろう」と私が学生の立場なら素朴な疑問が湧く。そして忙しさの中身を知りたくなる。「たとえばどのようなご用で?」と一人でもいいから聞き返して欲しかった。「教授リッチ(研究費が潤沢との意、注)で留守がよい」と一部では評判受けのするタイプであったのか、と私のようなげすは勘ぐってしまう。
突っ込みの欲しかったのはこの一例に止まらない。それが企画者の意図だったのかどうか、このインタビューは多比良氏の独演会のようなものに終わっている。せっかくの機会だからいろいろと事実関係をもっと明らかにして欲しかったの思いは残るが、多比良氏の『人間像』をある程度浮き彫りにした点では大いに評価できる。
さてその『人物像』である。
大阪大学杉野事件が表面化した際に、私は9月25日のエントリーで《在米期間が長かったと伝えられる杉野教授が、アメリカンスタイルをどうも持ち込んでいたらしい、と私は推測した。》と記した。そして、アメリカンスタイルとはどのようなものか、例を持ち出した説明した。ところがなんとここに実例があったのだ。アメリカの大学で専門教育を受けて学位も得た多比良氏が、アメリカンスタイルを自分の研究室に持ち込んだことをご本人が得々と語っているのである。研究ノートの一件である。
研究ノートの有無が東大多比良事件を特徴づけたぐらいそのウエイトは重い。私は研究ノートを撮した映像の一画面から、多比良氏は助手であった川崎氏に対しても研究ノートの『検閲』を目論んだなとの印象を持った。そう受け取られても仕方のない状況証拠なのである。私の印象がもし正しければ、これは紛れもなく『アカデミック・ハラスメント』になる。この問題は極めて重要であるので、年が明けてからまた取り上げることにする。
それはさておき、多比良氏はこのように仰っている。「私がデータを捏造すると、もっと早い時間に見つかっていた。というのは私は実験をやらないから。うん、実験をやった連中がすぐに気付く。私が何かデータを変えるとね」と。
ご多分に洩れず多比良氏も私が常に問題視する『自分で実験をしない、その実、実験をもはや出来なくなった教授』であったのだ。ところがその「実験をやらない」ことを逆手にとって、「だから私は捏造には関わっていない、それなのになぜ・・・」と暗に自己主張に結びつけるあたりは、さすがアメリカ仕込みの『debater』である。
この点でも聞く側の突っ込みがなかったのが心残りである。私が学生ならちょっと乱暴でも「先生、プロ野球でも、サッカーでも大相撲でも、プレイヤーが現役を退いたら、コーチとか監督とか親方になりますよね。そして後進の指導にあたる。現役のプレーヤーとは厳然と一線を劃しますよね。横綱が優勝すれば表彰されるのは横綱で親方ではない。先生が実験を止めたら現役を退くようなものではないですか。それなのに、先生が現場の研究者と同じように論文に名を連ねるなんて変におもわれませんか」と聞いてみて、反応を心待ちにするだろう。
ひょっとすると、東大の学生諸君にとって、多比良氏のように自分では実験をせずに大勢の教室員を使って『業績』をあげるような教授が目指す理想像なのだろうか、とも思った。それこそげすの勘ぐりで終わって欲しいものである。
このインタビューの映像を観て、それぞれの方がどのような感想を持たれるか、興味津々である。
動画は7本に分割しているようだ。単純に計算すると総時間数は57分22秒に及ぶ。この動画公開に際して、《多比良氏本人に了解をいただき、多比良氏取材の動画を、急遽、ほぼ編集なしで公開することにしました。ゼミの取材班が体験したのと同じように多比良氏の話をそのまま聞くことで、果たして東京大学の処分が適切だったか、また、多比良氏の人間像がいかようなものかなどを、皆様一人ひとりに考えていただきたいからです。》のコメントが付されている。取材場所は見当がつくが、取材日時はなぜか明らかにされていない。
『象牙の塔』の中で発生した『不祥事』の当事者が、たとえ一人でもこのような形で自分の主張を述べ、またその映像記録が公開されたというのは画期的な出来事である。
多比良氏はまことに能弁で、淀みなく話が流れ出る。インタビュー相手にこれだけ喋らすことができるとは、聞き上手だな、とも思った。しかし聞く側が多比良氏の弁舌に酔ったような気配もある。そのせいかどうか、聞く側の突っ込みらしい突っ込みがほとんどないのが気になった。それが取材方針だったのだろうか。
論文の書き方を学生に指導する話が出てくる。多比良氏がたとえ学部の学生でも先ず学生に書かせて、それを原型が残らないぐらいまで学生とやり取りをしながら修正をしていくというのだ。私も多比良氏のこの指導法にここまでは100%賛成である。ところが続いてこのような話になる。「昼間電話その他で忙しいので、夜、学生には可哀相なんだけれど夜中に呼び出して朝までに終わるとか」。聞く側はそれで感心してしまっったのか、ただ承るのみである。
教育・研究が本務である筈の大学教授が「昼間電話その他で忙しいので」なんて云うと、「電話と研究指導とどちらが大事なんだろう」と私が学生の立場なら素朴な疑問が湧く。そして忙しさの中身を知りたくなる。「たとえばどのようなご用で?」と一人でもいいから聞き返して欲しかった。「教授リッチ(研究費が潤沢との意、注)で留守がよい」と一部では評判受けのするタイプであったのか、と私のようなげすは勘ぐってしまう。
突っ込みの欲しかったのはこの一例に止まらない。それが企画者の意図だったのかどうか、このインタビューは多比良氏の独演会のようなものに終わっている。せっかくの機会だからいろいろと事実関係をもっと明らかにして欲しかったの思いは残るが、多比良氏の『人間像』をある程度浮き彫りにした点では大いに評価できる。
さてその『人物像』である。
大阪大学杉野事件が表面化した際に、私は9月25日のエントリーで《在米期間が長かったと伝えられる杉野教授が、アメリカンスタイルをどうも持ち込んでいたらしい、と私は推測した。》と記した。そして、アメリカンスタイルとはどのようなものか、例を持ち出した説明した。ところがなんとここに実例があったのだ。アメリカの大学で専門教育を受けて学位も得た多比良氏が、アメリカンスタイルを自分の研究室に持ち込んだことをご本人が得々と語っているのである。研究ノートの一件である。
研究ノートの有無が東大多比良事件を特徴づけたぐらいそのウエイトは重い。私は研究ノートを撮した映像の一画面から、多比良氏は助手であった川崎氏に対しても研究ノートの『検閲』を目論んだなとの印象を持った。そう受け取られても仕方のない状況証拠なのである。私の印象がもし正しければ、これは紛れもなく『アカデミック・ハラスメント』になる。この問題は極めて重要であるので、年が明けてからまた取り上げることにする。
それはさておき、多比良氏はこのように仰っている。「私がデータを捏造すると、もっと早い時間に見つかっていた。というのは私は実験をやらないから。うん、実験をやった連中がすぐに気付く。私が何かデータを変えるとね」と。
ご多分に洩れず多比良氏も私が常に問題視する『自分で実験をしない、その実、実験をもはや出来なくなった教授』であったのだ。ところがその「実験をやらない」ことを逆手にとって、「だから私は捏造には関わっていない、それなのになぜ・・・」と暗に自己主張に結びつけるあたりは、さすがアメリカ仕込みの『debater』である。
この点でも聞く側の突っ込みがなかったのが心残りである。私が学生ならちょっと乱暴でも「先生、プロ野球でも、サッカーでも大相撲でも、プレイヤーが現役を退いたら、コーチとか監督とか親方になりますよね。そして後進の指導にあたる。現役のプレーヤーとは厳然と一線を劃しますよね。横綱が優勝すれば表彰されるのは横綱で親方ではない。先生が実験を止めたら現役を退くようなものではないですか。それなのに、先生が現場の研究者と同じように論文に名を連ねるなんて変におもわれませんか」と聞いてみて、反応を心待ちにするだろう。
ひょっとすると、東大の学生諸君にとって、多比良氏のように自分では実験をせずに大勢の教室員を使って『業績』をあげるような教授が目指す理想像なのだろうか、とも思った。それこそげすの勘ぐりで終わって欲しいものである。
このインタビューの映像を観て、それぞれの方がどのような感想を持たれるか、興味津々である。