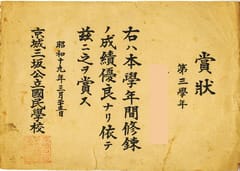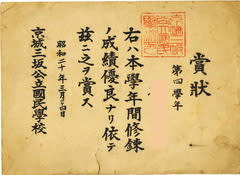5月16日付の読売新聞が《京都大病院の心臓血管外科が昨年末から手術を差し止められていた問題で、同病院は15日、成人患者の手術を今月10日に再開したと発表した。同病院は米田正始(こめだまさし)教授(52)を「手術の安全性が確保できない」として4月1日付で診療科長から解任しており、手術は同科の仁科健・講師が執刀。診療サポーターとして同大出身の坂田隆造・鹿児島大教授が立ち会ったという。》と報じた。
ことのおこりはこのようである。
《京都大病院の心臓血管外科が、昨年12月末から新規の手術を病院側から差し止められていることが18日わかった。
同病院では昨年、脳死肺移植を受けた患者が脳障害を起こして死亡。この問題に関連して内山卓病院長が、安全対策が確立するまで自粛するよう、同外科の米田(こめだ)正始(まさし)教授に指示したという。全国有数の国立大病院で、心臓・血管の手術全般がストップするのは極めて異例だ。
同病院の心臓血管外科は2005年に281件の手術を行った実績がある。患者が死亡した昨年3月の脳死肺移植手術にも、心臓血管外科医が加わっていた。》(2007年1月19日 読売新聞)
京都大病院の心臓血管外科がほぼ五ヶ月間新規の手術を行わず、あまつさえ米田教授がこの4月1日に診療科長を解任されてしまった。米田教授は学生相手の講義はできるのだろうが、病院での心臓血管外科の最高責任者としての地位を追われたからには、現実的に手術を行うことは出来ず、外科医としては髀肉の嘆を託つことになる。まさに飼い殺しの状態である。
米田教授の経歴を拝見すると1881年に京大医学部を卒業し17年後の1998年4月1日に母校の京大医学部心臓血管外科教授として招聘されている。しかし医学部卒業後6年間国内の私立病院勤務を経て日本を離れ、12年間外国で心臓外科医として研鑽を積み母校に戻ってくるその間、出身校の京大病院に医師としての勤務経験のないことが目を引く。そしてこの経歴を拝見して、「もしかして」の思いが浮かんだ。
論文捏造事件で阪大を追われた杉野明雄氏、東大を追われた多比良和誠氏がともに在米期間の長いところに一つの共通点があったが、米田教授もカナダ、アメリカ、豪州での滞在期間が長いことが共通しているからだ。
米田教授は外国のどういう優れたところを日本に持ち込み、定着させようと考えたのだろうか。また京大病院は米田教授に何を期待して招聘したのだろうか。両者にそれぞれの考えがあり、当然意見を交換したことだろう。そして意見の一致を見て教授人事が決定したと見るのが自然である。それが10年という節目を目前にして、両者にとって不幸な仕儀となってしまった。どうしてだろう。
質の高い医療の恩恵を受けることは日本国民が等しく願うところである。今回の出来事もその医療制度のあり方と深く関わっているように私は感じる。ここで私の目を引いた週刊医学界新聞の記事
米田氏へのインタビュー記事を少々長くなるが引用させていただく。
《プロフェッショナルな外科医を育てる-心臓血管外科領域の新しい動向》
経験が足りない日本の心臓外科医
米田正始氏(京都大学教授・心臓血管外科学)に聞く
の大見出しで始まる。(第2519号 2003年1月20日)以下に小見出しだけを引用するが、米田氏が日本における特に心臓外科手術のあり方に批判的であることが推測されよう。
《●国際基準から格段に遅れた日本
日本では外科手術をどれだけ経験できるか
●悪しき諸問題
門番外科
手術周辺の問題
●心臓血管外科医の専門教育について
外科専門医制度とのリンク
日本に専門医は何人必要か》
そしてこのような発言がある。
《欧米では「一人前の心臓外科医」になるには執刀・助手・術後管理とりまぜておよそ5000例ほどの経験が必要です。不文律ですが。年間2000症例をこなす施設なら1人が1000例以上は診るあるいは学ぶことができ、5年でゆうゆうと5000例に達します。最近ではドイツのように、年間3000-5000例の大施設で束ねる国もあり、世界の情勢はより改善方向にあります。日本の現状では、仮に年間50例としたら、欧米の基準に達するのに100年かかる計算になり、せめてその半分の2500を目標としても50年かかり、この違いは致命的です。 》
《この傾向はアジアも同様で、中国も1000例が基準です。上海もそうですし、北京では年間4000例の病院があります。できたばかりで年間300-400例の病院もありますが、1000例ぐらいを目標にしています。》
これに対して日本ではどうか、と言うと、2002年に厚生労働省が「年間症例数100」を外科手術件数の施設基準として示していると言うのである。そこで米田氏はこう主張する。
《基準が1000例を大きく下回っているのは世界で日本だけです。
このままいけば、日本の心臓外科は成り立たなくなり、結局、患者さんに迷惑がかかってしまいます。この意味で年間100例というのは議論の対象にさえならないレベルというのが国際的な見方です。 》と手厳しい。
そしてこう締めくくる。
《高度な専門技術が問われる手術は,熟練した手術チームではじめて可能になります。そして,どんなに手術が上手くても,手術中には不測の事態が起こるものです。運悪く合併症が起こりそうになっても,術後管理を含めて5000例の経験があれば、何か起こりそうだと「ピン」とくるため、すぐに手が打てるのです。一方,経験が少ないと、理屈だけで考えて余計なことをしたり、逆に後手に回ってしまう。外科、特にスピードが要求される心臓外科では、学問というよりは知的スポーツという側面も大きいため、例数がすべてではありませんが、熟練度つまり場数を踏むことは手術に携る者にとって重要です。》
その通りであろうと思う。だからこそ米田教授は手術例数を増やすことに力を尽くしたのであろうが、そのことが周りとの摩擦を産みそれを広げたのかな、というのが私の率直な反応であった。
上の記事によると、京大病院心臓血管外科は2005年に281件の手術を行った実績があるとのこと。手術日が週2日だとして年間延べ100日だから一日に3人。手術チーム数にもよるだろうが、下手すると、というよりそれが常態かもしれないが、1チーム1日に2例ということもありうる。場合によれば3例もありうるだろう。実態は調べると分かることだから、憶測はここで止めておく。
ただ手術例数の数字だけが独り歩きしては実態が見えてこない。例えば上の281例にしても、全て米田教授が執刀医を務めていたとすれば、助手はいつまで経っても助手、それでは一人前の執刀医は育たない。一人の医師が執刀・助手・術後管理のそれぞれに何例ずつ経験することが「一人前の心臓外科医」に必要なのか、それが見えてこない。また欧米で合わせて1年間に1000例と言われても『どんぶり勘定』の中身が見えてこない。自分のところではこのように執刀・助手・術後管理の割り振りを行っている、との実情を語って欲しかった。
それはともかく、米田教授が手術例数を増やす試みが、京大病院における手術室の稼働状況や医療スタッフなどを含めてその処理能力を上回ったことが今回の出来事の根底にあったのではなかろうか。やる気満々の『帰国教授』を迎え入れる大学について回る宿命とも云えようか。
たまたま本屋で見かけた南淵明宏著「医者の涙、患者の涙」(新潮文庫)に目を通した。

南淵医師も米田教授と同じように海外で心臓外科医としての実績を積み上げ、帰国後は挫折も経験しながら、大学病院ではなくある医療法人の病院で心臓外科を立ち上げた方である。大学病院ではなく民間のこぢんまりした病院で自分の技倆を拠り所に患者に尽くす医師の心意気がよく描かれている。
飼い殺しするのかされているのか、立場によって見方が変わるだろうが、いずれにせよ医学教育の中心をなす大学病院で、一つの重要なポストが活用されていないのはいかにももったいない。米田教授は大学を相手に地位確認と3300万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしているとのことであるが、裁判に勝つことの喜びと心臓外科医として患者を救うことの充実感を秤に掛けた場合、どちらにウエイトがかかるのだろうか。活躍の舞台は大学病院だけとは限らない。賢明な選択を期待したいものである。
それにしても京大病院とあろうものが(とは買いかぶりの弁でもあるが)、教授にふさわしい心臓血管外科専門医を自前で育てられなかったという事実が、米田教授の上の意見の正当さを裏付けていると見たはひが目か。