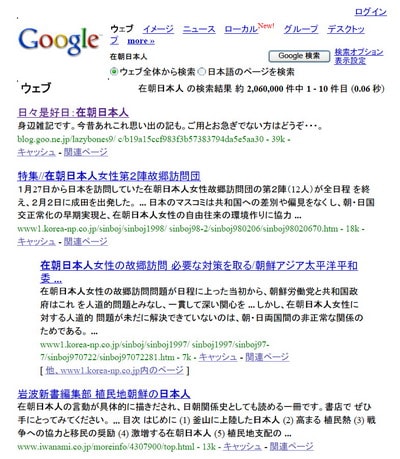多比良教授らの論文、調査委「再現性、信頼性ない」 (朝日新聞) - goo ニュース
大阪大学に引き続いて東京大学でも捏造論文問題にひとまずケリがついたようである。多比良和誠教授らの論文疑惑についての調査委員会委員長によると、「極めて捏造(ねつぞう)したと言えるに近い状態にあるが、断言するのは難しい」とのことである。司法権のない調査委員会が捏造を断言するのは確かに困難であるが、この結論を『黒』と受け取るのが素直であろう。
実験を行ったとされる川崎助手は取材の朝日新聞記者に「確かに実験ノートがなく、信頼性に欠ける部分はあったが、だからといって全く信頼性がないわけではない。論文の再現性についてはもう少し時間がかかる」と語ったそうである。
この引用が正確に川崎助手の言葉だとしても、その内容が素直に伝わってこない。「実験ノートがない」とはどのような状況を指しているのかが分からないのである。実験結果を記載したノートはもともとあったのに紛失したのか、行方不明になったのか、それとも何らかの意図で処分してしまったのか、それとも実験はしていないのでノートがないのが当たり前というのか、そのあたりが分からない。
その何れであるにせよ、実験したという証拠がない以上論文の正当性についてのいかなる主張も成り立たないのは明白である。立証責任のある実験者当人が実験の存在そのものを示すことが出来ないのだかこれで一件落着、さっそく当事者を処分すればいい。
「疑わしきは罰せず」というのは法律上の格言だそうで、「広辞苑」には《犯罪を行ったということが証明されなければ有罪を言い渡してはならないという原則》と記されている。しかし世間の目が簡単に届かないだけより高い倫理性が課せられている『象牙の塔』の出来事であるだけに、捏造論文問題については「疑わしきは罰せよ」を原則にすべきであると私は思っている。
『論文疑惑』が発生すると一番迷惑を被るのは周辺の同僚教授たちである。ただでさえ時間に追われているのに、特に訓練を受けたわけでもない検事や裁判官まがいの余計な仕事を引き受けざるをえないからである。調査にも省エネが望ましく、手っ取り早いのは全ての実験データと実験ノートを提出させてそれを検証すればよい。今回のように実験ノートがない、となればそれだけで『疑惑の存在』を確定すればよい。それ以上の『真相』の追求などはまったくの無意味で時間とエネルギーの無駄遣いである。第一そんな『真相』にいったいどのような価値があるというのだ。厳しく「疑わしきを罰する」ことで研究者に「李下に冠を正さず」の倫理観を一層徹底させることの方がはるかに大切である。
『捏造論文』は詐欺行為そのもので研究者にとってみれば手鏡でスカートの中を覗く以上に破廉恥な行為である。『詐欺犯』を大学が懲戒免職処分してもどこからも異議は出されないだろう。
最後に、「研究管理が不十分だった責任を痛感している。各論文に関する川崎助手の捏造の有無につき、完全な検証には至っていないが、実験に対する誠実性には疑義を持たざるを得ない」とコメントを発表した一方の当事者多比良教授はご多分に漏れずなかなか脳天気なお方である。研究者としての矜恃をひとかけらもお持ちでない。
自分で実験をしない、その実、実験をもはや出来なくなった教授の存在が『捏造論文』の横行を許していると私は思う。何れ改めてこの問題に触れるとしよう。
大阪大学に引き続いて東京大学でも捏造論文問題にひとまずケリがついたようである。多比良和誠教授らの論文疑惑についての調査委員会委員長によると、「極めて捏造(ねつぞう)したと言えるに近い状態にあるが、断言するのは難しい」とのことである。司法権のない調査委員会が捏造を断言するのは確かに困難であるが、この結論を『黒』と受け取るのが素直であろう。
実験を行ったとされる川崎助手は取材の朝日新聞記者に「確かに実験ノートがなく、信頼性に欠ける部分はあったが、だからといって全く信頼性がないわけではない。論文の再現性についてはもう少し時間がかかる」と語ったそうである。
この引用が正確に川崎助手の言葉だとしても、その内容が素直に伝わってこない。「実験ノートがない」とはどのような状況を指しているのかが分からないのである。実験結果を記載したノートはもともとあったのに紛失したのか、行方不明になったのか、それとも何らかの意図で処分してしまったのか、それとも実験はしていないのでノートがないのが当たり前というのか、そのあたりが分からない。
その何れであるにせよ、実験したという証拠がない以上論文の正当性についてのいかなる主張も成り立たないのは明白である。立証責任のある実験者当人が実験の存在そのものを示すことが出来ないのだかこれで一件落着、さっそく当事者を処分すればいい。
「疑わしきは罰せず」というのは法律上の格言だそうで、「広辞苑」には《犯罪を行ったということが証明されなければ有罪を言い渡してはならないという原則》と記されている。しかし世間の目が簡単に届かないだけより高い倫理性が課せられている『象牙の塔』の出来事であるだけに、捏造論文問題については「疑わしきは罰せよ」を原則にすべきであると私は思っている。
『論文疑惑』が発生すると一番迷惑を被るのは周辺の同僚教授たちである。ただでさえ時間に追われているのに、特に訓練を受けたわけでもない検事や裁判官まがいの余計な仕事を引き受けざるをえないからである。調査にも省エネが望ましく、手っ取り早いのは全ての実験データと実験ノートを提出させてそれを検証すればよい。今回のように実験ノートがない、となればそれだけで『疑惑の存在』を確定すればよい。それ以上の『真相』の追求などはまったくの無意味で時間とエネルギーの無駄遣いである。第一そんな『真相』にいったいどのような価値があるというのだ。厳しく「疑わしきを罰する」ことで研究者に「李下に冠を正さず」の倫理観を一層徹底させることの方がはるかに大切である。
『捏造論文』は詐欺行為そのもので研究者にとってみれば手鏡でスカートの中を覗く以上に破廉恥な行為である。『詐欺犯』を大学が懲戒免職処分してもどこからも異議は出されないだろう。
最後に、「研究管理が不十分だった責任を痛感している。各論文に関する川崎助手の捏造の有無につき、完全な検証には至っていないが、実験に対する誠実性には疑義を持たざるを得ない」とコメントを発表した一方の当事者多比良教授はご多分に漏れずなかなか脳天気なお方である。研究者としての矜恃をひとかけらもお持ちでない。
自分で実験をしない、その実、実験をもはや出来なくなった教授の存在が『捏造論文』の横行を許していると私は思う。何れ改めてこの問題に触れるとしよう。