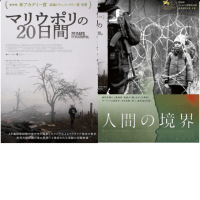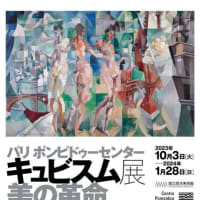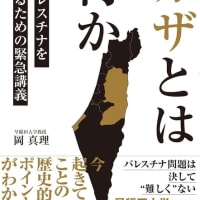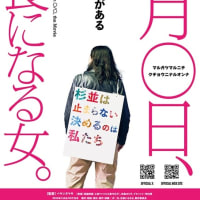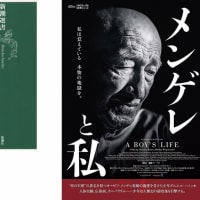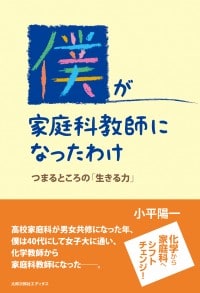
家庭科に男子も共修がはじまったのが1994年(中学。高校は95年)。それより前から、であるからこそ家庭科の男女共修をとの運動があり、小平さんも運動を実感していた。化学から家庭科へ。家庭科が生活の科学であると分かった現在となっては、化学教師から家庭科教師への道は、自然に、合理的に見えるが、当時は変人扱い。息子さんからは「お父さん、左遷されたの?」
小平さんが、家庭科教師に変転しようと思ったのには化学(科学)信奉への疑問と、ジェンダーの問題がある。それも、家事ができないのが当たり前から、妻が働きだして、いや応なしにすることになったイクメン生活。小平さん(1950年生まれ)の世代は学生時代に70年安保を経験したが、「デモの男子学生の後ろでおにぎりを握る女子学生」が当たり前。むろん闘う学生ではなかった小平さんは、デモや学校占拠も経験しなかったが、おにぎりを握ることもなかった。しかし、元来のマメさ、フットワークの軽さ、柔軟さから次第に育児・家事に「目覚めていく」。そしてそれが自然に、そして職業にまで。
いい出会い、環境もあった。初任の所沢高校では、後に所沢市議会議員としてフェミニスト議員連盟を牽引した中嶋里美さんが同僚にいた。また、子どもの保育園などの送迎でいつも遅刻、熱を出した子どもの世話で妻とのやりくりがつかず、子どもを保健室に託したり。要するに職場や同僚に理解があり、大らかだったのだ。今なら、教員だけなぜ恵まれているのだと(別に恵まれているわけではないのだけれども)の非難・攻撃が学校に押し寄せるだろう。現代は、それほど余裕のない社会・時代になったということでもある。
小平さんには、今回、本書をしたためる前提として、リタイア後学んでいる大学院での修士論文がある。そこでは、戦後、そして共修になった家庭科をめぐる状況 ― 良妻賢母の育成から、生活技術としての男子をもの必要性、そして、食品添加物や手作業の要、はては原子力発電など「発展社会」への疑問まで - 時代を反映した社会とのつながりの深さなど、受験科目でない分だけ自由に、そして深く突き詰めているという。
学校教育という画一的、包括的な学習機関には何が求められるのか。「国語」や算数、理科・社会など考えられる科目の外に、いや外にこそ、家庭科がある。家庭で、地域で生活科学を学べなくなった現代。生活科学を学べなくなったということは生活の哲学を学べなくなったということだ。そして、文科省の政権忖度姿勢のもとで、社会科などでは現代の生活、そのもとにある政治への批判、批評精神の醸成はほとんど皆無である。であるからこそ家庭科でできることは多い。小平さんが、手仕事の妙と要を生徒に伝えることで、その後ろにある、社会や世界の問題、に気づく機会をつくったことは大きい。そして、その生き方が小平さんにとって心地よいものであったことがもっと大きい。
小平さんら家庭科教員のがんばりにも関わらず、共修家庭科の単位数はどんどん減ってきている。それは、グローバリズムの名のもとに、英語授業を増やしたり、思い付きの学校「経営」ゆえの現在の単位構成の歪さの証でもある。
小平さんの労苦に思いはせ、「家庭科減った。日本死ね!」と書き込みたいと思う。(2016年1月刊 太郎次郎社エディタス)