おはようございます。ギリシャに始まった「欧州危機」は深みにはまるばかりで抜け出す方策が見つからず、ついには「世界危機」へつながる恐れが強まってきました。
生き生き箕面通信2024(110927)をお届けします。
・司法の正義を崩した小沢氏元秘書裁判の判決
「裁判所もここまで落ちぶれたか」という印象を受けました。小沢一郎氏の元秘書に対して出された東京地裁の昨日の判決は、「司法の正義」をないがしろにし、権力ゲームにまみれた判決といわざるを得ない内容でした。
浮かび上がって見えるのは、最高裁と検察がグルになって、最終的には小沢氏を「なんとしても有罪に持ち込む」という固い決意のシナリオの幕開きです。
小沢氏秘書3人に対する東京地裁の判決は、証拠となる調書を不採用とした段階で、本来なら「無罪」とするのが論理的な帰結のはずです。検察の全面敗北となるところでした。ところが、判決が出てみると一転、「検察の完勝」でした。
考えられるのは、最高裁の介入です。最高裁は、検察調書の証拠不採用が決まった時点で、「このままでは検察の権威が失墜し、ひいては日本の官僚組織全体にヒビが入りかねない」と、危機感を強めたようです。東京地裁の登石郁朗裁判長には、なんらかの働きかけ、つまり”圧力”が加えられたのでしょう。
最高裁は、事務総局を通じて全国裁判官の人事権を握っています。これまでも、権力に不利な判決を書くと、地方に転勤させられたり、昇給をストップさせられた例があります。「モノ言えば唇寒し」の風潮がはびこり、最高裁の顔色をうかがいながらの「ヒラメ裁判官」が増えていました。裁判官の良心が捻じ曲げられ、保身や出世を優先する仕組みに変貌してきたのです。
かつて田中角栄首相(当時)が、ロッキード汚職事件を仕掛けられ、コーチャン副社長に対する嘱託尋問で有罪にされたことがあります。日本の最高裁が「嘱託尋問は違法であり、田中角栄氏は罪に問えなかった」と、角栄氏の死後に立場を認めるこそくなやり方をしました。
あれから30数年、さらに悪質な権力擁護機関としての司法の姿が立ちあがってきました。
今回の判決で見られるように、証拠がなくても裁判官の判断でなんでも「合理的に説明できる」として有罪とすることができるようになりました。少なくともその突破口が開かれたわけです。客観的証拠に基づかなくても、有罪に持ち込める。恐ろしいことです。
これに対して、本日の大手紙は、朝日、読売、毎日、すべてそろって「検察勝利」を高く評価し、「権力裁判」を歓迎しています。ジャーナリズムも崩壊です。
官僚が支配する、国民を単なる統治対象とする時代がやってきました。これも国民が民主主義をないがしろにして、「お任せ民主主義」によりかかってきた帰結です。














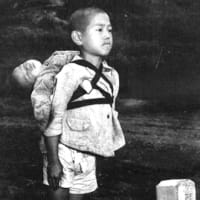

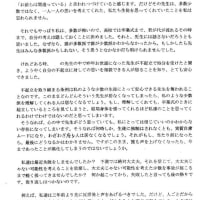
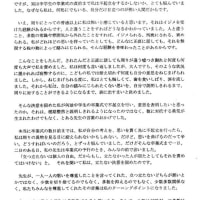


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます