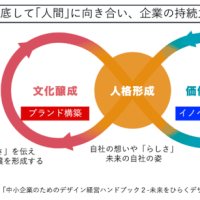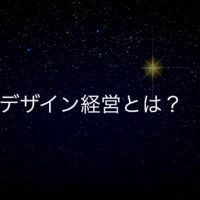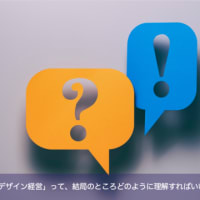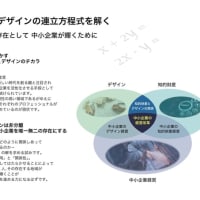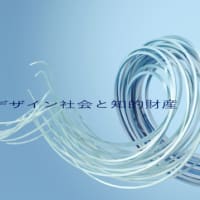「頭のいい人が儲からない理由」を読みました。アクの強い本なので好き嫌いが分かれそうですが、基本的なものの考え方で、ハッとさせられるようなことがいくつ書かれています。
その中に、
「閾値を超えるまで続けよ」
という話があります。1の努力と2の努力の差は単に2倍の結果の違いとして表れるのではなく、その間に飛躍的な効果の差を分ける閾値が存在していれば、結果の差は5倍になることだってある、ということです。従って、何かを始めるのであれば、そこまでは続ける覚悟をしなければ意味がない。この感覚は、仕事や勉強、スポーツなどの経験で実感された方も少なくないのではないかと思います。
知財業務の効果についても、あるレベルのところに「閾値」が存在していると思います。その閾値は、量を基準として決まるものだけでなく、時間を基準にした閾値も存在しているように思います。そして、その閾値は、知財業務に初めて取り組む企業が期待しているよりも、通常はかなり高い水準に存在していることが多いのが厄介なところです。
特にベンチャー企業の知財業務への本格的な取組みをサポートする際には、この閾値の存在とおおよそのターゲット(最初から明確に見えるものではないですが、2年くらいは頑張りましょうとか、10件くらいの出願を目指して特許ポートフォリオを作っていきましょうとかいった目標)を示していくことも必要なのではないでしょうか。
その中に、
「閾値を超えるまで続けよ」
という話があります。1の努力と2の努力の差は単に2倍の結果の違いとして表れるのではなく、その間に飛躍的な効果の差を分ける閾値が存在していれば、結果の差は5倍になることだってある、ということです。従って、何かを始めるのであれば、そこまでは続ける覚悟をしなければ意味がない。この感覚は、仕事や勉強、スポーツなどの経験で実感された方も少なくないのではないかと思います。
知財業務の効果についても、あるレベルのところに「閾値」が存在していると思います。その閾値は、量を基準として決まるものだけでなく、時間を基準にした閾値も存在しているように思います。そして、その閾値は、知財業務に初めて取り組む企業が期待しているよりも、通常はかなり高い水準に存在していることが多いのが厄介なところです。
特にベンチャー企業の知財業務への本格的な取組みをサポートする際には、この閾値の存在とおおよそのターゲット(最初から明確に見えるものではないですが、2年くらいは頑張りましょうとか、10件くらいの出願を目指して特許ポートフォリオを作っていきましょうとかいった目標)を示していくことも必要なのではないでしょうか。
 | 頭のいい人が儲からない理由講談社このアイテムの詳細を見る |